教師に必要な能力はいろいろ考えられるだろうが、欠かせないものの1つに話術があるだろう。
人並み外れて話が上手でないにしても、最低限、子供の手本としてふさわしくないような話し方だけは避けるべきである。
この点については、これまでいくつものうんちくを書いているので参照いただきたい。
では、上手に話すにはどうしたらよいだろうか。
発音がきれいで文法的に正しい日本語を話すだけでは不十分である。教科書に書いてある文章をアナウンサーのように読んだだけで、子供が学習内容を理解するかというとそうではない。
上手な話し方を考える前に、学習指導というものについて少し確認しておこう。
学習するということは、新しいものを理解する(覚える・身につける)ということである。しかし学習者にとって全く未知のものを理解させるということは難しい。例えば、音楽の階名(ドレミファ‥)を知らない人に和音の構成を教えても理解できないだろう。
下の絵のようにも例えることができるだろう。
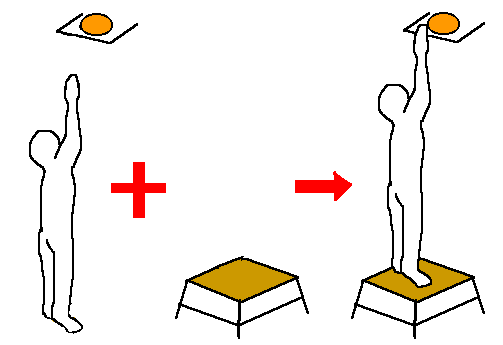
(あまりうまく描けなかったのでわかりにくいが‥‥)棚の上にミカンがある。
自分の身長だけでは棚に手が届かない。そばに踏み台があったので、それに上がったらミカンを取ることができた。
学習者にとってちょうどいい学習というのは、既に身につけている能力を生かして(それを土台にして・それを組み合わせて)新しい能力を手に入れることである。
上のミカンの例でいうと、新しく手に入れたい能力は「棚の上のミカン」にあたる。「既に身につけている能力」にあたるのが「自分の身長」と「踏み台」である。
自分の身長がもう少し低いとミカンには手が届かない。また身長はあっても踏み台がなければ、やはりミカンを取ることはできない。
2つの要素(能力)が備わっていて、それをうまく組み合わせることができたときにだけ、目標に到達することができるのである。
小学生全体を相手にして、あまり上手ではない話し方をする例を見ることがある。
「明日から楽しい夏休みですが、充実した生活ができるように次の5つのことを頑張りましょう。1つ目は学習を頑張るということです。2つ目は規則正しい生活をしようということです。3つ目は事故のない安全な生活をしようということです。4つ目は長い休みを利用して身体の悪いところを治しましょうということです。5つ目は家族の一員として自分ができるお手伝いをしようということです」
こんな話し方をしても小学校1年生・2年生あたりの心に響くわけがない。こんな話だったら小さい子供は聞いたそばから忘れてしまう。残るのは「子供たちに一応は注意をした」という自己満足だけである。
私が若い頃にお世話になったI校長先生は子供に話をする達人であった。夏休みの前に次のような話をされた。
- 小学校3年生のタケシ君がおりました。夏休みに入って3日め、とても暑い日だったのでタケシ君は先生から「行ってはいけない」と言われていた近所の川にひとりで泳ぎに行ってしまいました。
- タケシ君が気持ちよく泳いでいると、川にすむカッパがタケシ君の足を引っ張りました。カッパの強い力にひきずられるとタケシ君は川の深い渕の底に沈んでいきました。
- タケシ君の口や鼻から出たたくさんのあぶくが、水の上の方に上っていきました。そのキラキラ光るあぶくの中に、タケシ君はお父さんやお母さんの顔が見えたような気がしました。しかし、タケシ君は大好きなお父さんやお母さんに二度と会うことはできませんでした。
I校長先生が話したのはこれだけである。しかし、子供の心には「夏休みに危険なところで泳いではいけない」ということが強く刻まれたはずである。中には涙を流して聞いている子供もいた。
若い教師だった私も、「話とはこうやってしなければいけないのだ」ということを学ばされた。おそらく終業式に出ていた教師は全て同じように感じたはずである。こういう達人の技を見ることができた私は幸せであった。(こういう話をするために、I校長先生は何日も前から原稿を書き、推敲し、練習していたのだそうだ)この頃は上の拙い例のような話を聞くことが多く(しかもあまり準備もしていないのか、話し方自体もこなれていない)改めてI校長先生の素晴らしさを認識するとともに、今の子供たちや若い教師がI校長先生のような素晴らしい話を聞くことができない不幸を痛感する次第である(^^;)
話がちょっと脇道にそれてしまったが、上手に話すには例え話をうまく使うことだと私は考える。
話の聞き手が自分の既得体験として共感的にとらえられる例え話を使うと、伝えたいことをスムーズに理解してもらえる。
また話がそれるのだが、私がパソコン講座の講師をやるとき、コンピュータの基本としてビットとかバイトの説明をする際には次のような例えを使うことが多い。
- コンピュータって何かというと、簡単に言えばスイッチの集まりです。この部屋には4つの蛍光灯がありますね。それを点灯するためのスイッチも4つあります。
- スイッチ1つだけだと蛍光灯を点けるか消すかだけですから、「○」か「●」かの2通りになりますね。
- これがスイッチ2つになると、「○○」「○●」「●○」「●●」の4通りになります。
- この部屋のようにスイッチが4つだと、どうなるでしょう?
- 「○○○○」「○○○●」「○○●○」「○○●●」
- 「○●○○」「○●○●」「○●●○」「○●●●」
- 「●○○○」「●○○●」「●○●○」「●○●●」
- 「●●○○」「●●○●」「●●●○」「●●●●」
- のように、16通りになりますね。
- では、スイッチが8個あったら何通りの組み合わせが考えられるでしょう? そう256通りですね。
- コンピュータでは、スイッチが1個だけのときの2通りのデータを「1ビット」、この1ビットが8つ集まった256通りのデータを「1バイト」と呼びます。「1ビット」のデータは「0」か「1」という2進法で表現しますが、「1バイト」のデータは256種類もあるので、それらの1つ1つを「01001011」のように表現するのは大変ですから、前述の4つのビットが集まった例(スイッチが4つある16通りの例)に「0・1・2・3・4・5・6・7・8・9・A・B・C・D・E・F」のような16進数の呼び名をつけ、8ビットの前半部分4桁と後半部分4桁に分けて「38」とか「F2」「CE」のように表現します。
こんな具合に話を進めれば、最初は部屋の中にある4つの蛍光灯という具体的に目に見えるものから理解してもらい、後段になると実際には見ることができない256個の蛍光灯というような概念的な世界に理解を進めてもらうことができる。
同じくパソコン講座で話をする例なのだが、ワープロソフトなどは器用に使えてもコンピュータ操作の基本になるファイル管理などの知識がない人の例を「自動車は上手に運転できても、自動車の基本構造を理解していない人」に例えたりすることもある。
いずれにしても、聞き手が自分のものとして持っていない知識や概念を、既に持っている知識・概念を例えに使ったり、それを組み合わせたり発展させたりすることによって理解・体得してもらうという方法である。
聞く人によくわかってもらえる話や説明をするためには、聞き手がどの程度の既得知識を持っているかをきちんと把握することとともに、そのレベルの知識の人でも簡単に理解できる例え話のネタを数多く持っていることが大事である。
簡単な例だと、プリンを知らない人にプリンのことを説明するには「茶碗蒸しの黄色い部分のようなもの」という具合になるし(^^;)、ちょっと複雑な例だと、コンピュータの記憶媒体の「FAT(File Allocation Table)」を「本の目次や索引のようなもの」に例えるなどというのもある。
当たり前のことを当たり前のように話すこと自体には何の問題もないのだが、聞く側の立場になってみると、そういう話はつまらないしインパクトもない。
冒頭に書いたように、話術は教師に必要な能力の大きな部分を占める。誰でも言えるような当たり前の表現しかできない能力しかない教師は、教師としての能力に欠けるということになる。
力のある教師になるためには、日頃から言葉に対する感覚を鋭くして、効果的な例え話に使えるネタをたくさん持っていることが大事なのではないかと、私は考える。
<02.06.01>