学校図書館には文学を
私が小学生の頃、学校の図書室は宝の山のような感じだった。
たくさんの物語が私を待っていた。図書館から借りた本の世界の中に没頭した期間がしばらくあった。
なお、「図書館」と「図書室」という言葉を混ぜて表記したが、教室とは別の建物の「図書館」を持っている学校は少ないだろう。建築としての観点では「図書館」ではなく「図書室」なのだが、学校図書館法によると「学校図書館とは学校において、図書、視聴覚等資料を収集し、整理し、保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供する‥‥学校の設備をいう」とあるので、機能としての観点では「図書館」ということにする。
子供の頃の学校図書館には、無限に本があったような印象があるのだが、自分が教員になってみると、意外に学校図書館の本が少ない感じがする。
学校図書館にはどのくらいの蔵書数があればよいのかという基準が、下の「学校図書館図書標準」である。平成5年(1994)3月29日に文部省が設定し、「学校図書館図書整備新5カ年計画」を策定して目標達成をめざした。
文部省の学校図書館図書標準
|
小 学 校
|
|
中 学 校
|
|
学級数
|
蔵書冊数
|
|
学級数
|
蔵書冊数
|
1
|
. 2,400
|
|
1〜 2
|
. 4,800
|
2
|
. 3,000
|
|
|
|
3〜 6
|
. 3,000+520×(学級数− 2)
|
|
3〜 6
|
. 4,800+640×(学級数− 2)
|
7〜12
|
. 5,080+480×(学級数− 6)
|
|
7〜12
|
. 7,360+560×(学級数− 6)
|
13〜18
|
. 7,960+400×(学級数−12)
|
|
13〜18
|
.10,720+480×(学級数−12)
|
19〜30
|
.10,360+200×(学級数−18)
|
|
19〜30
|
.13,600+320×(学級数−18)
|
31〜
|
.12,760+120×(学級数−30)
|
|
31〜
|
.17,440+160×(学級数−30)
|
(平成5年3月29日設定)
この標準表だけでは、わかりにくいので、学校規模(学級数)ごとの早見表にしたのが下の表である。
文部省「学校図書館図書標準」学級数別早見表
|
小 学 校
|
学級数
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
蔵書冊数
|
2400
|
3000
|
3520
|
4040
|
4560
|
5080
|
5560
|
6040
|
6520
|
7000
|
学級数
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
蔵書冊数
|
7480
|
7960
|
8360
|
8760
|
9160
|
9560
|
9960
|
10360
|
10560
|
10760
|
学級数
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
蔵書冊数
|
10960
|
11160
|
11360
|
11560
|
11760
|
11960
|
12160
|
12360
|
12560
|
12760
|
|
中 学 校
|
学級数
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
蔵書冊数
|
4800
|
4800
|
5440
|
6080
|
6720
|
7360
|
7920
|
8480
|
9040
|
9600
|
学級数
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
蔵書冊数
|
10160
|
10720
|
11200
|
11680
|
12160
|
12640
|
13120
|
13600
|
13920
|
14240
|
学級数
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
蔵書冊数
|
14560
|
14880
|
15200
|
15520
|
15840
|
16160
|
16480
|
16800
|
17120
|
17440
|
平成10年でひととおり計画が終了したので、それに続く「第2次整備計画」が策定されればよかったのだが、残念なことに、財源難等で見送られて現在に至っている。
この「図書標準」がどの程度達成されているかという調査結果が平成12年8月に文部省から発表されている。
次の表は全国の小中学校の総計である。ちょっと数字が大きくなるが、標準冊数をもとにして整備状況を計算してみた。
|
蔵書冊数合計
|
標準冊数合計
|
整備率(%)
|
|
小学校
|
149,763,917
|
171,387,278
|
87.4%
|
|
中学校
|
79,369,288
|
103,449,168
|
76.7%
|
数字だけではわかりにくいので、グラフにしてみたのが下の図である。
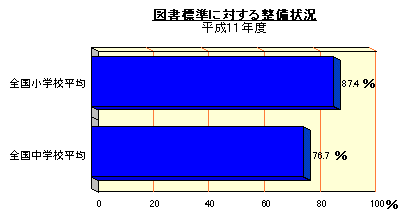
上のデータは、全国の総数をもとに計算したのだが、各学校の整備状況は次のグラフのようになっている。
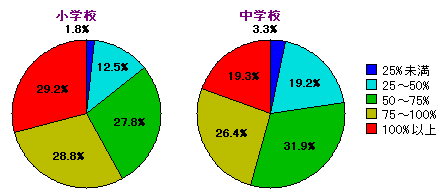
円グラフの赤い色の部分が標準以上の蔵書を持つ学校である。小学校では約3割、中学校で約2割が文部省の標準をクリアしていることになる。
別の見方をすれば、小学校の7割、中学校の8割で、まだ標準冊数に足りない整備状況であるといえる。特に標準の半分にも満たない学校が、小学校で約14%、中学校ではなんと20%もある。
この図書標準は前述のように平成5年に作られたものなので、私の子供の頃にはどうだったのかわからないのだが、あの頃は今よりも子供の数が多かったから、実際に冊数が多かったのかもしれない。
近年だと、いたみのひどい本は廃棄処分しているが、昔はかなりボロボロになったり黄ばんだりした本も多かったので、たしかに冊数はあったような気がする。
いずれにせよ、まだ学校図書館の本は不足気味の現状なので、新しく購入する必要があるのだが、前述の調査結果では平成11年度時点で、1校あたりの不足冊数が、小学校で2,134冊、中学校で3,568冊。今どきだと本の価格の平均は2,000円程度になるから不足を補うためには、4百万円から7百万円のお金が必要である。
これに対して、図書購入のための年間予算は、小学校の平均が47万円、中学校平均が71万円とのことなので、この調子でいけば、今ある本を全く廃棄しなくても、標準冊数に達するまでに、あと10年はかかることになる。
上記の調査結果によると、1校あたりの年間購入冊数が、小学校で約280冊、中学校で約370冊になっている。全国平均なので一概に計算はできないのだが、とりあえず、予算額を冊数で割ってみると次のようになった。
小学校 47万円 ÷ 280冊 = 約 1,678円
中学校 71万円 ÷ 370冊 = 約 1,918円
これを本1冊の価格ととらえれば、私が「本の価格の平均は2千円程度」と述べたのも、まちがいではないようだ。
さて、前置きが長くなったが(^^;)‥‥(「エーッ? ここまでが前置きなの!」と驚かないでほしい)本題に入ろう。
限られた少ない予算ではあるが、毎年、学校図書館に新しい本を買うことができる。そのときにどんな本を買ったらよいのだろうか。
私の知る範囲では、ここしばらくの間、理科や社会科の学習に役立つような本を多く買っている学校が多かったように思う。
図書館が単なる読書の場としてだけではなく、「学習センター」として「調べ学習」の場としても機能するようにということで、これまで不足気味であった理科・社会科などの分野の本を増やしたのだ。
同時に古くなった本は廃棄されていくので、物語・童話・詩歌などの文学領域の本(これらは古くなったものが多い)の比率は少なくなってきた。私が「図書館の本が少ない」と感じたのは、そういう事情もあったのかもしれない。
今でも「調べ学習」は学習活動の中で重要な位置を占めるのだが、インターネットが普及してきたこの頃では、だいぶ様相が変わってきた。
理科や社会科の調べ学習の資料としては、本よりもインターネットのほうが有効になってきたのだ。
社会科でも歴史関係の本のように、一度買えば20年くらいは活用できるものもあるが、産業の様子などを書いた本は数年たてばデータが古くて使い物にならないという例もある。
理系の本も同様で、現任校の図書館にある「コンピュータの本」などは、購入して4年しかたたないのに全く使えない。なにしろ「ベーシック(BASIC)のプログラムを打ち込んでゲームを作ってみよう」などという内容なのだ(^^;)
ということで、これから図書館の本を購入するときには、理科や社会科などの調べ学習に使う本は、どうしても必要で、かつ、買ったら10年以上は使えるという内容の本にとどめ、文学関係の本をたくさん買うようにしようというのが、私の考えである。(低学年向きの本の場合はちょっと事情が異なるが‥‥)
そのかわり、調べ学習の資料はインターネットを活用することにする。最新の情報が入手できるし、必要な情報だけを検索・収集できるので、効率的だし経済的でもある。
文学関係の本の価格が1,000円台と比較的安価なのに対し、理社系の本は2,000円以上のものが多い。カラー印刷などで体裁や製本が立派なことや、あまり売れない種類の本であるということがその理由だろう。
インターネットはお金がかかるという印象があるが、実際には本よりもずっと経済的である。
学校で使用する場合は、プロバイダへの契約料や電話回線の使用料等でも優遇されている。仮に一般ユーザーなみの料金を払ったにしても、1時間で200円程度(実際には優遇措置で100円もかかっていない)である。授業でしょっちゅう使っているような状態でも月に2万円はかからない。(現任校では常時接続しても、プロバイダ契約料が年間8千円、通話料が年間10万円程度である)
1年間、利用しまくっても、理社系の本30冊程度のお金で間に合う。
インターネットで資料を見るだけでなく、必要な部分を印刷して資料として使いたいという場合でも、印刷コストは1ページ10円程度である。市販の本と違って、本当に必要なデータだけを印刷できる。100ページ印刷して千円だから市販の本よりもずっと安い。印刷したものはフォルダに入れて保存をしておけば図書資料としても活用ができる。
この文章の最初のほうにある「学校図書館法」でも、図書館の資料は「図書、視聴覚等資料」となっているので、インターネットの情報も立派な図書館資料である。図書費をインターネットのために使っても問題はないと思う。
新鮮な情報を入手し活用する場面では、インターネットが書籍にとってかわることになるだろう。(ただし、低学年ではインターネットの使用技能の問題や、資料の内容の関係で、まだ書籍資料のほうが有効だと思う)
理社関係の本を買わなくなったお金をインターネットにむけるのもいいが、本来、インターネットにかかる経費は別枠で確保すべきである。図書購入費は、もっと文学書に向けたいものだ。(文学といっても名作文学だけではない。一般の小説、創作童話、絵本などでもよい。いわゆる物語系の本という意味である)
実は、これが私の本音である(^^;)
「うんちく講座」No.173「おきかえる力」でも書いたのだが、物語を読む効果は大きい。心が育つだけでなく、頭がよくなる(^^;) (このことについてはNo.173「おきかえる力」を参照いただきたい。No.241「少年少女世界の名作文学」でも少し触れている)
学校図書館が学習センターとしての機能を備え、子供たちがそこで活発に学習するのもよいのだが、私の個人的な感覚では、図書館は目眩くような文学への世界の入り口であってほしいものだと思う。
まあ、これは、放課後の誰もいない薄暗い図書室で、たくさんの本の背表紙を飽きることなく眺めていた、私の少年時代へのノスタルジーなのかもしれないが‥‥(^^;)
ここで文章を終われば、かなりロマンチックなのだが、例によって艶消しの余談である(^^;)
文学の本をたくさん揃えるといっても、読書感想文コンクールの課題図書を大量に買うのは、ちょっといただけない。(実際はそういう例がかなり多い)
課題図書に選ばれるぐらいだから、内容は素晴らしいものが多いが、学級数の多い学校などで、各学級に課題図書が行き渡るように、同じ本を10数冊ずつ買うのはもったいない。毎年これを繰り返していると、同じタイトルの本がたくさんならんだ図書館になってしまう。
学級全員で一斉に同じ本を読んで、感想等を語り合うという「集団読書」という方法もあるので、それに使えないわけでもないが、学級全員に行き渡るにはちょっと足りない冊数である。これは無駄だ。(集団読書をやるためには、それ専用の1冊100円程度の薄い冊子がある。これを使うべきだ)
ただでさえ蔵書数が不足気味の学校図書館なのだから、貴重な図書購入予算のかなりの部分を読書感想文コンクールの課題図書購入に費やす必要はない。買うにしても、せいぜい1種類につき2冊程度でじゅうぶんである。もっと学校としてのポリシーを持った本選びをするほうがよい。
蔵書数は5,000冊だけど、実際にある本の種類は1,000種類という図書館よりも、冊数は4,000冊しかないが、それが全部違う本という図書館のほうが、(私が読み手だったら)魅力を感じる(^^;)
<00.12.17>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ