最適化の邪魔者を消す
新しいパソコンは動作が速い。CPUの性能がアップし、搭載メモリも増えているからだろう。ハードディスクやCDドライブの読み書き速度も向上している。新しいOSも高速化に貢献しているようだ。
そんな新しいパソコンも、新しいアプリケーションをインストールしたり、ファイルの読み書きを繰り返したりしているうちに、ほんの少しずつ(意識できる程度ではないのだろうが)動作速度が遅くなってくる。
遅くなる理由は2つある。
それを改善すれば、新しいパソコンの性能をフルに引き出すことができるし、古いパソコンでも(若干ではあるが)快適な動作環境を得ることができる。
遅くなる理由の1つめは、ハードディスク内のファイルの配置が雑然としてくることである。
新しいパソコンのハードディスクの中は、最初はファイルが整然と配置されているが、不要なファイルを削除したり新しいファイルを書き込んだりしているうちに、下の図のように、ファイルの配置が雑然としてくる。
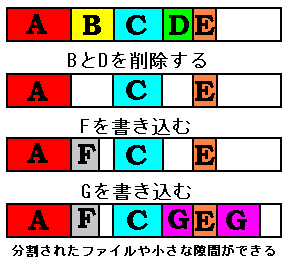
アプリケーションが動作するとき、ハードディスクの中のいくつかのファイルを読み込んで動くのだが、それらのファイルが連続した場所に配置されていれば読み込みは速くなる。しかし、必要なファイル群がハードディスクの中のあちこちに散在していれば、ハードディスクの読み込みヘッドが動き回らなければならなくなって、読み込み速度が落ちる。
CPUの処理速度が速く、ハードディスクの読み込み速度も向上しているので、使用者がその遅さを認識するということはほとんどないと思うが、パソコンのほとんどの処理がデジタルで超高速に行われている中で、ハードディスクの読み書きだけは、ヘッドが移動するという目に見える動きで行われているので、ヘッドがあっちに行ったりこっちに行ったりすることを繰り返すと、処理速度が遅くなる大きな原因になるかもしれない。
ハードディスクの中のファイルが雑然となっているのと整然となっているのの違いをイメージにしてみたのが下の図である(^^;)

例えば運動会の際に、リレーチームを招集するとする。
左の「未整理の状態」の場合には、たくさんの人間の中から、自分のチームのメンバーを1人ずつ呼び集めなければならない。ところが右のような「最適化の状態」になっていれば、既に整列している自分のチームをそのまま連れていけばよいことになる。
これをパソコンで行うのが「最適化」の作業である。
Windowsパソコンでは「マイコンピュータ」から最適化したいドライブの「プロパティ」を開き、「ツール」をクリックすれば「最適化」が出てくる。あるいは「プログラム」から「アクセサリ」を選び、その中の「システムツール」を開くと「デフラグ」というのが出てくるので、それをクリックしても同じである。
WindowsMEまでのパソコンだと、「詳細を表示する」を選べば、画面いっぱいに「裏返したマージャンのパイ」のようなものがたくさん表示されて、それらが並べ替えられ、整理されたものの色がどんどん変わっていく様子を見ることができる。WindowsXPでは、大容量ハードディスクを考慮したためか、ハードディスク全体を帯グラフのように表示して、その中が整理されていく様子を見せる方法に変わっている。
パソコンを買ってから長い間、一度も最適化を行っていないと、最初の最適化では数時間もかかる場合もあるが、2回目以降、月に1・2度のペースで最適化を行えば、数十分で作業が終わる。(パソコンの使用状況によって差が出るが)だいたいは夕食や入浴の時間程度で済む。長くかかりそうな場合は、寝る前に作業をスタートさせれば、朝起きたときには終わっている。
余談になるが、10年位前のMS-DOS時代には、「ノートン・ユーティリテイ」とか「エコロジーⅡ」といった市販のファイル管理ソフトに最適化の機能があった。けっこう懐かしい。今はWindowsに最初から備えられているのでありがたいことである。
最適化をやっていると、「破損されたファイルがあるので最適化ができません。スキャンディスクを行ってみてください」というような意味の警告が出る場合がある。こういうときは指示通りスキャンディスクをやってからでないと最適化作業ができない。
パソコンがフリーズし、どんな操作をしても回復できなくなって「電源切断」という強制終了をした場合なども、次回の起動時にスキャンディスクしなければいけないということもあるが(このことについての詳しい記述や、起動時にスキャンディスクをさせない方法などについては、うんちくNo.326『はずれパソコンのつき合い方』を参照いただきたい)そうでなくてもスキャンディスクはときどき実行しておきたい。ハードディスクの中に破損したファイルがあるとディスク容量の無駄遣いになるだけでなく、動作不良の原因にもなるからである。
ところが、最適化(デフラグ)やスキャンディスクを実行すると、作業が途中で中断され最初からやり直しになってしまい、最後まで実行することができないという状態になることがある。
キー入力やマウス操作が一定時間行われないと、スクリーンセーバーが起動したり、省電力モードに入るなどというのも問題なので、最適化やスキャンディスクを行う際にはスクリーンセーバー等が動作しないようにしておくのも大事なのだが、そうしておいても最適化やスキャンディスクが最後までできないということがある。
実はこれが、パソコンの動作を遅くしている2つめの原因でもある。
この現象を起こす張本人は、「常駐プログラム」と呼ばれるものである。
WindowsMEまでだと、「\WINDOWS\スタートメニュー\プログラム\スタートアップ\」というフォルダを見れば、パソコン起動時に自動的に実行されるプログラムを見ることができる。
自分で設定した覚えがなくても、ここにいくつかのプログラム(あるいはプログラムへのショートカット)が入っている場合がある。これは何かのアプリケーションをインストールした際に、そのアプリケーションが勝手に設定しているのである。
基本的には、ここにはもともと何もなかったのであるから、もし何か入っていたとしたら全て削除してもパソコンの動作自体には全く影響がない。反対にこの機能を利用して、この「スタートアップ」に自分がいつも使うプログラム(のショートカット)を入れておけば、パソコンを起動するとそのプログラムがひとりでに起動するようになるので、使ってみても面白い。例えばワープロソフトをここに設定しておけば、パソコンを起動すると同時にワープロが起動するという具合である。(このへんは、MS-DOSの「autoexec.bat」に起動アプリケーションを書いておくのと同じである)
ところが、この「スタートアップ」に入っているものを全部消したとしても、いわゆる「常駐プログラム」を全部消すことはできない。
最適化やスキャンディスクを行っているときに作業を中断させる邪魔者が消えないことがある。
常駐プログラムのいくつかは、パソコン画面右下の「タスクトレイ」に姿を現している。(下の図のような具合である)

新しいアプリケーションなどをインストールしているうちに、このタスクトレイに表示されるアイコンがどんどん増えて、なかにはここに10個近いアイコンが並んでいるパソコンを見ることもある。
そのアイコンを右クリックして「このプログラムを終了させる」という処理ができるものもあるが、その場では終了しても、次回の起動でまた出てくるのがほとんどなので始末が悪い(^^;)
常駐プログラムが全てタスクトレイに表示されるわけではなく、目に見えないところで常駐しているプログラムもたくさんある。
この常駐プログラムというシロモノ、中にはパソコンを動作させる上で欠かせないものもあるのだが、そのほとんどは「小さな親切、大きなお世話」という性質のものが多い(^^;)
たとえばマイクロソフトのワードとかエクセルといったプログラムインストールすると、ワードやエクセルを動作させるときに、その関係ファイルを高速サーチさせるような常駐プログラムが勝手に設定されてしまう。一太郎等のジャストシステムのプログラムをインストールすれば同様にジャストシステムのアプリケーション用の高速サーチプログラムも常駐してしまうのである。
また、複数のFEP(日本語用フロントエンドプロセッサ)をインストールすると、上の図の例のようなFEPを切り替えるためのアイコン(上の例では四角に15と書かれているようなもの)も出てくる。常時、複数のFEPを切り替えて使うというユーザの場合は必要だろうが、FEPは「ATOKだけ」などという私のようなユーザは、このアイコンも不要である(後述する方法で消すことができる)
常駐プログラムの多くは、パソコン全体の動作のためというよりは、特定のアプリケーションが動作するために便利というものが多い。
例えば(パソコンの動作とは違う例だが‥‥)100mを速く走るというためには、前もって陸上用のスパイクを履いておいたほうがよいというので常にスパイクを履いておく。さらに武器を持った敵と戦うのに備えて重装備の鎧(よろい)も着ておく。夜間に遠くの敵を発見できるように赤外線遠視カメラも携帯する‥‥という具合に、常駐プログラムが多くなると、特定のプログラムを動作させる時には反応が速くなるものの、平常時には重装備がかえって仇になってパソコンの動作を遅くするということにもなりかねない。
さらには、定期的にパソコンの状況をチェックするような常駐プログラムがあると、前述のように「最適化」や「スキャンディスク」を邪魔してしまうということにもなる。
これらの常駐プログラムがたくさんあると、システムリソースが常駐プログラムの分だけ減少する。システムリソースはパソコンの搭載メモリには関係がないので、搭載メモリを増やしてもシステムリソース減少問題は解決できない。パソコンの動作を軽快にするためには、できるだけ常駐プログラムを少なくしておいたほうがよいのである。(システムリソースが足りなくなると『システムリソースが不足なためアプリケーションを起動できません』という事態になることもある)
常駐プログラムを少なくするには「システム設定ユーティリティ」を使う。
具体的には、「スタート」ボタンから「ファイル名を指定して実行」をクリックし、開いた窓に「msconfig」と入力して「Enter」キーを押すとよい。すると次のような画面が開く。ここで下の図のように「スタートアップ」タブをクリックし、そこで表示された常駐プログラムのチェックをオフにすればよい。(システム設定ユーティリティについての詳細は、うんちくNo.326『はずれパソコンのつき合い方』を参照)
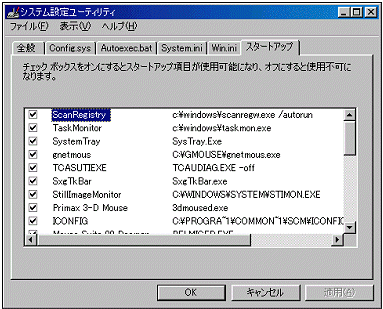
※ ただし、「msconfig」が使えるのは、Windowsの「98・ME・XP」だけで、「95・NT・2000」ではできない。
ここのチェックを不用意にオフにしてしまうのは危険がある。例えばこの全てをオフにしてしまったら、まちがいなくパソコンは正常に動作しなくなってしまう。
では、どれをオフにして、どれをオンにしたらよいかというと、正直なところ私もわからない(^^;)
1つずつオフにしてみて動作を確認するという「試行錯誤法」もあるだろうが、おなじみの「Windows処方箋」の中のこのページに常駐プログラムの具体例が詳述されているのでご参照いただきたい。
自分で普段使わないものは全て外してしまったほうが、パソコンの動作がすっきりするし、トラブルもなくなる。
パソコンは買ったままで使っているという方も多いだろうし、それでも通常の使用には支障がないかもしれないが、実際にはパソコンに不要な仕事をさせていて、その結果、処理速度が落ちているということもあるのではないだろうか。
気になった方は、ご自分のパソコンの動作状況をチェックしてみてもよいかもしれない。
<02.09.22>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ