ルビを読んでしまう
子供向けの本を読むことがある。
昔、読書少年だった(今はほとんど本を読まない)私には、大人の文学よりも子供向けの本が面白かったりする‥‥(^^;)
(それはさておき)小学校の国語教師は小学生向けの本を、中学校の国語教師は中学生向けの本をできるだけ読んだほうがいいように思う。
私があまり好きでない「読書感想文コンクール」(こちら参照)の審査員を若い頃は何度かやったことがあるが、審査会の前には自分が審査を担当する学年の課題図書は必ず読むようにしていた。読んだこともない本についての児童の感想文を審査できるはずがないからである(中には読んでいない審査員もいるようだが)
そういう意味で、課題図書でない自由読書の審査というのは無理があると思う。「フランダースの犬」とか「車輪の下」「蜘蛛の糸」のような誰でも読んだことがあるような名作文学についての感想文なら審査もできるが、新しい児童向けの創作物語の類になると大半の審査員はその本を読んだことがないはずである。その感想文を審査しようというのだから、かなり無茶苦茶なハナシである(^^;)
おっと余談に逸れてしまったので本題に戻ろう。
子供向けの本には、漢字にふりがながついているものが多い。下の画像のような感じである。
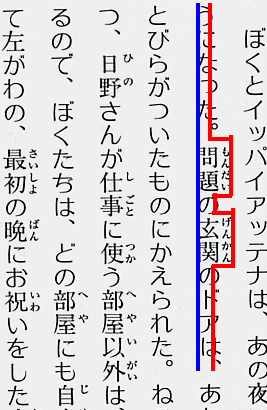
上の図の青い線は、ふりがながついていない場合の視線の動きである。ふりがながあっても同様に視線が動く人が多いかもしれない。
ところが、私の場合、ふりがながあると、図の赤い線のように、漢字ではなくふりがなの方を読んでいるような気がする。
皆さんはどちらだろうか。上の画像で線が描かれていない左の部分でチェックしてみていただきたい。
ふりがなを読まないというタイプの人は、上の青い線のように、ふりがなを無視して漢字そのものを読むのだろうが、私の場合はふりがなを無視することができず(^^;)視線がふりがなの方に移動してしまうようである。
もしかしたら、この現象は、私が子供の頃に読書少年だったせいかもしれない。小学校中学年から中学校の中頃にかけては、週に2冊程度の本を読んでいた。年齢のわりには少し難しい本も読んでいたように思うが、小中学校の図書館にある本にはふりがながついているものが多かった。学校で習っていない漢字が使われている本も多く読んだので、それについているふりがなを読んでしまう癖がついたのかもしれない。
(また余談になるが)読書をたくさんすれば漢字を覚えるという説もあるが、私はそうでもないように思う。
難しい漢字が出てきたときに最初の方だけふりがなをつけて、その後は省略するというやり方をしている本もあるが、その手の本は正直なところ読みにくい。ふりがなが省略された部分で読み方がわからなくなり、前のページに戻って読み方を確かめるということをやっていると、興ざめになって物語を読む楽しさが失われてしまうからである。(そういう点では、似たような登場人物の名前が出てくる外国文学なども同様で、この人はだれだっけなどと前のページをめくらなければいけなくなると、とたんに面白くなくなってしまう)
気持ちよく読ませるためには、最後までふりがなをつけるほうがいいのだが、そうなると(私のような読み方をするタイプにとっては)漢字についての学習効果は低い。
大人になった私にとっては、漢字の学習効果などはどうでもいいのだが(^^;)、困るのは「ふりがなは老眼には辛い」ということである。
子供向けの本は活字の大きさが若干大きくなっていることもあるが、(小学校高学年向きなどの)一般的な本での活字の大きさは5号(10.5ポイント)である。これのふりがなは7号(5.5ポイント)の活字が使われる。
10.5ポイント活字の文章を読むのは、老眼の私にもそんなに辛くはないのだが、5.5ポイント活字で印刷された文章を読むのは(老眼でなくても)辛い。
私のように、ついふりがなを読んでしまうというタイプの人だと、ふりがなつきの本を読むということは、実質的には5.5ポイントの小さな文字の本を読んでいることになる。
子供向けの本を読むのは、頭にとっては辛くないのだが、その本にふりがながついていて、しかも私のようにふりがなを読んでしまうタイプの人間には目にとって辛い。(ふりがなを読むのを常としている子供にとっても、小さい文字のふりがなは目にとってよくないだろう)
私のような「子供向けの本を読むのが好きな大人」の(目の)ために、ふりがなをつけていない「大人向けの子供向けの本」というのがあるとありがたいのだが‥‥(^^;)
さて、ここからは例によって余談のうんちくである。
この文章のタイトルで「ルビを読んでしまう」と書いたが、「ルビ」とはもちろん「ふりがな」のことである。
この「ルビ」という言葉、日本語のような気がするかもしれないが、語源は英語の「ruby」である。赤い宝石のルビーのことである。
イギリスやアメリカの印刷業界では、活字の大きさを特別な固有名詞で呼んだのだそうだ。
例えば、4.5ポイントだと「Daiamond」(ダイヤモンド)、5.0ポイントが「Pearl」(真珠)、5.5ポイントがこの「Ruby」(ルビー)になるのだが、イギリスでは「Ruby」と呼ぶけれど、アメリカでは「Agate」(めのう)と呼ぶそうだ。
ここまでの例だと宝石系の名前のようだが、6.5ポイントが「Nonpareil」(並ぶものがない極上品)、9.0ポイントが「Bourgeois」(中産階級、ブルジョア)という具合に、特に法則性はないようだ。(各サイズの詳しい呼び方は、こちらのサイトを参照)
こういう呼び方をしたのは、印刷工場等で、活字の大きさを指示する場合、聞き間違えがないようにするためと、「5.5ポイント」を「ファイブ・ポイント・ファイブ・ポイント」という具合に呼ぶのがわかりづらいというためなのではないかと思う。
そこで、ふりがなに使う7号活字が、5.5ポイントのサイズとほぼ同じなために、5.5ポイント活字の呼び方である「Ruby」という名称が使われ、それが「ルビ」になったとういうことである。
ちなみに、日本で一般的な文書に使われる5号活字は、10.5ポイントということだが、これにあたる呼称はないようだ。(10ポイントが「long primer」、11ポイントが「small pica」、12ポイントが「pica」というそうだ。「pica」は「ピカ」ではなく「パイカ」と読む)
パソコンの操作法などが話題になり「こういう操作をすると漢字にルビがつけられるよ」なんて話になったとき、ルビの語源についてうんちくをたれると尊敬のまなざしで見られるかもしれない。(あるいは、またいつものしったかぶりかぁ‥‥などと冷ややかに見られるかもしれないが)
<02.07.21>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ