文書も見た目が大事
私の職業(学校の教師)でも、子供や保護者向けの通信以外に改まった文書を書くことがある。
特に4月・5月頃には、学校要覧とか教育計画とかいった冊子に載せる「○○実践案」「○○経営案」などの文書を書かなくてはならない。
それらの文書の形式は、下のようなものが多いようだ。
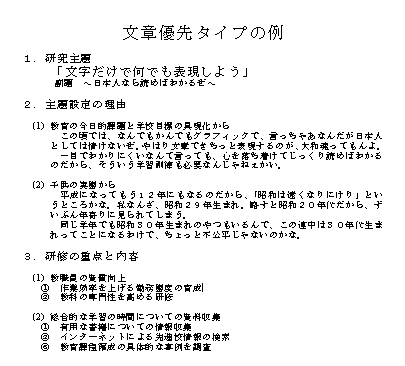
「学校要覧」「教育計画」などの冊子は、1年間の学校運営の基本になるもので、全ての職員の必携冊子であり、地区の教育委員会など公的な機関にも提出するものだから、きちんとした外見に仕上げることが多い。
昔は、学校で印刷する文書類は「ガリ版」で作るのが普通であったが、ガリ版では見た目も冴えないので(中にはガリ版でタイプ印刷に負けないような美しい文書を作る職人芸を持っていた教師もいたが)、ほとんどの場合、改まった印刷物を作るときには、印刷屋さんが用意した原稿用紙に手書きし、それを印刷屋さんがタイプ印刷してくれるという形式をとっていた。
したがって、文字は、印刷屋さんが持っているタイプの書体(明朝体・ゴチック体などの2・3種類の書体)で、文字のサイズも3〜4種類という、限られた表現形式で文書を作るしかなかった。
そうやって作られたのが、上のような文書である。
文字の書体や大きさの種類が少ないから、大見出し・小見出しなどで活字の大きさに若干の差をつけ、あとは文字位置の差(字下げ)によって大項目・中項目・小項目などを区別するので、自然と上の例のような形式になる。
文書としては、それなりに洗練されたかたちであり、見た目もすっきりとはしているが、一目見ただけで内容を把握できるかというと、そうでもない。
内容をきちんと把握するためには、じっくりと文章を読み、自分の頭で考えて理解するという作業が必要である。「見ただけで全てがわかる」という種類の文書とは言い難い。
印刷物を業者に任せてタイプ打ちする時代には、これでも良かったのだろうが(特殊なレイアウトを頼んだりすれば費用もかかるし、それに対応できる印刷屋さんも少なかった)、今では、この程度の文書なら誰でもワープロで簡単に作ることができる時代である。
実際に、この手の文書なら自分のワープロで作ってしまうということのほうが多くなっている。
ところが、多彩な表現能力を持つワープロを使っても、上の例のような、「タイプ打ち時代の書式」で文書を作っている例が多いようだ。
上の例は、書体の数や活字の大きさに制限があった頃の書式であり、今のように書体も文字の大きさも自由自在に扱えるようになっても、まだ上のような「一目で内容を理解しにくい」形式を、大事に使っている必要はないのではないかと、私は考える。
ということで、自分のワープロの様々な機能を使って、書体や文字の大きさを多様にした文書を作ろうとしている人もかなり見かける。
例えば、次のような文書にすることもできる。
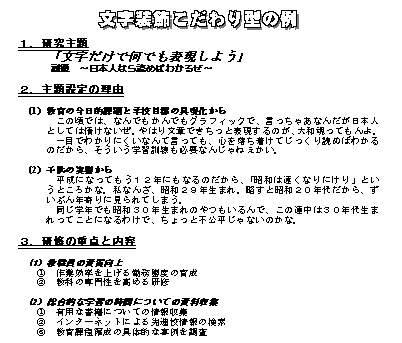
最初の文書と同じ内容なのだが、文字の書体を数種類使ったり、太字にしたり、斜体字にしたり、アンダーラインを使ったり、などと、様々な表現方法を用い、工夫している。
この結果、文章全体の構造は把握しやすくなっているし、大事な部分(見出しなど)だけを拾い読みしようとするときなど、読みやすいかたちにはなっている。
しかし、この形式、私に言わせてもらえば「超ダサイ!」(^^;)
ワープロの印字見本でもあるまいし、やたらにフォントや文字飾りを多用する必要はない。こういう文書を作って「視覚に訴える文書を作った」と思っているのであればセンスが悪い。むしろ最初の例のほうがあか抜けていると思う。
なぜ、このような文書にセンスがないと考えるかというと、文書作成の発想が、タイプライター方式から脱却していないからだ。
ご存知のことと思うが、タイプライターというのは、1行ずつ文字を印字していく。したがって、書体に若干の変化をつけようとも、基本的には横書きの文字を1行印字して、改行した後、次の文字を印字していくという仕組みだ。
このような印字方式のため、罫線を入れたり、ページの構成を段組にしたりするには、かなりやっかいな手間がかかる。
ところが、ワープロの場合には、罫線を入れるのも段組にするのも難しくはない。
タイプライター方式のように「1行単位での文字入力」ではなく、用紙全面を対象にして、好きな位置に好きな文字を置くことが可能なのだ。
だとすれば、タイプライター時代に確立された書式にこだわる必要はない。
少々、話は横道にそれるが、日本人は「第○巻 第○章 第○節」というような体系だった整理法が苦手なのだそうだ。
聖書は、ほぼそのようなかたちで整理されている。
ところが、お経にはそういうかたちのものが少ないのだそうだ。
お経は、どちらかというと文学的なのではないかと思う。
全体として整理されたかたちではないが、言葉の流れを時間の経過に沿ってたどっていくと、最終的に大きな感動が残る。これはまさに文学である。
ところが、聖書などは法規の文書に近い。法典という言葉もあるとおり、「○○に関するものをまとめた文書の、○○について書かれた項の、○つ目の内容」というように、それぞれの事項が大きな体系の中に位置づけられており、必要とする事項を探し出すのも容易である。
最初に述べた「○○実践案」「○○経営案」などは、どちらの形式が適しているかということは、あえて考えるまでもない。きちんとした体系づけがなくては、計画の実践はできないのである。
上であげた2つの文書は、タイプライター型の表現方法の中では、できるだけ全体の構造を明確にしようとしたものではあるが、それでもまだお経的要素を含んでいるように思える。
つまり、まだ、じっくり文章を読み、考えなければならないような表現を用いているということである。
上の2つの例の場合、大見出し・小見出し等はついているが、そのあとの部分は、文章で表現されている。この部分を理解するためには、落ち着いて文章を読んでいかなければならない。
「○○実践案」「○○経営案」などは、書いた本人もそれを有効に使い、他の人が見ても正しく把握できるように、「読む」のではなく、「見る」だけで内容が明確になることが大切である。そういう面では、上の例は中途半端である。
また、仮に「じっくり読んで理解し、実践に移す」というものだとしても、その読むべき文が、「読んで内容を把握できる」ものならよいのだが、「読めば読むほどなかみがわからなくなる」といったものもよく見かける。
要は「文章がヘタ」ということなのだが、その原因の多くは、書いている本人が、自分の実践目標をきちんと整理できないまま書いているので、必要以上に多くのことを1文に盛り込もうとしたり、事項どうしの関連が整理されていないために、わけのわからない接続詞を多様することにあるようだ。
そういうことを避けるには、できるだけ、文で表現するということを少なくするとよい。また、事項相互の関係を明確にするためには、接続詞で事項をつなくのではなく、図表化して表現するのが望ましい。
これだと、書く本人も、書くことによって自分の考えを明確にしていくことができるし、他の人が見てもわかりやすい。
これによってのみ、「読んでわかる」ではなく、「見てわかる」文書が可能になる。
では、どんな形式のものがよいのか‥‥ということで、作ってみたのが、下の例である。
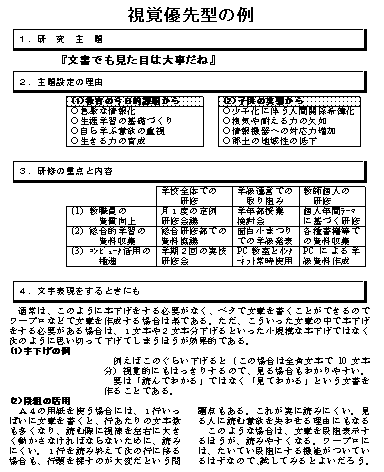
この例では、書体や文字の大きさにそれほど多くの種類を使ってはいない。場合によっては文字の種類を1つだけにしても大丈夫である。
そのかわりに、罫線を多用している。
見てわかるとおり、大見出しの部分を罫線で囲んでいる。立体的に見えるのは、特別に難しいテクニックを使っているわけではなく、細い線で箱形を引いたあとに、右側と下側の線を太い線にして引き直しただけである。
この「大見出しを罫線で囲む」という方法は効果的であるが、この方法を使っても、囲む箱形の大きさを、中の文字の長さに合わせている例も見かける。(中の文字数が多ければ長い箱になり、文字が少なければ短い箱になるというように) これでは、見た目の統一性がないし、インパクトも少ないので、上の例のように、ページいっぱいに箱を広げたほうが効果があるようだ。
この形式であれば、上の例の「4.」のように、普通の文章を書く場合にも、いちいち字下げをせずに、用紙の左端からベタ書きをすることができる。
ただ、A4の用紙を使う場合、ページの幅いっぱいに1行を使うと、視線の左右移動が大きくなって読みにくいので、上の例のように、思い切った字下げを行ったり、段組を使ったりすると、読みやすい文書になるようである。
また、これまで何度も述べたように、だらだらと文を長く書くと、見ただけではわかりにくい文書になるので、できれば上の例のように、表形式を多用したほうが、すっきりとしてわかりやすい文書になる。
最初にあげた例でも、とりあえず箇条書きの形式はとっているのだが、これだと、思いついたことを順序性なしにだらだら並べることにもなりがちなので、上の例のように、縦横の系列性を明確にした表形式を使ったほうが、書く側も見る側も頭の中がすっきりする表現になる。
このことについては、「うんちく講座」No.215「行列ですっきり」に詳述しているので、ご参照いただきたい。
いろいろと書いてきたが、要は「文書もパフォーマンスである」ということである。
「恥ずかしがり屋で口べただけど、心の暖かい、良い先生」という人もいるはずだが、教師という職業は、基本的には、巧みにしゃべったり、豊かな表情を使ったりしながら、子供に多くのことを伝える職業である。
自分が考えていることを、効果的に伝える技術は、プロとして持っていなくてはならない。
それは、話すことだけでなくて、文書で表現する場合にも同じである。(実際、学習事項を黒板にまとめる技術は、教師に必要な能力である)
自分の学級経営の方針を示す文書を、すっきりと効果的にまとめられなくては、きちんとした学級経営はできない。
そのためには、これまで述べたような方法を使って、見た目も(中身も)かっこいい「○○実践案」「○○経営案」をまとめてみるものよいのではないだろうか。
実は、もう1つ考えていることがある。
これまで述べたような形式の文書を印刷して冊子にできるのは、学校に備えられた印刷機が進歩したためである。
教師が自分のワープロで、自由自在に文書を作るといっても、それを冊子にするためには、ワープロで何十枚も印刷するわけではない。
教師は、ワープロで原版となるものを1枚印刷し、それを学校の印刷機で何枚も印刷するのである。つまり、学校にある印刷機は、原版さえあれば、それから同じ物を何枚も複製印刷できるのだ。
だから、市販の書籍から切り抜いた図表なども原版として使えるわけである。
したがって、原版は鉛筆で手書きしたものでも、いっこうに差し支えない。
だとしたら、「学校要覧」「教育計画」なども、手書きの原版で作ってもいいのではないだろうか。
上の例であげたような文書(罫線などを多用した)を、ワープロ等で作るとしたら、けっこうテクニックが必要である。ワープロを使い始めて数か月という人には難しい部分もあるかもしれない。
しかし、手書きなら、直線だけでなくどんな曲線も引くことができる。線の太さも自由自在だ。レイアウトだって思い通りにできる。
「字がじょうずでないので‥‥」などと遠慮することはない。自分の考えた通りの、自分だけの文書を作ろうとするならば、手書きのほうが自由度が高い。
タイプの文字が整然と並んだ文書をよしとしたのは昔の話である。
自由自在で思い通りの「○○実践案」「○○経営案」がたくさん収録された「学校要覧」「教育計画」を持つ学校のほうが素敵なのではないだろうか。
ワープロができないから‥‥などと臆することなく、自分の手・自分の字で、豊かな発想を表現することのほうが大事なようにも思う今日この頃である(^^;)
<00.04.11>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ