季語は?
地域の文化祭などで小学生の俳句の募集があることがある。国語科でちゃんと俳句の勉強をするのは6年生からなのだが、4年生以上の作品提出を求められたりすることがあるので、そんなときには担任の先生に「まあ五・七・五になっていれば、川柳や標語みたいなものでもいいから」と話して、とりあえず必要な数の作品を揃えて出品してもらうことが多い。
親切な主催団体になると、応募した作品を印刷してくれて、ひとつひとつの句に評をつけて返してくれることもある。
その評を見ると、「季語がありません」とか「2つの季語が混在しています」などというものもある。
「まだきちんと俳句を勉強していない子供の作品だから、季語ぐらいどうでもいいじゃないか」とも思っていたのだが、この頃になって考えが変わってきた。
そう思ったのは秋になってからであった。
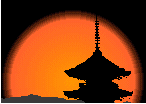
私がホームページのコンテンツを書くのは主に夜である。10月も中旬になると夜にはだいぶ寒くなる。ストーブを出すにはまだ少し早いのでジャンバーなどを重ねて着て寒さをしのぐのだが、足下からは寒さが忍び寄ってくる。
まして風呂上がりだったりすると湯冷めして風邪をひきそうで、ついインターネットに接続するのもおっくうになってしまう。
これが夏だったりすると、湯上がりのさっぱりしたところで、深夜までパソコンに向かうのも快適である。夏の夜は更けるにつれて涼しくなるので、夜遅くのほうが調子もよくなるのだ。
そのためか、秋に書いたコンテンツは、なんだかくどい内容のものが多いような気もする。調子に乗って一気に書き上げるというものが少なく、毎日、なんとなく気が乗らない中で、あーでもないこーでもないといじくりまわしたような物が多いのだ。
そういう目で見てみると、秋に限らず、それぞれの季節によって、私の書く文章の色が、少しずつだが、季節の影響を受けているようにも思える。
日本は四季のはっきりした国である。「春はあけぼの‥‥」の枕草子を例にあげるまでもなく、四季それぞれに、感じられる風情が大きく異なる。
その中で育った私たちは、難しい説明なしでも、共通に持ってる季節感があるように思う。
例えば「鯉幟(こいのぼり)」という語を聞いたときに、人により若干の違いはあるにせよ、ある程度共通に抱く感覚があるはずだ。初夏の青い空、爽やかな風、暖かさに身体もほぐれてくるような開放感までも感じられるだろう。
これをうまく使ったのが季語という技法なのだろうと思う。
季節を感じさせるある言葉を使うことで、読む人に、自分の持っているその季節の様々な感覚を想起させる。その感覚や色調をベースにした上で、さらに別の言葉で作者の感覚世界を展開していくという技法なのだ。(ベースの色調については、うんちくNo.97「おぼろ月夜ってすごい!」等にもつながるように思う)
俳句の17音という限られた長さの中に、豊かな感覚の世界を展開するには、日本人にとっては「お約束」の感覚ともいえる季節感を利用する「季語」が不可欠なのは、こういう理由なのだろう。
たしかに、俳句で表現したい内容が、全く季節に関係のない場合もあるだろう。無季の俳句も作られてはいる。しかし、無季の俳句では、そこに表現されるのは、17文字(音)が表現するものだけである。それに対して、季語を使った場合には、17文字で書かれたこと以外に、読者が既に持っている多様な季節の感覚をも利用することになるのだから(例えば背景のある舞台の劇と背景の無い舞台の劇との違いのようなものである。ときには背景がないほうが効果的なこともあるだろうが)読者が抱く感覚の世界の豊かさには大きな差が出てくるように思う。
俳句の倍近い文字数を使える短歌に季語がないのは、無理に季語という技法を使わなくても、32文字もあればある程度自由な表現が可能だからだろう。削ぎ落とされた、極端に短い表現をしなければならない俳句とは違っていると思う。
余談のようになるが、私が考えるには、全く季節と関係のない感覚の俳句というものもないように思う。たとえ季節の事象に触れていない内容でも、人間の感覚というのは、大なり小なり季節に影響されていると思うからだ。
ちょっと長くなってしまったが、このように「季語なんてどうでもいいじゃないか」という私の考えは変わってきた。
ただ、ちょっとなじめないのが、俳句を長く勉強している人たちの言う「これは夏の季語ではありません」とか「季語重なりがあってどうのこうの」という言葉である。
季語の基準となっているのが「季語集」である。「歳時記」とも呼ばれる。
ちょっとした国語辞典の巻末などについていることも多いので目にした方もいるだろう。
これを見てみると、けっこう面白い。「なるほど」と感心する季語もあれば、「へえー、こんなのも?」と思うようなものもある。暇つぶしに見るには最適である。
ただ、この季語集をもって、季語がどうのこうのというのは、なんだか了見が狭いようにも思える。
例えば「更衣(ころもがえ)」、これは夏(5月)の季語として扱われている。しかし実際には「ころもがえ」は年に2度あり、秋(10月)に行うのも「ころもがえ」である。10月1日になって、制服などが一斉に冬服になり、タンスから出して着た樟脳の匂いなどは、誰でも共感できる秋の風物詩のように思える。
この「ころもがえ」を使って秋の感じを表現しようとした俳句を「ころもがえは夏の季語ですからだめです」というのでは、頭が固すぎると思う。
「ころもがえ」という言葉以外に秋の雰囲気が感じられる表現があったとしたら、「ころもがえ」は立派に秋の季語になると考えたほうが自然だろう。
反対に「西行忌」「虚子忌」のような、よくわからない季語も多い。(どちらも春の季語)俳句を学んでいる人には常識なのかもしれないが、一般の人には補足の説明がないと季節がわからないような語を使って「季語があるから立派な俳句です」というようでは、俳句そのものが日常生活から遊離してしまうだろう。
話は俳句から離れるのだが、これまで述べたように、日本人と四季の感覚というのは深く結びついている。
俳句でなくても、手紙の冒頭などに「新緑の候」のような時候の挨拶をつけるのは、日本人らしい美しい感覚であると思う。
だから、ちょっとしたエッセイなどにも、季節を感じさせる表現があってもよいのではないだろうか。
論文の発表会などの際、次のように質問してみるのも面白いかもしれない。
「大変、けっこうな論文でした。ところで季語は何でしたか?」(^^;)
以上で本文は終わりなのだが、ここからは余談‥‥
先日、知り合いの方からカレンダーをいただいた。
とてもセンスのよいデザインで、タイトルの文字などは全て英字である。「もしかして海外からの輸入物かな?」と考えて、思わず笑ってしまった。
ポスターならば海外製の輸入物ということもあるだろうが、カレンダーでは輸入物ということはあり得なかったのだ(^^;)
あらためて日付のところを見て確信した。2月11日(金)は赤い数字になっていて、ちゃんと日本語で「建国記念の日」と印刷されてあった‥‥‥
<99.12.12>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ