電動黒板ふき掃除機の掃除
今回は教職員ネタである(^^;)
良い授業を行うためには「黒板とチョークだけの授業」ではダメであると言われているが、やはり学習指導の際にいちばん多く使われるのが「黒板とチョーク」である。
チョークで黒板に書いた文字や図を消すのが「黒板ふき」であるが、消しているうちにチョークの粉がたくさんついて、きれいに消せなくなる。
そんなとき、昔であれば、窓の外に身を乗り出して、黒板ふきを棒で叩いて掃除をしたものだが、この頃は下の写真のような「電動黒板ふき掃除機」を使うことが多い。
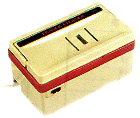
この道具、けっこう高価だ。現在だと市価15,000円程度である。
ただ、構造的にはかなり単純で、一般の家庭用掃除機と似たような構造である。上の写真の3本の切り込みのような部分が、掃除機の吸い込み口になっていて、そこから黒板ふきについたチョークの粉を吸い取るようになっている。
ところで、この文章をご覧の教職員の方で、この「電動黒板ふき掃除機」の掃除をしたことがある方は、どのくらいいるだろうか?
「私は何度もやったことがある」という方は、この問題に限っては、優れた教師である。
反対に「一度もやったことがない」という方は(この問題に限っては)、教師としての態度を反省してみたほうがよい(^^;)
この種の掃除機は、ほとんどの学校にあるだろうから、一度も掃除をしたことがないという方は、ぜひ中身を開けてご覧いただきたい。
構造は実に簡単で、吸い込み口の下には、布製の集塵袋がある。その集塵袋の中には、さらにスポンジ状のフィルターが入っている。
吸い込まれたチョークの粉は、この集塵袋の中にたまる。スポンジ状のフィルターの中にも入っていくので、使い始めて数日たつと、粉がたまっていくので、吸い込みが悪くなってくる。
本来の使い方としては、使用後、数日たったら、集塵袋にたまったチョークの粉を捨てることになっている。それでもスポンジ状のフィルターの目詰まりが起きるので、時々はスポンジを取り出して水洗いし、乾燥させることが必要である(これは、取扱説明書に明記されている)
ところが、恐ろしいことに、この「電動黒板ふき掃除機」を、購入してからずっとそのまま使い続けている例がある。(かなり多いように思える)
これでは吸い込まれたチョークの粉が大量にたまり、それがコンクリートのように固まってしまい、吸い込みを極端に悪くして、全く用をなさなくなる。(モーターの音だけはものすごく大きくなるのだが‥‥)
この「電動黒板ふき掃除機」にたまった粉を掃除してくれる担当者は誰になっているのだろうか?
気の利いた校務員さん(私のいる秋田県では「校務員さん」と呼んでいるが、「用務員さん」という県もあるだろう)がいれば、定期的に掃除をしてくれているかもしれない。
しかし、校務員さんには、印刷や外勤、湯茶の準備、校内外の清掃など、たくさんの仕事がある。「電動黒板ふき掃除機」は学級担任や児童生徒が使うのがほとんどなのだから、ふだん使っている人が「自分のことは自分で」やるのが当然である。
それぞれの教室に、この「電動黒板ふき掃除機」が備え付けられていることは少ないだろうが(価格が高いので)、2教室あるいは4教室に1つぐらいの割合で、廊下に備え付けられていることが多いのではないだろうか。
そうならば、自分の教室の前に「電動黒板ふき掃除機」がある教師が、掃除をするのがよい。
できれば毎日、チョークの粉の撤去をする。スポンジフィルターの水洗いは毎日というわけにはいかないので、乾燥する余裕のある第2・第4土曜日の前の日(金曜日)にやるとよい。
「うんちく講座」のNo.83「OHPは30年もつ」にも書いたが、概して教職員は学校で使う機器のメンテナンスを自分で行うことが少ないように思う。(ちゃんと自分でやっている方はごめんなさい)
「電動黒板ふき掃除機」の吸い込みが悪くなったので、新しいものを購入してほしいなどと言うことは、自分でその機器のメンテナンスをやっていないのであれば、口が曲がっても言ってほしくない。(モーターの耐用年数が切れたなどという場合は別であるが、正しくメンテナンスをして使うなら数十年はもつ構造である)
「電動黒板ふき掃除機」や「OHP」に限らず、学校で一般的に使っている「構造が簡単な機器」について、その内部の構造を知らずに、具合が悪くなったらすぐ誰かに修理を頼むような人は(この問題に限っては)、教師としての適性を欠くし、子供たちに「生きる力」を指導するにはふさわしくない。
男女雇用機会均等法などで、男女の差別をすることが否定されているが、こういうことに関しては、男であろうと女であろうと、ドライバー片手にいろいろとやってみることが、教師には必要であると、私は思う。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ