何もなくてもがんばる?
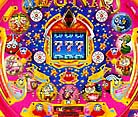
私は球戯の中ではパチンコがかなり好きである。パチンコ屋さんに寄る回数も多い。
(週に数回)
パチンコ屋さんの隣にはボウリング場がある。これも「球技」というよりは「球戯」なのだろうが、ここに行く回数は極めて少ない。たまに家族で行ったり、職場のレクリエーションで行ったりはするが、こちらは年に数回である。
パチンコもボウリングも楽しいのだが、行く回数に大きな差があるのは、パチンコはうまくすると儲かるからである。ボウリングはどんなにハイスコアを出しても、結局ゲーム料を払ってくるだけだが、パチンコなら遊んだほかにおみやげも持って帰れる。(もちろん、そうでないことのほうが多いのだが)
話は変わって、車の運転。
新車に乗り換えたこともあって、すいている道路などでは、ついスピードを出したくなる。アクセルを踏み込んで加速を楽しむこともあるが、それでも制限速度を大きくオーバーするような運転はしないようにしている。
車そのものは時速100kmを超えても大丈夫なのだが、そんなときに突然、警察の人が出てきて、スピード違反で捕まえられたら大変だからだ。
こういうのを「外発的動機づけ」というらしい。
「自分に得があるからやる」「自分に損があるからやらない」というように、行動をやる・やらないの決定が、自分の純粋な意志ではなく、賞罰などによって動機づけられるというものだ。
反対に「内発的動機づけ」というものもある。
最近では教育界の主な話題が「生きる力」になって、ちょっと色あせた感もあるが、現在の学習指導要領が発表されたときに、その中心となる考え方であった「新しい学力観」の基盤となる「自己教育力」(自己学習力ともいう)を語る場合、欠かすことのできないキーワードが、この「内発的動機づけ」であった。
詳しいことを書くと長くなるので、「内発的動機づけ」については、ここをクリックして、お読みいただきたい。
要は、「何か得になるからやる」「怒られるからやらない」「強制されたからやる」というのではなく、「やりたいからやる」という気持ちが大事だということである。
これを育てないと「自ら学ぶ力」は育たないというのだ。
確かにもっともなハナシだ。こういう気持ちを持った子供を育てるのが、私たち教師の理想である。
しかし、理想を実現することは難しい。自分のことを考えてみたとき、ほとんどの行動は「外発的動機づけ」によるものだからである。
前述のパチンコやスピード違反の例は卑近なものだが、学校での自分の仕事を考えても、ほとんどが「外発的動機づけ」によるものである。
○ 提出期限が迫っているから報告文書を仕上げる。
○ 年度のまとめに研究紀要を出すから実践資料をまとめる。
○ PTA参観日があるので教室をきれいにする。
○ 通信簿を書かなければいけないのでテストをする(^^;) 等々
まあ、極論すれば、家族を養わなければならないので仕事をするなんていうこともできるだろう。
見方を変えれば、外部からの強制があるから、それなりの行動をすることができるということになるのかもしれない。上の例にあげた「研究紀要を出すから実践資料をまとめる」にしてみても、もし研究紀要を作るということがなければ、「自分の授業実践を振り返り、成果と課題を分析し、論文形式にまとめる」という作業をやる教師は、ほとんどいなくなるかもしれない。
自分自身がこういう状態なのに、そうでない子供を育てるというのは、かなり難しい。しかし、本を読むと、内発的動機の育て方が書かれている。
それは、「本人の中に、有能感・有効感を育てること」なのだそうだ。「有能感・有効感」というのは、ちょっと理解しにくいが、「有」を「無」に変えて読んでみて、その反対の概念だというとわかりやすいだろう。
反対の概念は「無能感・無効感」である。これはよくある感覚ではないだろうか。教室で学習をしていく中で、子供が「ボクは無能だなぁ」とか「ボクのやっていることは何の役にも立っていないなぁ」と感じる、あの感覚である。多くの方は子供時代にこんな感覚を持ったものだろうと思う。
これまでの学校教育では、こんな感覚を持たせる場面が多かったと思う。せっかく手を上げて発表しても、「うーん、ちょっと違いますね。誰か他の答がある人はいませんか」などと言われると、しみじみと無能感・無効感を感じたものだ(^^;)
では、有能感・有効感を育てるにはどうしたらよいかというと、「認め」が効果的なのだそうだ。これには3つのステップがある。
1番目は「教師による認め」である。
前述の「うーん、○○君の答はちょっと違いますね」を例にするとこんなふうになる。「○○君の答はちょっと違うけど、すごく惜しかったですよ。先生はそれよりもちゃんと手を上げて答を言った○○君はすごいと思いますよ。○○君はいつも手を上げて発表してくれますよね。なかなかできないことです。こういう勇気って、大人になったときに、とても大きな力になるんですよ」
ただし、これだと本当に認めてほめたとは言い難い。こういった「正解・不正解」や「優・劣」がつくような場面ではなく、本当にその子だけの優れた点を見つけだして認めてやることができるとベストである。
2番目は「友人による認め」である。
「教師による認め」がうまく行われるようになると、それが引き金になって、級友もその子の良さを認めるようになる。「△△についてなら、やっぱり○○君が頼りになるよ」というような発言が出るようになったら、目標達成である。
3番目は「本人による認め」である。
教師に認められ、級友に認められてくると、次第に本人も「ボクって△△についてはすごいのかもしれないな」と思うようになる。(実は自分で自分の力を認めるということが1番難しいのである)
「ボクは、あまりたいしたことはできないけど、△△だったら、ちょっとは人に負けない自信がある」と考えることができるようになったら、有能感・有効感は完成である。
「ここを頑張って勉強しておかないとテストで良い成績はとれませんよ」などと外発的動機づけをしなくても、自信と興味があるものについては自分から進んで取り組むようになる。
「やりたいからやる」「やるのが楽しいからやる」という内発的動機づけがなされるからである。
私自身のことを考えると、生活行動のほとんどが外発的動機づけによるものなのだが、ホームページでうんちくをたれることや、音楽作りをすることは、内発的動機からやっているような気がする。
どうしても書かなければならない仕事上の文書などは、「書かなくてもいいよ」と言われれば、すぐにでも書くのをやめてしまうのだが、「うんちく講座」などは「やめろ」と言われても書いてしまう。眠いのもがまんして書いている状態だ(^^;)
これも、他の人からの認めがあるからだろう。「ホームページ読みました。おもしろいですね」とか、「とても参考になりました。これからもたくさん書いてください」などという励ましをもらったからこそ、自信を持てたのであって、ホームページを公開しても誰も読んでくれず、反応もなければ、とっくの昔にやめてしまったように思う。
「一人一人の子供の良さを伸ばす」とは、こういったことのように思う。計算能力の高さとか、走る速さなどという、優劣をつけることができるようなものでは、一部の子供に優越感を与えることができても、多くの子供には無能感を植えつける結果になってしまう。
どの子にも有能感・有効感を持たせ、内発的動機を育てるには、他の子供と較べるのではなく、まずその子1人を見つめ、その中の良さを認めてやることが大切だと思う。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ