子供の時間も開かないと
(長文です)
「開かれた学校」というのが、これからの学校教育を考える場合のキーワードのひとつであることは、ご存じの方も多いと思う。そのことについては多くの文献も出ているので、ここではあえてそのことについて詳しくは触れないが、私には今一つすっきりしないものがある。
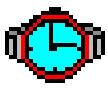 例えば、地域の事物や自然を生かした学習活動をすることや、地域の人材を指導者として活用すること、これは確かに良いことである。現在でも小学校低学年の生活科や、中高学年の社会科・理科などでかなり取り組まれていることである。
例えば、地域の事物や自然を生かした学習活動をすることや、地域の人材を指導者として活用すること、これは確かに良いことである。現在でも小学校低学年の生活科や、中高学年の社会科・理科などでかなり取り組まれていることである。
しかし、これらは全て、学校の外のものを学校教育活動の中に取り入れようとする活動である。
学校の授業という時間の枠の中で、子供たちは地域・自然を学び、地域の人材と触れ合う。
これはなんか変だと私は思う。
今の子供たちは、地域社会での体験が極端に少ない。だから学校教育でその点に力を入れた活動をしていくということになるのだろうが(確かに教科書を教室の中で読むだけの活動よりはずっといいのだが)、本末転倒の感がぬぐえない。
子供の学力を定着させるためには復習が大切であることは昔から言われていることである。調査によれば、学校で学習したことをその日のうちに(家庭学習で)復習した子供と、そうでない子供とでは、忘却曲線のカーブが全く違うということも実証されているそうだ。
では、「開かれた学校」などといって、地域を生かした学習活動をしたときに、それを家に帰ってから復習する子供はいるのだろうか?復習する場と時間はあるのだろうか?
もう少し具体的に述べよう。
小学校の生活科では、砂場などで川や池、トンネルなどを作って遊ぶという学習活動をする。いわゆる「泥んこ遊び」である。これは実に楽しいし、子供たちに様々な力がつく。ところが、これが楽しかったからといって、家に帰っても友達と泥んこ遊びをしてみようという子供がどれだけいるだろうか?
あるいは、社会科の学習で農家の人の野菜作りの工夫や苦労を知るために、担任の先生に引率されて農家の畑に行き、そこで農家の人に話を聞く。でも、学校から帰ってから、もう一度、畑の様子を見に行く子供はどれだけいるのだろうか?
「開かれた学校」はけして悪いことではない。しかし、上に挙げた例のようなことは、本来は子供が学校から帰ってからの自由な時間の中で遊びながら(あるいは家の人の手伝いをしながら)、自分の目で見て、自分の体で体験して身につけていったはずのものである。
学校が終わった後の子供の活動はどうなっているだろうか。この「うんちく講座」のいくつかのコンテンツで私がしつこく述べているように、まさに「閉じられた時間」というしかない。
小学校も中学年になるとスポーツ少年団などというわけのわからない組織に組み入れられて、暗くなるまで拘束される生活。(百害あって五十利くらいしかない)低学年の子も学習塾などに通う毎日(学校の授業だけでは知識や技能が身につかないのだろうか)
これからの学校教育で重要視されている「体験活動」「問題解決活動」などというものは、本来は、子供の世界、子供の時間の中で行われていたものである。それが子供の時間・子供の世界を閉じてしまったために、学校で背負い込まなくてはいけないはめになってしまった。
学校教育の中に地域を生かした体験活動を取り入れるのはよい。しかし、これは本当の体験ではない。教育活動として必要な要素だけを抽出して行うという意味では効果的なのかもしれないが、あくまでもダミーの体験である。しかも、これは教師の監督のもとに同年齢の子供の集団だけで行われる温室の中の活動である。いわばバーチャルリアリティの世界である。
大人が管理する虚構の世界の中に子供たちは生きているような気がする。過保護で、同年代の子供たちだけに輪切りされ、幼児の気持ちのまま青年時代に運ばれるという現実。(このことについてはNo.42「心の教育もいいけれど」に詳述しているので参照いただきたい)
どんな時代背景があるにしろ、子供の世界で子供が自分で学ぶべきことを学校教育が請け負い、反対に、学校が指導すべきことを塾などに任せるというかたちはおかしい。
これからやらなければならないのは、スポーツ少年団も部活動も塾もない、子供の世界・子供の時間を開いてやることだと思う。
No.42「心の教育もいいけれど」で書いたことをもう一度ここに繰り返して書いて、この文章のまとめにする。
私たち大人が、今、子供に与えなければならないもの、それは「愛と自由」だけである。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ
例えば、地域の事物や自然を生かした学習活動をすることや、地域の人材を指導者として活用すること、これは確かに良いことである。現在でも小学校低学年の生活科や、中高学年の社会科・理科などでかなり取り組まれていることである。