九十九をツクモと呼ぶ訳
おかげさまで、「うんちく講座」のコンテンツも、この文章で99個めになった。
99を漢字で書いた「九十九」、これを「つくも」ということは、ご存じの方も多いと思うが、どうしてそう言うようになったのかについては、正直なところ知らなかった。
少し大きな国語辞典を見ても、「『百』という文字から『一』の線を取り去ると『白』という字になるから」ということと、「老人の白髪が植物の『ツクモ』に似ているから」という記述はあるのだが、それなら、どうして「ツクモ」が「九十九」なのかという関係は判然としなかった。
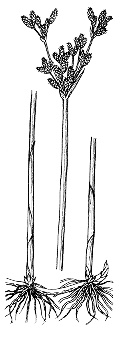 まず、左の絵が「ツクモ」である。それについての説明を引用しよう。
まず、左の絵が「ツクモ」である。それについての説明を引用しよう。
- ツクモ
- 植物「フトイ(太藺)」の古名。浅水中にはえるやや大形の多年草。カヤツリグサ科。根茎は太く地中に横たわり、茎は高さ80〜150cmで丸く太く、緑色が濃くて粉白をおび、基部に葉の退化した長い少数の鱗片がつくのみで、節はない。ときに生け花に用いられる。日本全土に生じ、ムシロや敷物を編む目的で栽培もされている。
どうやら、水辺でワサワサと絡み合って茂っている様子や、枯れてきて色が白っぽくなった様子が、老人の髪の毛の様子を連想させるということはわかってきた。
しかし、なぜ、それが九十九と結びつくのかということははっきりしない。
実は、ある短歌が、「九十九という数字」と、「植物名である『つくも』」を結びつけているカギであるらしい。
それは、「伊勢物語」の63段にある、次の歌である。
「百年(ももとせ)に一年(ひととせ)たらぬつくも髪 我を恋ふらし面影に見ゆ」
つまり、これは洒落になっているのである。「白い髪」を「つくも」の様子に例え、さらに「白」を「百」から「一」ひいた文字としている訳である。
こう書いただけでは分かりにくいので、表にしてみる。
老人の髪の様子
↓
|
白い
↓
|
ぼうぼうに乱れている
↓
|
白という字の形は
百という字の上の
棒(一)をとった
ようなかたちだ。
↓
|
水辺に生い茂っている
植物の「つくも」のよ
うに見える。
↓
|
100-1=99だ。
↓
|
九十九
↓
|
つくも
↓
|
「九十九」を「つくも」と呼ぶことにした
|
「白髪」を「つくも髪」と洒落たこの歌が、「九十九」=「つくも」という読み方のルーツになっていたということである。
なお、この件について調べている中で見つけたこちらのページも、私の調べたものと植物の「科」は違うが、ほとんど同じ内容であり、さらにもっといろいろな面白いことも書いてあったので、ご覧いただきたい。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ