ゴム印押しの裏技
年度始めに学級担任の教師が最初にやる仕事に、「氏名ゴム印押し」がある。出席簿・学級名簿・健康観察簿・教科書給付証明書などに、学級の子供たちの名前のゴム印を押す仕事である。
職員室でその作業をやっている先生たちのやり方を見ていると、いろいろな方法があるようだ。
いちばん能率が悪いのが、次のやり方である。
○ ゴム印箱から、ゴム印を1つだけ取り出す。
○ それをスタンプ台(インクがついているもの)に押しつける。
○ 帳簿にゴム印を押す。
○ ゴム印箱に戻す。
この方法だと、ゴム印を箱から取り出したり戻したりするたびに、いちいち場所を確認しなければならないし、手を動かす回数がとても多くなる。
ちょっと気の利いた人だと、5個とか10個とか、ある程度まとまった数のゴム印を取り出して、それを机上に重ね、上から順に取って作業するということをやっているが、もっと改良された方法がある。(すでにやっている人も多いだろうが)
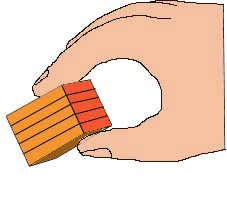
○ まず、右の絵のように、まとまった数のゴム印を箱から取り出す。
○ 次にそれをまとめて持ったまま、スタンプ台に押しつける。
(全部にインクがつく。こうやっても1〜2分はインクが乾かない)
○ 重ねたまま机上に置く。
○ 重なっているゴム印の上から順に取り、帳簿に押し、箱に戻す。
※
- ゴム印を押さなければならない帳簿が数種類ある場合は、1種類ずつ押すと手間がかかる。一度インクをつけたゴム印は3回程度なら、それほど見苦しいインクの薄さにはならないで押すことができる。(私の経験では大丈夫である)帳簿を2〜3種類準備しておいて、トン・トン・トンと一気に押してしまう方が合理的である。
ささいなことなのだが、これを実行すると、手際の悪い方法でやるよりは、作業の時間が半分位に短縮できるはずだ。
もっとすごい荒技もある(^^;)
ゴム印を押す場所があらかじめ決められている帳簿ではできないワザだが、単なる学級名簿(名前の一覧と枠線だけがあるもの)などのように、自分で枠線の大きさを決めることが出来る場合は、ゴム印を重ねて持ったときにぴたりと収まる大きさに枠線を引いておく。そして、重ねて持ったまま一気に押してしまうのである。もちろんこの方法だと、間が詰まった名簿になってしまうので、ゴム印を押してから拡大コピーする。名前も大きな文字になるので、けっこう便利な方法である。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ