過去の栄光を処分
入り口とか校長室の前とかに、大会やコンクールで受賞した賞状や盾などの陳列棚を設けいている学校も多いだろう。ガラス張りで中に賞状や盾・カップなどがずらりと並んでいるあれである。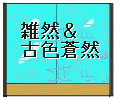
担当者がきちんと管理していればいいのだが、誰が担当なのか明確でなかったり、もらってきた賞状などをとりあえず押し込んでおいたりすると、この中は次第に雑然となる。
ガラス戸がどちらからも開けやすい構造になっていればいいが、この手の棚は見た目をよくするためにはめころしのところがあったり、たてつけが悪くなってガラス戸が開きにくくなっていたりして、中の物を整理するには具合が悪くなっていることもある。私が見た多くの例は、そうであった。
すると取り出しにくい奥の方には、いつ、何でもらったかも分からないようなものが押し込められたままになってくる。手前の方には最近のものが窮屈に並べられる。町内の大会で3位というような、あまりたいしたことのない(子供のがんばりを「たいしたことがない」と評価するのはよくないのだが、この場合は何十年も陳列する必要のないという意味である)ものも、「とりあえずここに置いておこう」と入れられたまま、だれも整理しないでいると次第に奥に押しやられ、そのままになってしまう。
こうして、栄光の陳列棚であるはずのものが、うっかりするとガラス張りの物置になってしまうのである。
これを整理しようと考える人もいるだろうが、かなりの手間がかかることと、古い物を処分するためらいがあるのとで、なかなか実行に移せない。体育主任が担当になっている学校も多いだろうが、若い体育主任だったりすると、学校の歴史を自分で管理するのはおそれおおいと躊躇してしまうだろう。(本当は校長がやるべきである)
私は、これを次のように改善(?)してみた。
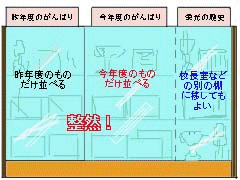 まず、陳列棚の役割を考えて見る。たしかに学校の過去の栄光の歴史を飾るものではあるが、それであれば、「全国大会での入賞」とか「文部大臣表彰」とか「全県優勝」などのよりすぐられたものだけでよい。
まず、陳列棚の役割を考えて見る。たしかに学校の過去の栄光の歴史を飾るものではあるが、それであれば、「全国大会での入賞」とか「文部大臣表彰」とか「全県優勝」などのよりすぐられたものだけでよい。
毎年もらえる「郡大会の入賞」などは、いつまでも陳列しておく必要はない。
本来は、現在、学校にいる子供のためのものであるはずだ。
そこで、左の図のような整理のしかたをすることにした。
まず、一度、中にあるものを全て出してしまう。(実際、ものすごい量が入っていることがあるし、なんでこんなものまでと思うようなものが保管されていたりする)
その中で、この後もずっと陳列すべきものをより分ける。おそらくはせいぜい10個程度しかないだろう。
次に、今年度と昨年度のものだけより分ける。(これは後でもう一度陳列する)
その他は、全て処分する。もしどこかに保管する場所の余裕があれば、そこにしまってもいいのだが、おそらく二度と日の目をみることはないだろうし、何年かあとに捨てられるのだから、ここで全部捨てるつもりでやったほうがよい。賞状などは捨てないで額縁から中身だけを取り出し、これを冊子のように綴じて保管する方法もあるだろう。(私の場合はめんどうなので全て処分した)
空になった額縁が大量にできるが、これは後で使うので、きれいに拭いて保管する。
まず、永年保存のものを置くコーナーを決めて、そこに並べる。これはあまり出し入れする必要がないので、取り出しにくい奥のほうでもよい。校長室や応接室のあたりに別の陳列場所があるなら、そこに移してもよい。
次に、先ほどより分けた今年度と昨年度のものを、空いた棚を二分して並べる。ここには、「郡市大会6位」などの、とるに足らない(語弊はあるが)ものも全て並べる。おそらくそういう賞状には額がないだろうから、先ほどの整理で大量に出てきた空の額縁に入れる。(これだけでけっこう立派に見えてくる)
最後に図のように、「昨年度のがんばり」「今年度のがんばり」などというタイトルを掲示して、この整理は終わりである。
あとは新年度になるたびに「昨年度のがんばり」に入っていたものを全て処分して、空きのスペースを作るだけでよい。もし永年保存すべきものがあったら、そのコーナーに移し、他は捨てる。
さらに、上に掲げていた「今年度」と「昨年度」のタイトルを入れ替える。(中身は場所を変えなくてもよい)
これで、「今年度のがんばり」の場所には何も入っていない状態になるので、新しく賞状や盾をもらってくるたびにそれを入れていけばいい。
過去の立派な成績をずらりと並べて、「あなたがたも、これに負けないように頑張らなくてはいけません」と激励するのは古い教育観、子供たちの小さな頑張りも全て認めて大事にしてやるのが新しい教育観だという。賞状等の陳列棚も新しい教育観にあったものに変えていかなくてはならないだろう。
」
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ