絶対できる校内TV放送
どこの学校でも校内放送というのは行われていると思うが、新しい校舎の学校では、スピーカーから出る音声だけでなく、教室等に配置されたテレビを通しての画像放送ができるようになっている学校もあると思う。
私もそういう学校にいたことがあるが、放送室からの操作で、校内スタジオからの生中継や、収録してあるビデオテープの放映などが簡単にできる。風邪が流行っている時期などは、全校集会を体育館で行わず、校長先生の話や児童委員会からの連絡などを事前にビデオに収録しておいて、それを全部の教室でテレビで見てもらうなど、けっこう便利なものである。
「とは言っても、うちの学校は校舎も古いから、そんなことはできない」とお考えではないだろうか。
ところがどっこい、学校にテレビがあるところなら、全てこの校内TV放送が可能なのである。(事実、私は、自分がいた全ての学校でこれをやってきた)
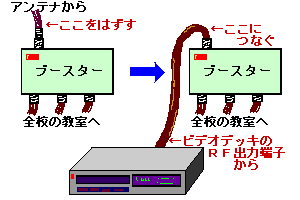 左の図をご覧いただきたい。
左の図をご覧いただきたい。
どこの学校でも、NHKなど一般のTV放送を各教室で見ているとなれば、必ずアンテナからの電気信号を増幅して各教室に送っているはずである。
これをやっているのが「ブースター」という機械である。
この「ブースター」のある場所を見つけさえすれば、校内TV放送は可能になる。
放送室の近くにあることもあるが、多くの場合は、学校のTVアンテナから近い場所にあるはずだ。私の体験では最上階か、更にその上の屋上にある場所(貯水槽など)に設置されていることが多い。
アンテナから入った電波を増幅して各教室に送っているのがブースターなのだから、アンテナからの入力のかわりに、ビデオデッキからの信号を送ってしまおうというのが、この考え方である。
ビデオデッキから出力させるのは、ビデオ出力ではなく、アンテナからの入力と同じ種類のものを出す「RF出力端子」を使う。これは1チャンネルと2チャンネルの切り替えがついているので、自分の学校の環境に合ったものを選ぶ。
これでビデオデッキの再生をすれば、各教室でそれを見ることができる。ただし、この間、一般の(電波で受信する)TVを見ることはできなくなる。また各教室のTV受信機のチャンネル設定を、きちんとVHFの1(または2)チャンネルに合わせておくことも必要である。
この方法でやってみて、校内の一部でしか見ることができなかったとしたら、そのブースターが、おおもとのブースターではないということになる。ほとんどの学校では、このブースターを階層的に使っている。つまり、おおもとのブースターで増幅した信号を、1階棟・2階棟などの二次ブースターに送り、そこから各教室に送るという仕組みである。
全校で同時に見るには、おおもとを探すことが必要だが、この二次ブースターもうまく使えば、その学年棟だけで、一緒にビデオを見るなどというときには重宝する。
ビデオデッキがカメラからの入力も可能なものなら、生放送もできる。
私は電気関係の専門家ではないので、ゲインの問題などはあるかもしれないが、とりあえずこの方法で全校TV放送が可能であることは、どこの学校でも体験してきた。
一度チャレンジしてみる価値はあると思う。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ