ハイマウントストップランプ
最近になって気づいたのだが、ハイマウントストップランプを装着している自動車が増えてきたようだ。
ハイマウントストップランプとは、正式には「補助制動灯」と呼ぶらしい。下の図の赤色の部分がそれである。
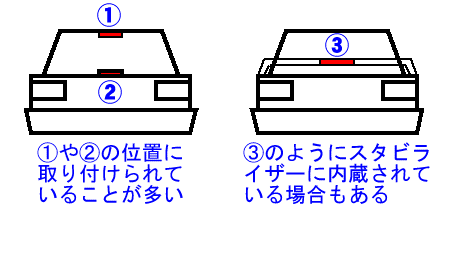
我が国では、平成14(2002)年9月より、乗車定員10人未満の乗用自動車への装備が義務付けられたそうだ。(現在、備え付けられていない車はそのままでもかまわないが、2006年以降に生産される車は装備が義務付けられるとのこと)
アメリカでは1985年に乗用車、1993年に小型トラックに装備が義務化されたし、ヨーロッパ(EU)でも1998年に乗用車への装備を義務化している。
今回の国土交通省の保安基準改正での、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)装備義務化は、追突事故防止のためということである。
追突防止にどのような効果があるのか、例によって「物好き」の虫が動き出してきたので、ハイマウントストップランプをじっと見て考察してみた。
ハイマウントというぐらいだから、車両の高い位置に装備されるのだが、車によってはそれほど高くない位置に付いているものもある。上の図の2や3の例はそうであるし、デザイン面を重視してリアデッキ上端に付けた車もある。ベンツのスポーツタイプなどはテールランプより数センチ上に付いているだけである。しかし、それでもヨーロッパの保安基準を満たしているわけだから、「高い位置に付けたから後方車からの視認性が増す」ということでもなさそうである。
よく見ているうちに、昼夜による周囲の明るさや、テールランプとの明るさとの関係が大事なのではないかと思ってきた。以下、うんちくを述べてみたい(^^;)
まずは、周囲が明るいとき(昼間)に、車がブレーキを踏んだときの様子である。
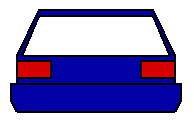
この図では補助制動灯がないのだが、ブレーキを踏まない状態だとテールランプが点灯していないので、テールランプと同じ位置にある(内蔵されている)ストップランプがブレーキによって点灯すると、かなり目立って、後続車の注意を喚起することができる。
次は、補助制動灯がない車が、夜間にブレーキを踏んだ様子である。
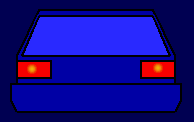
この場合、テールランプが点灯しているので、ブレーキランプが点灯しても明るさが増すだけで、変化を認識しにくい。うっかりすると前の車がブレーキを踏んだことに気づかず追突するという事故が起こる可能性もあるだろう。
そこで、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)を装備すると、夜間にはこのようになる。
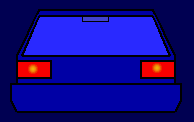
リアウインドウ上部に取り付けられた補助制動灯は、それほど大きくはないが、ブレーキを踏んだときにだけ点灯するので、後続車に対するアピール度は大きい。ふだん何も光っていない位置で新しく光り出すという効果であろう。
ここまでで、補助制動灯の効果は確認できたのだが、昼間の効果はどうだろう。
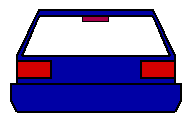
昼間にも補助制動灯は点灯するのだが、それよりも面積の大きいテールランプ内のブレーキランプのほうが目立つために、後続車の運転手はそちらに注意が向くと思う。(私が最近まで補助制動灯装着車が増えていることに気づかなかったのは、日中に車を見ることが多かったからかもしれない)日中であれば補助制動灯がなくても追突事故の危険性は少ないように思う。
以上のようなことを考えると、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)は夜間の追突事故防止に効果が大きいようだ。
また、補助制動灯取り付け位置の高さはあまり問題にならないように思う。ブレーキランプと同じ位置でさえなければ、極端に低い位置でない限り、十分に役目を果たすことができるだろう。
最初に書いたように、2006年以降に生産される車以外は、補助制動灯を装着していなくても問題はないとのことだが、夜間に運転する機会が多い車は、カー用品店などで売られているストップランプを自分で取り付けたりする(ガラスに吸盤で付けられるものもある)ことも、追突事故防止には有効かと思う。
「既に他のものがある場所で光っても注目されないが、何もない場所で光れば注目される」とか、「ふだんは目立たないが、いざというときには小さくても大きな役目を果たす」など、ハイマウントストップランプ(補助制動灯)を見ていると、人生についてもいろいろと教えられるような気がするのは、なんでもこじつけたがる私の悪い癖かもしれないが‥‥‥(^^;)
<02.12.28>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ