紙巻器の革命
道具・機械の類でめざましい進歩・変化を遂げたものと、ほとんど変わりがないものがある。
私が子供の頃(40年ほど前)と今とを比べてみると、それがよくわかる。
コンピュータなどは、私が子供の頃にはもちろん(一般家庭には)なかったし、視聴覚機器の発展もめざましい。
ところが鉛筆削り機などは、ここ数十年、ほとんど変化がなかったように見える。電動餅つき器などもそうだ。こういった構造がシンプルなものは、一度、基本型ができてしまえば、あとは変化がないのかもしれない。
構造がシンプルで基本型ができていたと思っていたのに、近年になって大きな変化が起きたものに出会った。
それが、トイレットペーパーの紙巻器である。
「紙巻器」というのは耳慣れない呼称だが、業界ではそう呼ぶのが正しいのだそうだ。一般には「トイレットペーパーホルダー」などと呼ばれている、トイレットペーパーを装着するあの器具である。(トイレットペーパーホルダーというと、紙巻器ではなく予備のペーパーを保管しておく棚等を指す場合もあるらしい)
トイレットペーパーの構造(というほど大袈裟なものではないが‥‥)は下の図のようになっている。
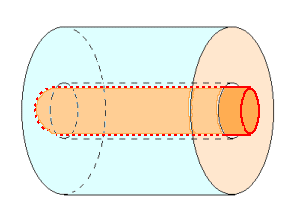
トイレットペーパーのロールの中央に空いている穴に、図のように心棒を差し入れて保持し、トイレットペーパーを回転させて紙を巻き出すのである。
ペーパーがなくなるとロールを交換しなければならないのだが、交換のために下の図のような仕組みになっているのが一般的だったと思う。
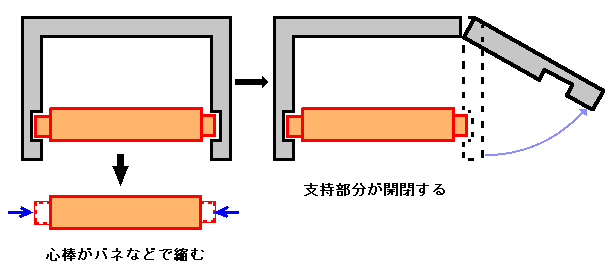
左の方は心棒が縮むタイプである。右の方は心棒を支持する部分が開くものである。(右の場合、心棒が支持部分に固定されているタイプもある)
いずれも使い終わったペーパーのロールから心棒を抜き出し、新しいロールに差し入れるという作業が必要である。
この作業が意外に面倒である。両手を使わなくてはいけないし、交換の際に新しいトイレットペーパーを床や棚の上に置かないと作業ができないということもある。
うっかりすると、手もとがくるって心棒やトイレットペーパーを便器に落としてしまうなどということもあるかもしれない(^^;)
トイレの紙巻器は、そんなにしょっちゅう更新するものでもないので、トイレを新しくしたときからずっと同じ物を使っているということも多いだろう。場合によっては10年・20年と使い続けることもあるかもしれない。
私の家でも、数年前に紙巻器が壊れたので、しかたなく新しい物に取り替えたのだが、その紙巻器を見て驚いた。(下の写真のようなタイプである)

なんと、心棒がないのである!!
上の写真でもある程度はわかるのだが、構造は下の図のようになっている。
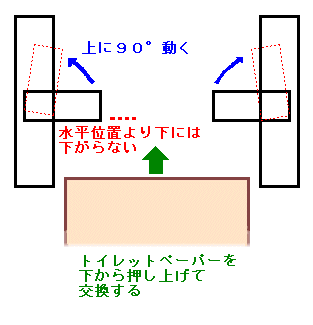
この方法だと、新しいトイレットペーパーを下から押し上げるだけでワンタッチで交換できる。使い終わったロールも同時に上に押し上げられるから、交換は1回の動作で済む。
トイレットペーパーのロールの中にある円筒状の空間に、円筒状の心棒を差し入れないといけないという発想を捨てたときに、この紙巻器が生まれたのであろう。私には革命的なアイディアに感じられた。
私がこの紙巻器を知ったのは近年のことだが、学校で子供たちに聞いてみたら、7割ぐらいの子供たちの家庭でこのタイプの紙巻器を使っているということだったので、もっと前から普及していたのかもしれない。
いずれにせよ、私がこの紙巻器を初めて見たときは、大きなショックを受けると同時にとても感動したものである。
紙巻器そのものはそんなに高価なものでもないので、「うちでは10年以上も古いタイプのものを使っている」という方には、新しいタイプのものに替えてみることをお勧めしたい。
トイレットペーパーの交換が楽になるとともに、交換するたびに「世の中にはアタマのよい人もいるもんだなぁ‥‥」と感動できること請け合いである(^^;)
<02.12.23>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ