音の出口の話
電気を使った音響(オーディオ)機器の出力装置はスピーカー(またはイヤホン)である。
電話のように人の話し声が聴き取れればよいというなら、ちっぽけなスピーカーでも問題はないが、楽器の演奏音などを生々しく再生したいならば出力装置のスピーカーが高性能なほうがよい。
入力装置や増幅装置にどんなにお金をかけても、貧弱なスピーカーを使えば貧弱な音しか出ない。極端な話、スピーカーがなければ音響装置そのものがないのと同じである。
さて、そのスピーカーであるが、ステレオに図のような裸のスピーカーをつないでも良い音は出ない。たとえそのスピーカーが何万円もするようなものであっても、これでは貧弱な音しか出ない。

スピーカーのコーン(振動部分)はアンプから送られた信号の通りに正しく振動しているのだが、それが迫力ある音として私たちの耳には届かない。
スピーカーの音を邪魔しているのは、実はスピーカー自身なのである。
スピーカーは電気信号に変えられた音の振動を再現するためにコーンを前後に振動させ、空気の濃い部分薄い部分を作り出す。これが空気を伝わって耳に届き、鼓膜が震えて音を感じる。
ところがスピーカーのコーンが前に出て圧縮した濃い空気を作り出している時に、コーンの背面は薄い空気を作り出しているのである。
スピーカーの前面からの振動だけが耳に届けば原音を忠実に再現することになるのだが、逆位相の背面からの振動が前面からの正位相の振動と干渉し合って音を打ち消してしまうので、ちゃんとした音にならないのである。(図参照)
この現象は周波数の高い高音域ではたいして問題にならないのだが、周波数の低い低音域では干渉が如実に現れるので、スピーカーから聞こえるのは低域のない寂しい音になってしまう。
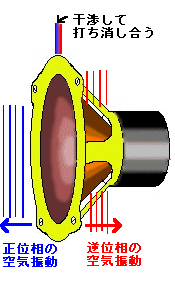
背面から出る音を消して、前面からの音だけが聞こえるようにするには、スピーカーを板や箱に取り付けるとよい。
下の図のような方法がある。(図はいずれも断面図である)
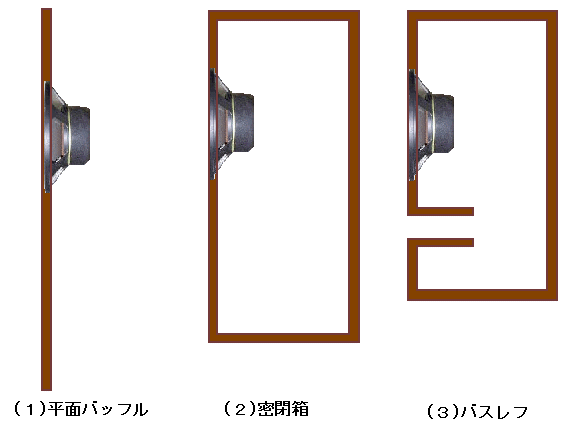
(1)は平面バッフルという方法である。
大きな1枚の板にスピーカーを取り付ける。板は大きければ大きいほどよい。無限大のバッフルが理想的なのだが、それは無理なので1辺が1m程度の板でもよいだろう。
コーンの振動を妨げるものがないので、素直な音が出る。ただ、板の剛性が低いと、スピーカー自体の振動が板に伝わってビビリ音のような板鳴りを起こすことがあるので、補強材を裏に取り付けたりする工夫も必要である。
この発想を大胆にすれば、隣の部屋との境の壁に取り付けるなどという方法もある。条件が許すならば素晴らしい音が出るはずである(^^;)
(2)は密閉箱という方法で、背面からの音が外に漏れないように、空気が漏れない箱にスピーカーを取り付けるものである。
この方法だと、箱の中の空気が逃げる場所がないので、空気がバネのようなはたらきをして、コーンの振動を抑制してしまう。したがって箱が小さいとスピーカーのコーンは思うように振動できない。
スピーカーに素直な音を出させるには、密閉箱の容量を十分に大きくする必要がある。(スピーカーを買うと指定箱の図面がついていることもある)
(3)はバスレフという方法である。語義の通り、バス(低音)レフ(反射)ということで、空気箱の中で低域の振動を反転させて前面に放射させるやり方である。
スピーカーコーンの背面から放出される逆位相の振動を箱の中で正位相の振動に変換して低域の音を増大させるという方法で、そのための箱内の容量やホーンダクトの寸法を計算するのは難しいが、うまくやれば迫力のある音を出すことができる。小型のスピーカーシステムを作るには効果的な方法である。
これを更に効率的にした方法としてバックロードホーンというやり方もある。箱の設計は難しいが、うまくやれば驚異的な効果を得ることもできる。
以上の3つの方法で、スピーカーのコーンの振動を効果的に前面に伝えることができるのだが、最近では、スピーカーのマグネットのパワーを上げて、密閉箱の空気ダンピングを無視して強制的にコーンを振動させたり、アンプ部分で低域を増幅して空気ダンピングに負けない振動を起こさせたりするという方法で、小さなスピーカーボックスでも迫力ある音を鳴らすという方法も使われているようだが、ロック系の派手な音では効果的ではあるが、クラシックのオーケストラ演奏のような周波数帯域の広い演奏や、ジャズのように中音域の豊かさが要求されるような演奏では、スピーカーが伸び伸びと無理なく振動できるような、大容量密閉箱の方に軍配が上がるような気もする。
上記の方法はいずれもスピーカーを使うので、部屋(リスニングルーム)が必要なのだが、音楽の空気振動を直接、鼓膜に伝えるというヘッドフォン(イヤフォン)の方法もある。
大別すると、下の図のように4つの方法がある。
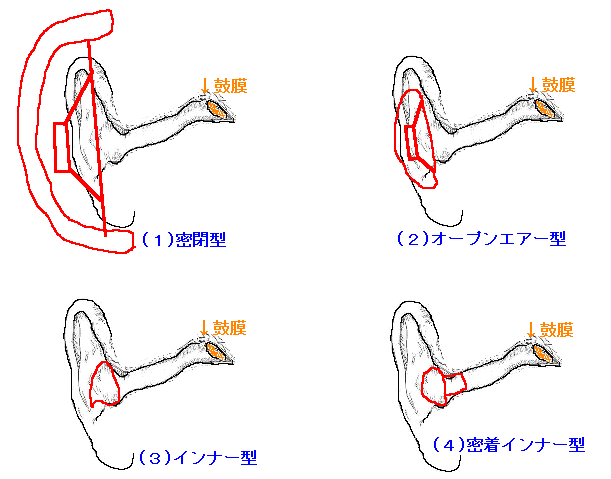
図の(1)が昔からあったいわゆるヘッドフォンである。耳たぶ(耳介)の外側をふさぐ大きな耳あてのような中に小さめのスピーカーを内蔵したものである。
スピーカーの口径もけっこう大きめなものを使えるので、出てくる音は自然であるし、鼓膜までの距離も大きいので音の響きも素直である。聴感的にはリスニングルームでスピーカーを鳴らした感じに近いものを得ることができる。ただ装置そのものが大きくなってしまうし、耳に圧着させるためのヘッドバンドが必要になるので、かなりかさばる。寝るときにベッドで装着するとか、電車の中で装着するには向かないかもしれない。音質的にはこれが一番なのではないかと思う。
最近はこの手のヘッドフォンも安くなったが、昔、数万円もしたこの手のヘッドフォンはかなり良い音がする。
(2)は、(1)の密閉型ヘッドフォンを小型にしたタイプである。
ひと昔前は密閉型ヘッドフォンのように頭の上から装着するヘッドバンド型が多かったが、この頃では耳にきちんと装着するために耳たぶの付け根に眼鏡のつるのようなクリップを使っているタイプが増えてきた。
見た目はかっこいいが、実際の音となると、(1)の密閉型や、(3)のインナー型よりは劣るような感じがする。
(3)は、ウォークマンタイプのステレオカセットなどによく使われているような「耳穴にはめ込む」タイプのヘッドフォンである。一般的には「インナーレシーバー」などと呼ばれているようだ。
このタイプの音質は価格によって千差万別である。安価なステレオカセットなどに添付しているものは情けない音質のものもあるが、インナーレシーバーとして単品販売されているもので、価格が5千円以上するものだとかなりの音質である。
ただし、耳穴の形状は人によって異なるので、うまくフィットすればよい音質で聞こえるのだが、そうでないと寂しい音質にもなる。(下の図の青のようにコードが下に垂れるように耳穴に入れるのが一般的だが、耳穴の形状によっては図の赤のようにコードが前にくるような装着の仕方の方がフィットすることもある。お試しいただきたい)
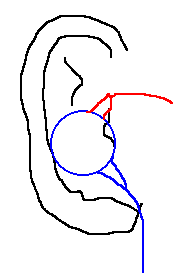
このインナー型のヘッドフォンを外側から指で押さえて耳穴に密着して聞ければ、かなりの高音質が期待できるのだが、ただ耳穴に突っ込んだだけでは低域が不足することもある。最近は密着度を増すためにこのインナー型にヘッドバンド(見た目をよくするために首の後を通すタイプも多い)を組み合わせたり、耳たぶクリップ型を組み合わせたりしているものも出てきている。個人的には、耳たぶクリップ式のものが気に入っている。
(4)はインナータイプのものの密着度を高めるために、柔らかい素材のパイプのようなものを外耳道の中に突っ込むようにしたものである。
音響的にはスピーカーの振動を無駄なく鼓膜に伝えるので効果的ではあるが、外界からの音は一切内部に伝えない仕組みであるため、これを装着していると外の音は全く聞こえないそうだし、(私はこのタイプを持っていないので、ネット上の使用情報しかわからないのだが)あまり良い音ではないというハナシも聞く。
いずれ、自分でも購入して試用してみたいとは思うが、あまりにも鼓膜にダイレクトに振動が伝わる感じがあり、空気の響きが伝えられないような感じもあるし、耳の健康にもよくないような感じがあって、今の時点ではお勧めできないような気がする(^^;)
この手のヘッドフォン(イヤフォン)の情報は、インターネット上で検索すれば入手できると思うが、いろんなスタイルのヘッドフォンの情報を一度に見るとすれば、こちらのサイトなどは便利かと思う。
シンセサイザーのように生音がなく、最初からスピーカーで再生されることを前提にしている楽器もあるが、たいていの音楽はマイクで拾った空気振動を、スピーカーの振動によって再生することになる。
生楽器が作り出す空気の震えを再現して、それが鼓膜に伝わるのが理想的なのだが、十分な広さと防音設備のあるリスニングルームを確保するのも難しい。スピーカーの使いこなしを工夫したり、ヘッドフォンを活用したりして、質のよい音楽を楽しみたいものである。
余談めいたハナシになるが、ヘッドフォンは音程を正確に再現していないような気もする。
自作曲を録音するときに、作ったカラオケをヘッドフォンで聴きながら歌をマイクに入れるのだが、どうも伴奏の音程と歌の音程がずれ気味である。私の音感が悪いせいもあるだろうが、ヘッドフォンから聞こえてくる音楽のピッチがずれているような気がする。
大きめのスピーカーから伴奏を再生し、自分の生の声と聞き合わせて歌えば、それほど音程がずれることはないのだが、ヘッドフォンで伴奏の音楽とマイクで拾った自分の声を聞きながら歌うと、ピッチがずれるように思う。
もっと高性能のヘッドフォンを使えばよいのかもしれないが、肌で感じる空気の振動というのも大事なのかもしれない‥‥。
<02.11.14>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ