正しい一本締め
宴会などの最後に「それでは皆さん、お手を拝借」と手拍子をすることがある。
正式には「手締め」といい、広辞苑によると「事の決着を祝って行うそろいの拍手」と説明されている。
手締めにもいろいろな種類があるようだが、私には三本締めというやり方が一番なじみが深い。「よーぉっ」というかけ声の後に「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」という手拍子を3回繰り返すやり方である。
リズム譜にすると、次のようになる。
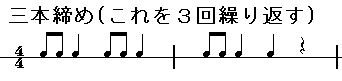
音にすると次のようになる(MIDIデータが再生可能な方は下のMIDIプレーヤの再生ボタンをクリックして聞いていただきたい)
宴会の締めに「それでは、三本締めでお願いします」と言われると、私は何も悩むことなく、気持ちよく手をたたくわけである(^^;)
ところが、最近では「一本締めでお願いします」という場面も多くなった。
これが問題である。
私の感覚では、三本締めが上の例のようなのだから、一本締めはその3分の1ということになり、下のリズム譜のように、「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」を1回だけやるという具合になるはずである。

そのつもりで、「シャシャシャン‥‥」と手拍子をしようとすると、「よーぉっ、ポン」と手拍子一発で終わってしまうことがある。他の人が手拍子一発で終わるのに二拍目以降をたたいてしまうと、実にかっこうが悪い(^^;)
これを最初に体験したときは(ちょうど酒宴だったので)おふざけでやっているのかと思ったのだが、最近は結婚披露宴とか○○祝賀会というようなあらたまった席でも、この「よーぉっ、ポン」に遭遇することがある。
テレビでも、スポーツ選手や政治家などが、これをやっているのを目にすることがある。
三本締めを「よーぉっ、ポンポンポン」とやる人はいないだろう。誰でも「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」と手拍子をするはずである。
ところが、これが一本締めになると、「よーぉっ、ポン」というやり方が増えている。「三本締め ÷ 3 = 一本締め」という計算式が成り立たなくなっているのである。
私にはどうもこの不合理が気にくわなかった(^^;)
そこで、いろいろ調べてみたら、次のようなことがわかった。
一本締め
本来、一本締めというのは、私が思っているように、「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」と手をたたくやり方である。
一丁締め
「よーぉっ、ポン」と手拍子一発で終わるやり方は、一丁締めという。
関東一本締め
ところが、関東地方では、一丁締めを一本締めと呼び、「一本締めでお手を拝借」と言われると「よーぉっ、ポン」とたたくところが多い。
要するに「よーぉっ、ポン」を一本締めとして行うのは、関東地方のローカルなやり方である。もちろん手締めについて定めた法律などはないので、その地方その地方で一般的なやり方でやればよいわけだが、関東が人口の面でも文化の影響の面でも大きな比重をしめていることや、テレビなどが「関東一本締め」を紹介していることによって、私のような正常な数感覚を持つ人間が、一本締めの世界から駆逐されようとしている(^^;)
別にそれに目くじらを立てる必要もないのだが、言葉の整合性という筋を通すならば、一本締めは「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」であるべきである。
関東の人が関東で「一本締めでお願いします」と言って、全員が「よーぉっ、ポン」で終わるなら何の問題もないが、関東以外の土地に行ってこれをやろうとするならば「関東風の一本締め(あるいは『一丁締め』)で、ポンと一発お願いします」と言うべきであろう。
そうしてもらえれば、私も「どうやって手をたたこうか?」と悩まないですむ(^^;)
一本締めといいながら一丁締めをやったとしても罪になるわけではないのだが、私が正規の一本締めにこだわるのは、それなりの理由がある。
「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」という、三拍を三回重ね、それにもう一拍つける手拍子には、悪いことを遠ざけ、めでたいことを願うという意味があるのだそうだ。
三を三つ重ねると「九」になる。「九」は「苦」にもつながるが、「九」という文字にもう一つ点を加えると「丸」になって、全てが丸くおさまるということにつながるのだそうだ。
そういう深い意味があるのだとすれば、願いをこめて「シャシャシャン、シャシャシャン、シャシャシャンシャン」と手をたたきたい気にもなるし、それをさらに三つ重ねる三本締めは、いっそうありがたみが増す(^^;)
これを「よーぉっ、ポン」の一発だけで終わらせてしまうのは、私にはありがたみがないという感じに加えて、なんだかおふざけで失礼なような気もする。一発の拍手に全ての気持ちをこめるという解釈もあるかもしれないが、結婚披露宴とか○○竣工式とかいうようなめでたい会で、参加者一同が幸せを願うというような場合には、できれば三本締めをやるのが望ましいし、簡略化したとしても正規の一本締めをやりたいものである。(もちろん、先祖代々、いわゆる一丁締めで手締めをやってきたという地域に、私の考えを押しつけるつもりはないが‥‥)
ちなみに、「よーぉっ」という最初の発声も、単なるかけ声だけではなくて、「祝おう」からきているのだそうだ。
また、手締めの音頭取りは、主催者側が行うべきもので、来賓に音頭取りをしてもらうのは大変に失礼なことなのだという。
これらは、今回、この文章を書くためにいろいろ調べていて、私が初めて知ったことである。
これもまた余談になるが、手締めをするときに、応援団などがやる「三三七拍子」と間違えてしまう人がいるとか、手締めの後半の拍数をちょっと増やすと三三七拍子になるというようなことが、今回検索したサイトの中にいくつか書かれていたが、私は「ちょっと違うんじゃないかな」と思った。
三三七拍子を文字で書くと「チャンチャンチャン、チャンチャンチャン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン」となり、手締めと似ているように思えるが、リズム譜にすると次のようになる。
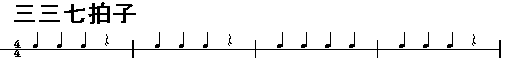
音にしてみると、下のようになる。
上の手締めの例と比較していただければわかるが、手締めの場合は一拍の基本単位が8分音符なのに対して、三三七拍子では4分音符が一拍の基本になっている。リズムの乗りが半分(倍)なので、根本的に別種のものなのではないかと思う。
<02.09.01>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ