お歯黒が消えた
私が小学生の頃(昭和30年代後半)といえば、テレビの普及期なのだが、テレビで見る時代劇では、登場人物の女性がお歯黒をしているものが多かった。
お歯黒は、江戸時代まで既婚女性のあかしとして行われていた風習で、歯を黒く染める化粧である。
江戸時代の既婚女性は、眉も剃っていたので、おしろいを塗った眉のない白い顔に、口元から黒い歯がのぞく顔は、一種独特の雰囲気があり(どちらかというと異様な感じだったが)子供の頃の私は強い印象を受けた。
当時、時代劇によく出演していた浪花千栄子さんなどは、そういう化粧をすると「翁媼の人形」の「媼」のようで、いかにも昔の女性はこんな感じだったのだろうなと思ったことを覚えている。

|
|

|
浪花千栄子さん
オロナインH軟
膏の看板より
|
|
眉を剃り、お
歯黒をすると
こんな感じ
|
お歯黒については、インターネットで検索をしていただけば、詳しい情報を得ることができるのだが、私が調べた情報を、以下、簡単にまとめてみよう。
お歯黒のはじまり
古墳からもお歯黒をした埴輪(はにわ)が見つかったということなので、かなり古くから行われていたようだ。「古事記」にもお歯黒について書かれたと思われる記述もあるそうで、4〜5世紀頃に大陸から伝わったらしい。
当時の酒造りは「口醸す酒」製法で、山ブドウ・桃・杏等の果物を口で噛み、壺に入れて唾液で発酵させたという。それをやっていたのが女性たちで、よく働く女性の歯は果物の渋で黒くなった。これが「働く女性の美しさ」として習慣になったという説がある。
また、山ブドウなどを妊婦が好んで食べたので、ブドウの渋で歯が染まるのが既婚の女性のあかしとされたという説もある。
平安時代のお歯黒
平安中期までのお歯黒は、草木・果物染めの方法で行われていたようだ。その後、鉄文化が伝わり、鉄を材料としたお歯黒が一般的になった。(お歯黒の別称「つけがね」もこれによる)
鉄を使ったお歯黒の作り方は、お茶・酒・酢・飴等を混ぜた液体に、焼いた鉄屑を入れて発酵させ、数日おいて錆びて黒くなった液体を沸かして作るもの(鉄漿水)だったという。かなり悪臭がして、体質に合わないと口が腫れ上がるなどということもあったようだ。
西暦753年に渡日した鑑真和尚が、酢酸第一鉄(鉄漿水)のかわりに硫酸第一鉄(緑バン)を使うお歯黒を伝え、高価ではあったが悪臭がなく、付きもよいものだったので広く普及したようだ。
上流階級の女性は、成人のあかしとして、17歳頃にお歯黒をするようになった。また男性も表情を柔和に見せて女性にもてるようにとお歯黒をする習慣があったようだ。今のお化粧ロックバンドなどと同じ感覚かもしれない(^^;) 11世紀頃から行われたようだが、男性の場合は身分の高い層に限定されていたようである。平家・源氏の公達や今川義元・北条早雲などもお歯黒をしていたという。戦で首をとったときに、身分の高い人物であるとごまかすために、首の歯にお歯黒をつけたという逸話もある(^^;)
室町・戦国時代
女性のお歯黒はかなり普及して、13歳頃にはお歯黒をするようになった。これを「十三鉄漿(じゅうさんかねつけ)」と呼ぶそうだ。一方、男性のお歯黒は、戦いなどが激しくなるにつれ、衰退していった。
江戸時代
世の中が平和になり、生活も安定してきた元禄時代には、女性のお歯黒は身分を問わず全国的に普及してきたようだ。13歳の11月15日には「お歯黒染めの日」というお祝いをし、お歯黒を始めたという。ただ、お歯黒をつけるのはかなり面倒だったようで(黒々としておくためには2日に1回はつけなおす必要があった)実際には庶民の場合、既婚者だけがお歯黒をしていたという。
遊郭の女性や芝居の女形もお歯黒をしていたそうだ。男性のお歯黒は姿を消した。
お歯黒がはげないで、いつも黒々を光らせているには、最低でも1週間に1回は染めなければいけなかったようで、かなりの手間であったらしい。
明治以降
明治になると、お歯黒は旧習とされて禁止令も出されたため、急激に衰退していった。
それでも頑としてお歯黒をつけていた女性もいたようで、資料によると、昭和50年頃に我が秋田県でお歯黒をつけていた90歳以上の女性がいたということである。山形県では平成10年頃までお歯黒を製造していた業者があったそうだ。
私の妻(昭和29年生まれ)も、小さいときに自分の祖母がお歯黒をしていた記憶があるそうだから、地方では終戦後もお歯黒をしていた女性がいたようだ。
お歯黒は歯によい
前述の秋田県の女性の例だと、100歳近い年齢であったのに、歯の年齢を調べてみたら50歳代の状態だったそうだ。
お歯黒をきちんとつけるには歯垢を取り除かなければならず、お歯黒の成分にも虫歯を防ぐものが含まれていたそうで、虫歯予防にはかなりの効果があったそうだ。
というようなことが、お歯黒に関するミニ知識なのだが、この頃はテレビや映画でもお歯黒をつけた女性が登場することはほとんどなく、「お歯黒」そのものを知らない方も多いのではないかもしれない。
これは、テレビ等の時代劇のあり方自体が変容してきたためではないかと思う。
私が子供の頃の、テレビ創生期には、時代劇には「時代考証」というものが大きなウエイトを占めていた。
番組の最初(あるいは最後)のスタッフタイトルには、「音楽:コンソール・レニエ」などといっしょに、「時代考証:○○○○」という文字が大きく出ていた(今でも出る例もあるが)
江戸時代を背景にしたドラマであれば、江戸時代の風俗・習慣に忠実なドラマづくりをすることが義務づけられていたようだ。
江戸時代のドラマに電柱などが映っているのは問題外だが(^^;) 時代的にあり得ないような様子・行動・言葉づかいなどが画面に出ないように、時代考証担当の方が目を光らせていたのである。
ところがこの頃では、時代劇そのものが「昔の時代を舞台にした現代劇」という感じになってきている。歴史資料としての時代劇という要素はほとんどなくなってきたようだ。
したがって、厳密に時代考証をしたらあり得ないような場面も多くなった。
例えば、将軍や大名が家臣一同を大広間に集めるといったシーンの場合、本当ならば蝋燭数本の灯りで薄暗いはずなのに、テレビ画面では大広間はまばゆいぐらいに明るく映っている(^^;)
また、水戸黄門などでも、網タイツのセクシーな女忍者が登場したりするし(^^;) 随行の町人(八兵衛など)が、「畏れ多くも先の副将軍」様とタメ口をきいたりする(^^;)
要は時代劇もドラマであり、娯楽作品なのだから、社会科歴史資料として時代考証を厳密にする必要はないというスタンスになったのだろう。
最初に書いたように、当時の時代に忠実に、眉を剃ってお歯黒をつけると「異様な顔」になることも、出演の女優さんたちが嫌うのかもしれない。
最近の時代劇には、アイドル系や美人系の女優さんたちも多く出演しているが、島田髷や丸髷のカツラをつけていることを除けば、今風の美人顔のままの出演である。
これが、時代に忠実に「眉のないお歯黒顔」であれば、かなりのイメージダウンかもしれない。我々見る側としても、歌番組に出てくるような、ミニスカートに茶髪で可愛いアイドルのイメージを期待しているのであって、お気に入りのアイドルが「白塗りで眉なし、お歯黒顔」の前衛舞踏派のような顔で出てこられたら幻滅を感じるかもしれない(^^;)
ネットサーフィンしていて見つけた「モナリザの微笑み」に、興味深い文章があった。
モナリザは歯を出していないというのである。
永遠の神秘の微笑みともいわれるモナリザは、口を閉じて微笑んでいる。
これが、今流行りのアイドルのように、白い歯をむき出しにしていたら興ざめかもしれない(^^;)
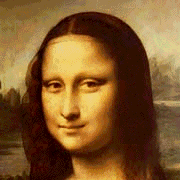
まして、大きく開いた口もとから、お歯黒が覗いたとしてもブキミである(^^;)
江戸時代までのお歯黒美人も、大口を開けて黒い歯を歯茎まで剥き出しにしていたら、かなりグロテスクであろう。
成人女性のあかしとして行われたお歯黒も、実は、その黒い歯をあまり人前にさらさないような奥ゆかしさを求めた制限だったのかもしれないし、それでも垣間見える歯が、十分に手入れされて黒く輝いているところに慎み深い大人の色気を感じたのだとすれば、私が子供心に異様な感じを受けたお歯黒にも納得できるような気もする(^^;)
<01.04.08>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ