ソシオメトリーをもう一度
「いじめや仲間はずれのない楽しい学級づくりを」と、学級担任であれば誰しも願う。
「みんな仲良くしなさいよ」といつも言うことも大事ではあるが、それで事足りるぐらいなら苦労はしない(^^;)
いじめなどのない学級づくりのためには、学級の子供の人間関係を正しく把握し、実態に応じた具体的な手立てを講じることが必要である。
学級集団での人間関係を調べるのに効果的なのが「ソシオメトリー(sociometry)」である。
ギリシア語で集団あるいは社会を意味する「socius」と、測定を意味する「metrum」を語源とする言葉で、社会測定という意味である。アメリカの精神医学者のモレノ(Jacob Levy Moreno、1892〜1976)によって提唱された理論に対して限定的に使われる言葉である。
この理論に沿って行われるのが「ソシオメトリック・テスト」である。
具体的には、集団の中で各成員が他のどの成員を選択するか(好きか)、どの成員を排斥するか(嫌いか)を調査し、その相互関係をまとめる。
一般的には、選択者・排斥者ともに3名程度の名前をあげさせる。
この結果を、図示したものをソシオグラム、表で示したものをソシオマトリクスという。
下の表は、ソシオマトリクスの例である。
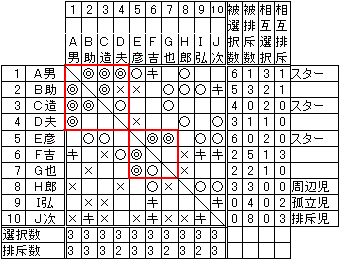
この表を縦に見ていけば、その子が誰を選択し、誰を排斥しているかがわかる。例えば2番のB助の場合は、A男・C造・E彦を選択し、G也・I彦・J次を排斥している。
B助の場合、A男・C造からは選択されているので、相互選択を示す「◎」のマークがついている。また、J次とは相互に排斥しているので、相互排斥を示す「キ」マークになっている。
横に見ていった被選択・被排斥の状況によって、多くの子から選択されている者には「スター」、多くの排斥を受けている者には「排斥児」などの注釈がついている。
赤線で囲んでいるのは、相互選択による結びつきが強い、いわゆる「仲良しグループ」である。その中に入っていない子は、選択・排斥の状況によって、周辺児・孤立児と判断される。
このソシオマトリクスは、参考例として適当に作ってみたので、人数も少ないしちゃんとした調査をもとにしたものでもないが、これでもよく見ると、様々なことがわかってくる。
例えば、一見、仲良しグループのような、A男を中心とした4人グループでも、D夫とB助の人間関係に若干問題があることがわかる。
また、この集団をうまくまとめていくためには、E彦がキーになることも見えてくる。
このようなデータを、学級担任がきちんと把握していれば、学級づくりのための大きな力となることは、この例をご覧になってもおわかりだろう。
ところが、このソシオメトリーを行うのに、難しい問題が2つある。
1つは、データ処理の難しさである。
個々の子供から集めた個別データを、学級全体のマトリクスデータとしてまとめるには、手順を追った複雑な作業が必要で、これは手慣れた人でも半日ぐらいかかってしまう。
私が学級担任をしていた頃(10数年も前だが)、これをパソコンで処理するBASICプログラムを自作して使っていた。当時は今からみたらオモチャ程度の性能しかない8ビットパソコンで処理していたので、データを全て入力してからプリントアウトが済むまで数十分もかかったが、それでも手作業でやるよりは10倍以上速かった。同じ学年の他のクラスの処理も一手に引き受けて重宝がられていた思い出がある。
その後、市販のアプリケーションでも「ソシオ処理プログラム」などが出てきたが、当時は自作プログラムを作る人も多く、中にはパソコン通信などで、自作プログラムを提供している人もいた。(当時はMS-DOSも普及していない頃で、パソコンやプリンタなどメーカー固有の仕様だったので、他人からもらったプログラムもうまく動作しないことも多かったが‥‥。自作したときには、データ処理のプログラムよりもプリンタ制御の部分が難しかった記憶がある)
まあそれでも、データ処理は、定められた手順でこつこつと行えば手作業でもできるのだから、あまり大きな問題ではない。
もっと大きな問題は、調査の際の子供に対する配慮であった。
基本的には、好きな人・嫌いな人を書いてもらうことになるのだが、それをナマのかたちで、「これから好きな人と嫌いな人の名前を3人ずつ書いてもらいます」などと子供に言ったのでは、大騒ぎになる。
そこで、「今度、席の並び替えのときの参考にするので、できれば同じグループになりたいなあと思う人の名前を3人書いてください。それから、なんとなくこの人とはいっしょになりたくないなあと思う人がいたならば、その人の名前も書いてもいいです。そういう人が特別にいないという場合は書かなくてもいいですよ」というような感じで話して、データを集める。
座席の並び替えでなくても、遠足や発表会のグループづくりなどを例にしてもよい。
いずれにせよ、子供にとっては、あまり気持ちのよい調査ではないので、できるだけ子供の気持ちを傷つけないように、じゅうぶん配慮する必要がある。
ところが、この調査が保護者の間で問題になり、新聞等で取り上げられて社会的問題になってしまったことがあった。
平成10年(1998)6月の出来事である。
北海道の小学校で、4年生の担任が、クラスの児童全員に「一緒に遊びたくない子」の実名とその理由を書かせるアンケートを行ったというニュースが全国紙等で大きく報じられた。
そのニュースの詳細については、こちらのサイトや、こちらのサイトでご覧いただきたい。
ニュースとしては「一緒に遊びたくない子」の実名を書かせたということがセンセーショナルに書き立てられているが、記事をよく読んでみると「一緒に遊びたい子」も書かせている。時期的にも5月中旬ということだから、ちょうど学級の実態を調べるには適当な時期である。
おそらく、ソシオメトリック・テストを行ったのであろう。
記事には、校長等が「配慮が足りなかった」ということで陳謝したとある。また上の2つめのサイトの記事では「教育関係者からも児童の名前を記入させたのは行き過ぎとの声もあがっており」という内容もある。
私の考えでは、まさに配慮が足りなかったということだけが問題だと思う。きちんとした配慮があれば、この調査自体は悪いことではない。「児童の名前を記入させたのは行き過ぎ」という教育関係者がいたのだそうだが、その見解には疑問がある。ソシオメトリック・テストは実名の記入なしには成立しないのだ。
この事件があってから、ソシオメトリーについて教育界全体が及び腰になってしまったような感がある。
学級経営のために子供の人間関係を調べたくても、「うちの学校でも新聞に出たような調査をやっているようだ」という保護者からの声が出るのを恐れるためか、ソシオメトリーをやることができなくなった学校も多いようだ。
インターネットで全国の学校の行事表などを検索してみたら、平成10年度までは5月頃に「全校一斉ソシオ週間」などという行事を行っていた学校も、平成11年度からはとりやめている事例もあった。
少し前までは、都道府県の教育センターなどで、教職員を対象にした「ソシオメトリー実践講座」などがあったのだが、この頃は姿を消している。
市販のパソコン・ソシオメトリー処理ソフトもぐっと少なくなった。以前は大々的に宣伝していたのだが、今ではソシオ関連製品の宣伝さえもしなくなったメーカーも多いし、製品としては残していても、旧式のMS-DOSバージョンのままで、新しいWindows対応版を作っていない例もある。
私が教職に就いたばかりの頃は、新任教職員研修や5年経過教職員研修などで「ソシオメトリー」は必修として研修させられたものだが、今は研修内容から消えている。
そのことについて、いろいろ聞いてみたら、「今はソシオメトリック・テスト以外にもすぐれた方法が開発されてきているから」という話もあったが、子供のナマの声を聞いて、学級集団の構造を把握できる方法としては、これ以上のものはないようにも思える。
私が小学生の頃に、担任の先生がこのような調査をした記憶もあるので、教育現場では数十年の間、ソシオメトリック・テストは効果的な手法として行われてきたはずである。それが、ここ1・2年で潮が引くように消えてしまったのは、やはり前述のニュース報道が影響しているのではないだろうか。
では、どんな配慮があればよいのだろうか。
私は、校長の腹ひとつだと思う。
ソシオメトリーを行う場合、その話し方や調査の仕方にじゅうぶんな工夫がいるのは言うまでもないが、その調査を行う担任がどんなに配慮をしたとしても、自分が独断専行で、校長の許可も得ないで行うのはよくない。
本来であれば、担任が調査をしたいからという希望を出して行うのではなく、校長が「子供の実態把握のために学校全体で行おう」という姿勢を示すべきである。
仮に、校長がそのことに気づかずにいて、一人の担任から「こういう調査を行いたいのですが」という申し出があった場合、「ああそうですか。○○先生、やっていいですよ」と言うだけでなく、「○○先生、それは良い方法ですね。ぜひ学校全体で取り組んでみましょう」という姿勢が欲しい。
学校全体としての取り組みであるから、保護者に対して説明をし、同意を得るのは校長の仕事である。
前にも触れたように、学級経営にデータを生かすのであれば、1学期の前半の5月か6月には実施したい。そうなれば、4月のPTA総会などの機会に、学校全体の経営方針を話す場があるはずだから、そこで「今年度はいじめなどのない仲の良い学級づくりを進めたい。そのためには5月頃にこういった調査を行う。悪いことに使うという意図はなく、学級の実態に即した指導を行うためなのでご了承いただきたい。実施に際しては子供の心を傷つけないように十分に配慮する」という説明をすればよい。
きちんと話をすれば同意は得られるはずだし、仮に反対意見が出たとすれば、その時点で実施を取りやめることにすればよいわけだから、前述のように新聞沙汰になることはない。
つい先日、いじめによる自殺事件の裁判で、いじめを放置していた学校にも大きな責任があるという判決が出たそうだが、学校には子供の実態をきちんと把握し、状況に対応した手立てをとる責任がある。
「子供に好きな人や嫌いな人を書かせるような調査をしなくても、ふだんから子供の様子をきちんと見ていれば、子供どうしの人間関係は把握できるはずだ」という意見もあるが、それは甘いと思う。
表面だけを見ていたのではわからないから隠れたいじめなどがある。いじめや仲間はずれがあることをわかっていながら放置しておく学校はほとんどないだろう。一見、仲がよさそうだとしか見えないので、結果的にいじめなどを放置することになってしまうのである。
隠れた実態をつかむには、「この学校にいじめはありますか?」などという間の抜けた質問法ではなく、ソシオメトリーが効果的である。隠れて見えなかった実態が明らかになるし、その対応法も見えてくる。
一部の配慮不足の取り組みを過剰に騒ぎ立てた報道によって、良い方法もできなくなるような及び腰ではなく、校長をリーダーとして、きちんとした学校経営の方針のもとに、「子供にとって良い」と思うことを自信をもって進めていくことが大切だと考える。
<01.01.17>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ