教師の感覚の世代間ギャップ
私の地域の教頭会で「子供の変容に関するアンケート」を行った。最近の子供の実態を考えようという趣旨ではあるが、むしろ私には教師の意識調査という意味で興味深かった。
アンケートは、「友達とうまくかかわれない子供が増えたと思うか」「指示待ちの子供が増えたと思うか」等の設問で、その回答結果を20代・30代・40代以上の教師層に分けて集計している。
それをグラフにしたのが下の図である。それぞれのグラフのタイトルが「○○な子供」というようになっているが、これは「○○な子供が増えたと思う」という意味である。
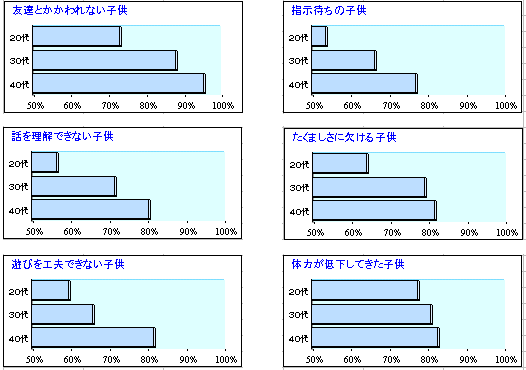
どの年代でも「そういう子供が増えている」と答えた教師が多いのだが、世代によるとらえ方に大きな差があることに気づく。
グラフの最小目盛りが50%なので、結果が強調されてはいるが、「話を理解できない子供」「遊びを工夫できない子供」等で「そういう子供が増えていると思う」と答えたのが、20代では50%台なのに、40代以上だと80%以上になっている。このデータを見ると、明らかに子供を見る感覚が世代によって違っていると言えるだろう。
なお、このアンケートは全体で300人以上の回答を得たものであり、それぞれの年代の回答者数も100人前後であるから、ある程度の信頼性・普遍性を持ったものと考えてもよいだろう。
全ての回答結果について世代間の違いがあるわけではなく、「体力が低下してきた子供」などでは世代間の差は10%もない。やはり20代と40代で回答に差があるものについては、そのこと(遊びを工夫する等)についての感覚の違いが存在すると考えてもよいだろう。
ここで、20代・30代・40代以上が育った環境について少し考えてみよう。
私は現在46歳なので、りっぱな40代以上なわけだが(^^;) ひとことでいうと何もない時代に育ったといえる。細かく見れば今の40代はテレビがある子供時代を過ごし、50代はテレビのない子供時代を過ごしたという差はあるが、後述する20代・30代の人たちの子供時代とは大きな差が2つある。
まずは20代との差だが、この世代はテレビゲーム世代と言ってもよいだろう。初代ファミコンが発売されたのが昭和58(1983)年の7月。当時12歳の子供は今ちょうど29歳になる。全ての子供がテレビゲームに興じたわけではないだろうが、今の20代の人たちの子供時代の遊びの中心にテレビゲームがあったことは確かだろう。
次に30代の人たちと私の世代との大きな違いは放課後の過ごし方、言い換えればスポーツ少年団の有無である。日本にスポ少が発足したのが昭和37(1962)年。これが一般化したのが昭和40年代なかばである。ちょうど今の30代の人たちがスポ少世代ということになる。私がこれまで「うんちく」で何度も書いているように、スポ少の普及によって、地域での異年齢集団の遊び文化が消えてしまった。
テレビゲームとスポ少という2つの要素によって、20代・30代・40代以上の世代間に大きな生育歴の違いが生じている。
私のような40代以上の人間だと、子供の頃の遊びは自由に野山を駆け回るものだった。特別な遊び道具もなかったので「遊びは工夫するもの」というのが当然だったし、道路を走る車もほとんどなかったので、遊び場はいたるところにあった。
ところが交通量が増え、道路は子供の遊び場でなくなり、スポ少の練習で近所の小さい子と遊ぶ機会も消滅し、さらにテレビゲームの普及で子供の遊びは室内中心になってしまい、遊びの質は変わった。
40代以上が「自分の子供の頃は野山を駆け回って遊んだものだ」などと言っても、部屋の中でテレビゲームをするのが普通だった20代の人たちにはぴんとこないだろう。彼らは私たちよりははるかに今の子供に近い育ち方をしているのである。
「話を理解できない」という点でも、私の子供時代の教師は、ほとんどが戦中に育った年代だったので、「話す人のほうをしっかり向いて、背筋を伸ばして聞く」ということをきびしくしつける教師が多かったのだが、その後、画一的なしつけなどが嫌がられるようになり、(よく言えば)リラックスして話を聞く子供が増えてきた。もっともこの点については、今の20代の人たちを担任したのは他でもない私たち40代・50代であるから、私たちに責任がないとは言えないのだが‥‥(^^;)
さて、教師の間にもこういった世代間の感覚の違いがあることは事実として認めなければならないだろうが、このことについてどんな対応をとっていけばよいのだろうか。
40代以上の私たちの側から見れば、「全く近頃の若い教師は、子供みたいな考え方しかできないのだから‥‥」などと考えがちだ。子供たちと友達のような口調でしゃべっている姿を見て「教師と子供の間にも節度ある態度が必要だ」などと言いたくもなる。
しかし、そういう考え方でよいのだろうか。子供と感覚が近いのは若い教師なのである。むしろ40代以上の人間の感覚が子供とかけ離れてしまったのかもしれない。
私などは「自分の子供の頃はよかった」という感覚を持ちがちである。(実際にそう思っているのだが‥‥)
ともすれば、それを子供の教育にも押しつけがちになる。生活科や総合的な学習の時間で行う学習活動も、「失われた自然や地域とのふれあい」を重視したくなるし、その中で「自分が昔やったこと」を再現したくなってしまう。(生活科や総合的な学習の時間を発想したのも私たちの世代だろうし)
その中にはたしかに良いものもあるだろうが、子供にとってはもちろん、若い教師にとっても、「何が何だかよくわからないもの」もあるかもしれない。
「今の子供たちは昔の子供とくらべてかわいそうな環境に育っている」というのが私の年代の見方かと思うが、コンピュータを自由に使いこなし、スポーツもばりばりやっている今の子供たちは幸せだという見方もできるだろう。子供の感覚で考えれば何もない貧しい時代に、鼻水を垂らしながら外で遊ぶしかなかった私たちの年代こそ「かわいそう」なのかもしれない‥‥(^^;)
今の子供たちや若い教師の感覚を全て肯定することもできないが、私たちの年代の感覚が世の中のスタンダードだと思ってしまうと、それこそ「世の中の感覚からズレた世代」になってしまうおそれがある。
そんなことを考えさせられた、このアンケートの結果であった。
<00.11.23>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ