プレゼント貧乏家族
「よしお君、お誕生日おめでとう。これはお父さんからのプレゼント!」「おばあちゃんからはこれよ」「お兄ちゃん、これは私から」‥‥という光景は多くの家庭で見られるのではないだろうか。
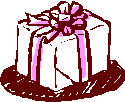
家族の人数が多いほど誕生日の数も多い。プレゼントをする人数も多いので、年間のプレゼント数およびそれにかかる経費も多くなる。こうやって大所帯の家族はプレゼントで貧乏になっていく‥‥。
これは半ば冗談だが、全くのデタラメとも言えないだろう。
仮に、祖父母・両親・子供3人の7人家族で、家族のそれぞれが別々にプレゼントをするとしたら、誕生日ごとに6つのプレゼントが贈られることになる。プレゼントの単価を安く見積もっても2千円、6個で1万2千円。それが7回なら年間に8万4千円になる。
家族の全員がお金をかけたプレゼントをするわけではないかもしれない。子供が紙で作った「肩たたき券」や似顔絵をあげることもあるし、おばあちゃんが手編みの手袋をプレゼントすることもあるだろう。
しかし、単価2千円以上のプレゼントも多いだろうから、1回の誕生日で1万2千円程度はかかると見ても間違いではないだろう。これにクリスマスやお年玉、父の日、母の日、敬老の日などのプレゼントを加えれば、この家族の年間プレゼント経費は10万円を超えるだろう。
これはかなりの金額である。家族の半月分の食費ぐらいにはなるだろう。
プレゼントをする側も、毎回高価なプレゼントをするのも大変なので、ある程度安いものを探さなければならないが、もらう側にしてみれば、あまり自分が欲しいと思っていないようなものをゴチャゴチャもらうということもあるだろう。
おじいちゃんやおばあちゃんが「この頃の子供が喜ぶ物がわからなくて‥‥」とこぼす話を聞くこともあるが、実際に、「これは喜んでもらえるだろう」と思ってあげたのに、孫はあまり喜ばないということもあるようだ。
気持ちが伝わればそれでよいということもあるだろうが、家の中のお金が、大して使われない品物に姿をかえていくのも不経済な話だ。
O・ヘンリーの短編「賢者の贈り物」は、若い夫婦が互いにプレゼントした金の時計鎖とべっこうの櫛が、結果的には役に立たなくなったけれど、二人の愛を深めたという名作だが、これもクリスマスに一度きりだったので感動的なのであって、年に数回もそんなことがあっては、たまったものではない(^^;)
むだをなくすには、お金をかけないプレゼントにすればよいだろうが、その度ごとに手作りの小物や自作の曲を作るのも大変である。
家族個々のお金は共有財産であると考えて、個人個人のプレゼント交換はやめて、ある程度高価なものを1個だけ、家計の中から支出して買うという方法もあるだろう。ちょっと味気ないが合理的ではある。実際にこの方法をとっている家庭もかなりあるかもしれない。国としてそういう経済の仕組みをとっていたところでは、その仕組みも崩壊してきたところも多いが‥‥。
<00.09.20>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ