指導のアクセント
タイトルが「指導のアクセント」になっているが、これは「アクセントの指導」の間違いではない。文字通り、「指導」という言葉のアクセントのことである(^^;)
この頃、「指導」を妙なアクセントで話す人が増えてきた。私の回りでも見かける(耳にする)し、テレビ・ラジオ等の放送でもときどき出てくる。
アクセントの細かいことについては後述するが、簡単にいうと「武士道」の「ぶ」をとったようなアクセントなのである。
「妙な」と表現したが、妙だと感じるのは、私の言語感覚である。したがって、私にとっては妙だと感じられるアクセントも、話す人にしてみれば、それが当たり前なのだろう。
問題は、私のアクセント感覚が正しいか、間違っているかということになる。
これについて、私は、ちょっと自信を持っている(^^;)
というのは、私が田舎育ちだからだ。
幼児の頃、まわりには標準語を話す人がいなかった。耳にしていたのは立派な方言ばかりであった。そのため、小学校に入学しても方言しかしゃべれない子供が多かったのである。
ちゃんとした標準語を話せるようにするために、学校では「方言を使わない運動」などという、今では非難の的になるようなことが普通に行われていた。「ことばカード」なるものを持たされて、方言を使うとカードに×印を付けられるのである。
方法の良し悪しはともかく、このおかげで標準語には気を遣うようになった。なにしろ普段自分がしゃべっているのとは別の言語である(^^;) ちゃんとした標準語を聞かないことには、どうしゃべったらよいのかもわからない。
そこで、心がけて聞いたのが、テレビやラジオのアナウンサーの話し方である。(今でもそうだが)ニュース番組が好きな私は、ニュースの内容だけでなく話し方にも興味をもって聞いていた。
当時のアナウンサーは、今よりもきちんとした話し方をしていたので、子供の頃の私が耳にしていたのは、かなり正確な標準語であったと思う。
そうやって耳で覚えたアクセントには(自分ではちゃんとしゃべれないにしても)かなり自信を持っているという次第である。
その私が、「おやっ?」と感じる「指導」のアクセントは、やはりおかしいのではないかと思ったのだ。
もちろん、日本語というのは全ての方言も含んでいるものなのだが、標準語というのはちゃんとした基準を持っているはずだ。標準語どおりにしゃべらなくてはいけないということはないが、日本全国を対象とする公的な性格を持つ放送では、アナウンサーは標準的なアクセントで話すべきだし、子供に日本語を指導する立場の教職員もあらたまって話すときには標準的なアクセントを使うべきであろう。
そこで、標準的なアクセントの基準をどこに求めるかということが問題になるのだが、私は「NHK日本語アクセント辞典」に頼ることにしている。
この辞典は、昭和18年に刊行されて以来、NHKのアナウンサーはもちろん、話し言葉に関わる人には「正しいアクセントの基準」として愛用されている。私が子供の頃に聞いたアナウンサーのアクセントも、これがもとになっているので、自分のアクセント感覚を確かめるには、これが一番である。
ちなみに、このアクセント辞典は、平成10年の春に4度目の大改訂が行われたので、現在の日本語の基準を最も正しくあらわしているといえるだろう。価格も税込みで3,990円と手頃なので、日本語に関わる職種の人は自分で1冊持っていてもよいだろう。
さて、本題に戻ろう。
このアクセント辞典で、「指導」のアクセントはどうなっているのだろうか。
実は、このように書かれていた。
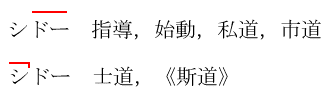
上に横線が引かれている部分が、その語のアクセントである。
この例だけでは、アクセント辞典の表記と、実際に発音するアクセントの関係がわかりにくいかもしれないので、下にいくつか例を示してみよう。
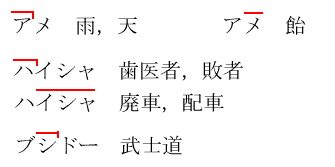
これを見ながら実際に声に出してみれば、アクセントの表記については理解していただけるのではないだろうか。
「指導」のアクセントに関しては、どうやら私のアクセント感覚の勝ちのようである(^^;)
勝ち負けがどうのこうのという問題ではないので、標準的でないアクセントで話す人を非難するということもできないのだが、近頃では「彼氏」を「枯死」としか聞こえないアクセントで話す「おバカ風日本語」も蔓延してきている。(専門家は『アクセントの平板化による日本語の乱れ』と呼ぶそうだ)
おかしな日本語がスタンダードにすり替わってしまわないように、アナウンサーや教師など、日本語の手本となるべき人間は、標準的なアクセントはどうなっているのかをきちんと知り、正しい話し方をすべきであろう。
例によって余談になるが‥‥(^^;)
私のアクセント感覚が標準語に近いのは、実は訳があった。
前述の「NHK日本語発音アクセント辞典」の後扉の裏側には「全日本アクセント分布図」という日本地図がついている。
標準語は、東京型のアクセントがもとになっているのだが、「ほとんど東京型」とされているのが「東京・埼玉・群馬・新潟南部・千葉の一部・神奈川・静岡・山梨・長野・岐阜・愛知・鳥取・岡山・広島・山口・島根東部」であり、「それにかなり似ている型」というのが「北海道・青森・秋田・山形東部・新潟北部」となっているのだ。
私の住む秋田は、発音はかなりズーズー弁であっても、アクセント的には東京型に近いのである。それで、標準的なアクセントにあまり違和感を持たないのかもしれない。
東京型アクセントとだいぶ違っている地域に育った人の場合は、標準的なアクセントそのものに対して、「妙な」感じを抱くのかもしれない。
<00.09.15>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ