市町村教育委員会も大変だ
法規(ほうき)はしょっちゅう使うものではないが、ゴミが出たときには役に立つという名言を聞いたことがある。
学校教育の場でも、表立って法規をふりかざすということはないのだが、実は、日々の教育活動も法規に則(のっと)って行われており、私たち教師も法規(法律・規則)に無関係ということはありえない。
若い教諭であれば、「法規は知りません」でも通用するかもしれないが、校長・教頭などの管理職や、教務主任・事務職員などの事務的な手続きに関わる職員は、ある程度、法規に関する知識は必要である。
たまに、教務主任の経験なしで、学級担任から教頭・校長になる人もいるが、なかには「そういう法規のことは事務の先生に任せているので、自分はほとんどわからない」という方もいるようだ。これはまずい。
教科等の学習指導には卓越した能力を持っていても、学校運営や事務処理に関する能力は別物である。
自動車を運転することはできても、自動車の構造がわからなければ、故障などの、いざというときの対応ができないだろう。法規を全くわからない教員は、それに似ている。
事務の先生は、それが仕事であるから給与や人事に関わる法規及び事務処理に詳しいのだが、管理職や教務主任であれば、事務の先生と同程度の法規の知識を持っていることが必要である。給与等に関しては事務の先生に負けないということは無理かもしれないが、その他の教育に関する法規については事務の先生以上の知識が必要である。それを「法規のことについては事務の先生にお任せ」ということでは、馬鹿にされるだけであろう。
さて、その法規についてであるが、私たちは法律の専門家ではないので、法規の条文を暗記しているということはない。ただ、必要に応じて、関係法規を参照できる力があればよいだろう。
そのときに使うのが法規集である。おそらく他の都道府県でも同種のものが発行されているだろうが、私の場合は秋田県版の「教育関係職員必携」という冊子を使っている。
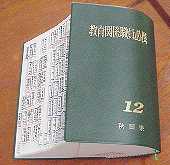
これには、全ての法規のおおもとになる「日本国憲法」をはじめとして、最近見直しが論議されている「教育基本法」(どこが悪くて改正しなければいけないのかわからないが)、「学校教育法」等から、県の条例まで、およそ教育に関係する法規のほとんどが収録されている。これを見れば、学校での時間割をどうするかとか、勤務時間や給与をどうするかなど、たいていのことがわかるようになっている。
さて、この法規集は2年に1回、新しい版が発行される。基本になる法が変わることは少ないのだが、その施行令や施行規則などはしょっちゅう改訂されているので、新しい法規を載せるには少なくても2年に1回は新版を出さないといけないのだ。
ちなみに、話題になった「学校評議員の設置」「職員会議校長主宰の明示」などは「学校教育法施行規則」の中に新たに加えられたものである。平成12年4月1日付で施行された法規(主に令や規則だが)にはかなり大きな変化がある。
さて、夏休みに平成12年版の「秋田県版教育関係職員必携」が届いたので、いつものように必要な部分にタックインデックスをつけたり、条文にカラーマーカーで線を引いたりした。すると驚くべきことに気がついた。
と、ここまでが「前ふり」である。ちょっと前ふりが長すぎたきらいもあるが‥‥(^^;)
驚くべきことというのは、県で出している条例等の中でなくなったものが、かなりあったということである。
タックインデックスをつけるときは、これまで使っていた「教育関係職員必携」(2年前のもの)を参考にしながら行う。作業も楽だし、新たに改訂された部分も比較することでわかりやすいので、効果的な作業である。
そうやって作業をやってきたら、新しい「教育関係職員必携」には、「市町村立小中学校管理規則準則」がなくなっていたのを見つけたのである。
このことについて詳しく書く前に、私たちのような市町村立小中学校に勤務する教員の身分について確認しておこう。
私のように町立小学校の教員の場合は、基本的には町の職員である。ただし、町役場の職員のように、特定の町に採用されたわけではないので(いくつもの市町村の学校を転任するということ)、任命権は県にあり、給与も町の予算からではなく、県の予算から支出されている。これを県費負担職員という。さらにこの給与の2分の1を「義務教育費国庫負担法」によって、国が負担している。つまり、私たちは給与を国から半分、県から半分もらっている町の職員なのである。
給与はともかく、立場としては町の職員であるから、学校運営や勤務については、町の教育委員会が管理者となる。その基本的な事項を書いたのが「○○町(あるいは市・村)立小中学校管理規則」である。
「管理規則」などというと厳めしい感じがするが、具体的には「夏休みは○○日から○○日までとする」というようなことが書かれてある。夏休みなどは学校が勝手に決めるものではなく、町の規則に従っているのだ。
この「○○町立小中学校管理規則」も、最終的に制定するのは町教育委員会であるが、全ての条文を町で作るのではなく、県教育委員会で作った原型を、ほとんどそのまま使うのが普通だった。この原型になるのが、県教育委員会で出した「市町村立小中学校管理規則準則」である。早い話が、なかみはそのままで、名称だけ「○○町立学校管理規則」に替えて制定するという仕組みである。
ところが、前述したように、原型となるはずの「市町村立小中学校管理規則準則」を、県教育委員会が出さなくなってしまったのだ。(他の都道府県でも同じはずである)
これは、都道府県教育委員会がさぼったということではなく、学校教育法施行令が変わったためである。例えば、長期休業や学期等に関する部分である学校教育法施行令第29条は、これまで「学期は都道府県の教育委員会が定める」となっていた。ところが新しい施行令では「市町村の教育委員会が定める」と変わった。
つまり、町の教育委員会が「うちの町の学校では、3学期制ではなく、2学期制にしよう」と決めれば、それでもよいということになったのである。そのために、県教育委員会で一律に規定していた「市町村立小中学校管理規則準則」の存在価値がなくなり消えてしまったという次第である。
「市町村立小中学校管理規則準則」が消えても、今すぐにトラブルがあるというわけではない。これまでの「市町村立小中学校管理規則準則」をもとにして作られた「○○町立小中学校管理規則」が現在も効力を発揮しているので、学校運営に支障はない。また細かい手直し程度であれば小さな町の教育委員会であっても難しいことではないだろうから、平成12年度版「学校管理規則」も制定できるだろう。
しかし、前述の学校教育法施行令の改訂の趣旨は、地域の特色を生かした創造的な教育を可能にしたというところにある。そのために県で一律に決めてしまうやり方をなくしたのである。したがって(すぐには無理であっても)市町村教育委員会ごとに「学校管理規則」を大胆に改訂していくことが必要とされる。
規模の大きい市などの教育委員会であれば、事務局の人数も多いだろうし、学校教育に造詣の深い人材もいるだろうから、専門の委員会等を設置して改訂を検討できるだろうが、小さな町村ではかなり困難な作業になるかもしれない。この文章のタイトルを「市町村教育委員会も大変だ」としたのは、そういう意味である。
しかし、大変だからといって、今後何年間も、古い「管理規則」をちょっとずつ手直ししていくだけでは、学校教育法施行令の改訂の趣旨に沿っているとはいえない。教育長さんの指導力を生かして、前向きな改訂を期待したいものだ。
「市町村教育委員会も大変だ」というのには、もう1つ理由がある。
今回の改訂で消えたのは「市町村立小中学校管理規則準則」だけではないのだ。例えば「公立小中学校における修学旅行の基準準則及び計画・実施上の留意点について」なども消えているのである。
これも本来は「準則」であるので、これをもとに市町村教育委員会が「修学旅行の基準」を制定しなければならないのだが、それを省略して、市町村の「基準」を制定せずに、県の「準則」を流用していたところもあるようだ。(市町村の「例規集」に載っていなければ、制定されていないことになる)
県の「基準準則」がなくなった時点において、もしこの「基準」がない場合は、すぐに制定しなければ、一切の基準がないという状態になる。
市町村の教育委員会では、都道府県で出した「準則」で消えたものを洗い出し、それに対応する「規則」や「基準」が未制定の場合には、即刻制定しないとまずいことになりそうだ。
こういった作業も急いで行わなければならないので、ほんとに「市町村教育委員会も大変だ」と思った次第である(^^;)
例によって余談になるが‥‥
この文章を読み返してみると、なんだか知ったかぶりのようで嫌な感じもする。自分ではそういう気はないのだが、感じが悪かったら申し訳ない。ただ、こういう知識は必要なことだと思うし、こういう知識がない(あるいは知識を得ようとしない)学校の管理職・教務主任や教育長・教育委員・教育委員会事務局は、ちょっと使い物にならないのではないかと思う。
<00.09.10>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ