35時間で割り切れない
新教育課程の時間割編成の問題
これまで、学校の時間割といえば、4月のはじめに担任の先生から渡されて、それを1年間使うのが普通だった。
担任の先生も、1年間子供たちが使う時間割なので、デザインなども工夫したきれいなものを作り、それをもらった子供たちも自宅の自分の机の前に大事に貼っておくというのが、普通に見られた光景である。私が子供の頃もそうだったし、教師になってからもずっとそうやってきた。
ところが、これからは(遅くても平成14年度から、はやいところでは今年度から)場合によっては毎週の終わりに「はい!これが来週の時間割ですよ」と手渡されることになりそうだ。
学校によって違いがあるのだが、毎週変わる時間割とまではいかなくても、月に一度は時間割が変わるということになる。
今回は、そのことについて述べたい。なお、このホームページをご覧くださる方は教育関係者ばかりではないので、各学年毎の詳しい内容についてはある程度省略する。(全部の事例について詳説すると膨大な量になるので‥‥)
なるべくシンプルに書こうとは思うが、それでもかなりくどい内容になりそうなので、ご了承いただきたい(^^;)
まず、これまでの時間割はどうだったかというと、下のようであった。(小学校の場合)
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
1
|
国語
|
国語
|
国語
|
国語
|
国語
|
国語
|
2
|
算数
|
算数
|
算数
|
算数
|
算数
|
道徳
|
3
|
社会
|
社会
|
社会
|
音楽
|
音楽
|
|
4
|
理科
|
理科
|
理科
|
図工
|
図工
|
|
5
|
体育
|
体育
|
体育
|
家庭
|
家庭
|
|
6
|
特活
|
特活
|
|
|
|
|
これは5年生・6年生の例である。この表での授業時数の1単位時間は45分となっている。なお特活(特別活動)のうちの1時間はクラブ活動となっていた。
教科の時間数がわかりやすいように、上の例では、国語を全部1時間目に並べたりしているが、実際には様々な要素を考えて教科を配置して作成するわけである。(土曜日に3時間を割り当てている学校もある)
上のように1年間を通して同じ時間割でやっていくことができたのは、学習指導要領によって、各学年の年間授業時数が次のように定められていたからである。
現行(平成4年度〜平成13年度)の学習指導要領
(正確には学校教育法施行規則)が定めた各教科の授業時数
区分
|
各教科の授業時数
|
道
徳
の
授
業
時
数
|
特
別
活
動
の
授
業
時
数
|
総
授
業
時
数
|
国
語
|
社
会
|
算
数
|
理
科
|
生
活
|
音
楽
|
図
画
工
作
|
家
庭
|
体
育
|
第1学年
|
306(9)
|
−
|
136(4)
|
−
|
102(3)
|
68(2)
|
68(2)
|
−
|
102(3)
|
34
|
34
|
850(25)
|
第2学年
|
315(9)
|
−
|
175(5)
|
−
|
105(3)
|
70(2)
|
70(2)
|
−
|
105(3)
|
35
|
35
|
910(26)
|
第3学年
|
280(8)
|
105(3)
|
175(5)
|
105(3)
|
−
|
70(2)
|
70(2)
|
−
|
105(3)
|
35
|
35
|
980(28)
|
第4学年
|
280(8)
|
105(3)
|
175(5)
|
105(3)
|
−
|
70(2)
|
70(2)
|
−
|
105(3)
|
35
|
35
|
1015(29)
|
第5学年
|
210(6)
|
105(3)
|
175(5)
|
105(3)
|
−
|
70(2)
|
70(2)
|
70(2)
|
105(3)
|
35
|
35
|
1015(29)
|
第6学年
|
210(6)
|
105(3)
|
175(5)
|
105(3)
|
−
|
70(2)
|
70(2)
|
70(2)
|
105(3)
|
35
|
35
|
1015(29)
|
数字だけが並んだ表なので見にくいのだが、ていねいに見ていくといろんなことがわかる。
まず、上の表で黄色に色づけした部分をご覧いただきたい。これは6年生の国語科の授業時数である。年間の総時数が210時間(正確には45分を1単位時間とする210単位時間)で、( )内の6という数字は、1週当たり6単位時間の授業を行うということである。
6年生の欄の右端には年間の総授業時数が書かれており、これが1015単位時間になっている。週当たりには29時間である。
1015÷29の計算をしていただければ分かるが、この表では、1年間の授業週数を35としている。児童が出校する日は、約40週ほどあるのだが、行事等で教科等の授業を行わない日もあるので、実際に授業を行うのは、ほぼ35週である。1年生の場合、入学式後の約1週間は、登下校の指導など学校への適応指導を行う時期があるので、他の学年より1週分少なく、34週として数えている。
このように、どの教科も、年間の授業時数が「35で割り切れる数」に定められていたので、1年間同じ時間割で進行することができたわけである。
ところが、新しい学習指導要領が完全実施される平成14年度からは、そういうわけにいかなくなった。
理由は2つある。
1つは、全ての土曜日が休みになったことである。
これによって、週当たりの総授業時数を(4年生以上で)29単位時間としていたものが実施不可能になる。少なくても全体で週当たり2時間は授業を削減しなければならない。
実際に、後述する新学習指導要領では、2時間削減して、週当たり27時間となっている。(土曜日に3時間の授業を行っていた学校では、月〜金の中で授業時数を1時間増やさないといけないことになった)
2つめの理由は、「総合的な学習の時間」が新設されたことである。
私もこれまで「うんちく講座」の中でこのことには触れているのだが、「総合的な学習の時間」の趣旨には大いに賛同できるし、私たちも積極的に取り組んでいかなければならないのだが、授業時間を編成していく場合には、かなり難しい課題を与えられたことになった。
「総合的な学習の時間」は、小学校3年生以上に設置され、3・4年生は105時間(週当たりにすると3時間)、5・6年生では110時間となっている。5・6年生では35週で割り切れない数になっている。
土曜日の授業がなくなり総時数が不足になったところに、新しい教科が入ってくるわけだから、これまであった教科の時数もそのままではいけないことになる。
今回の学習指導要領改訂では、難しすぎる内容を削減し、基礎・基本の確実な定着を図るということにも重点が置かれているので、各教科の教育内容が縮減されている。
その結果、例えばこれまで5年生の社会科であれば、105単位時間で指導していたものが、新教育課程では90時間で指導可能になった。
そこで定められたのが、下の表の授業時数である。(平成14年度から完全実施される学習指導要領)
区分
|
各教科の授業時数
|
道
徳
の
授
業
時
数
|
特
別
活
動
の
授
業
時
数
|
総合
的な
学習
の時
間の
授業
時数
|
総
授
業
時
数
|
国
語
|
社
会
|
算
数
|
理
科
|
生
活
|
音
楽
|
図
画
工
作
|
家
庭
|
体
育
|
第1学年
|
272
|
−
|
114
|
−
|
102
|
68
|
68
|
−
|
90
|
34
|
34
|
−
|
782
|
第2学年
|
280
|
−
|
155
|
−
|
105
|
70
|
70
|
−
|
90
|
35
|
35
|
−
|
840
|
第3学年
|
235
|
70
|
150
|
70
|
−
|
60
|
60
|
−
|
90
|
35
|
35
|
105
|
910
|
第4学年
|
235
|
85
|
150
|
90
|
−
|
60
|
60
|
−
|
90
|
35
|
35
|
105
|
945
|
第5学年
|
180
|
90
|
150
|
95
|
−
|
50
|
50
|
60
|
90
|
35
|
35
|
110
|
945
|
第6学年
|
175
|
100
|
150
|
95
|
−
|
50
|
50
|
55
|
90
|
35
|
35
|
110
|
945
|
この表で水色になっている部分が、35で割り切れない時間数になった授業である。
あくまでも「1年間、変更のない時間割にする」ということにこだわるのであれば、これまで週に3時間(年間では105時間)だった教科を、週に2時間(年間では70時間)にすればよいのだが、そうするには教科の教育内容を3分の2にしなければならないことになり、これは実現不可能だったのだろう。
その結果、上の表のような授業時数に落ち着いたのだろうが、これまで繰り返し書いたように、この授業時数では、1年間、同じ時間割で通すことができない。
そこで、4つの方法が考えられている。
1つ目は「平準化」という方法である。
例えば、5年生の授業時数を見てみると、道徳と特別活動を除いては、35で割り切れる授業時数が1つもない。
各教科等の時数を35で割って、さらに余りの数を出してみると、次の表のようになる。
教科
|
時数
|
35が
|
あまり
|
国語
|
180
|
5コマ
|
5
|
社会
|
90
|
2コマ
|
20
|
算数
|
150
|
4コマ
|
10
|
理科
|
95
|
2コマ
|
25
|
音楽
|
50
|
1コマ
|
15
|
図工
|
50
|
1コマ
|
15
|
家庭
|
60
|
1コマ
|
25
|
体育
|
90
|
2コマ
|
20
|
道徳
|
35
|
1コマ
|
なし
|
特活
|
35
|
1コマ
|
なし
|
総合
|
110
|
3コマ
|
5
|
合計
|
945
|
23コマ
|
140
|
あまりを35で割ると
|
4コマ
|
ここで「35が」という欄に書かれた「○コマ」という数字は、通年で時間割に位置づけることができる時間数である。
例えば、国語の場合、総時数180時間のうち、35×5の175時間は時間割上に固定できることになる。しかし残りの5時間は適当な時間を探して実施しなければならないということになる。
そうやって、ちゃんと位置づけられるのが、上の表のように合計23コマ。1週間の授業時数は27コマなので、各教科の余り時数を足すと140時間となり、これを35で割るとちょうど4コマになるので、合計27コマとなり計算が合う。
そこで各教科の余り時数を見てみると、例えば上の表の算数(10)と理科(25)を組み合わせれば、きっちり35になるように、余り時数は「5・10・15・20・25」という数になっている。
それらの教科の余り時数をうまく組み合わせて作った時間割が下の表である。
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
1
|
国 語
|
国 語
|
国 語
|
国 語
|
国 語
|
2
|
算 数
|
算 数
|
算 数
|
算 数
|
図 工
|
3
|
社 会
|
社 会
|
理 科
|
理 科
|
音 楽
|
4
|
体 育
|
体 育
|
家 庭
|
道 徳
|
特 活
|
5
|
総 合
|
総 合
|
総 合
|
算・理
|
社・音
|
6
|
図・体
|
国家総
|
|
|
|
1つの枠に1教科が収まっているところは、1年間同じ時間割でやれる部分。下段の4時間分(灰色になっている部分)は、複数の教科を組み合わせて行う部分である。
ただ、複数の教科を組み合わせて行うといっても、組み合わせの比率がそれぞれ異なるので、微妙な調整が必要になってくる。それを図示したのが次の表である。
学期
|
1学期
|
2学期
|
3学期
|
余り時数
(学年計)
|
月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
1月
|
2月
|
3月
|
週数
|
2
|
4
|
4
|
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
2
|
国・総・家
(週各1時間)
|
国語
|
○
|
|
|
|
|
|
★
|
|
|
|
☆
|
5
|
総合
|
|
|
|
○
|
|
|
★
|
|
|
|
☆
|
5
|
家庭
|
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
|
25
|
算・理
(週各1時間)
|
算数
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
|
|
|
○
|
10
|
理科
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
25
|
社・音
(週各1時間)
|
社会
|
○
|
○
|
|
*
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
20
|
音楽
|
|
|
○
|
*
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
15
|
図・体
(週各1時間)
|
図工
|
|
|
○
|
#
|
○
|
|
|
○
|
|
○
|
|
15
|
体育
|
○
|
○
|
|
#
|
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
20
|
(注)★‥‥11月の4週のうち、2週を国語、2週を総合にあてる。
☆‥‥3月の2週のうち、1週を国語、1週を総合にあてる。
*‥‥7月の2週のうち、1週を社会、1週を音楽にあてる。
#‥‥7月の2週のうち、1週を図工、1週を体育にあてる。
かなり難しい‥‥(^^;)
この方法だと、毎月、時間割を発行しなければならないが、1ヶ月の間は固定した時間割で授業を進められることになる。またある程度は各教科の進度のバランスがとれているので、理科などのように季節に関わった学習をする場合など、実際の気候と大きなズレが生じることはない。
2つ目は「3期制」という方法である。
前に述べた半端な「余り時間」は、「5・10・15・20・25」というように全て5の倍数になっているので、1年間の35週を「15週・10週・10週」という3期に分けて、そのまとまりごとに時数を配分するという方法である。
例によって5年生の時間割は次の表のようになる。
|
国語
|
社会
|
算数
|
理科
|
音楽
|
図工
|
家庭
|
体育
|
道徳
|
特活
|
総合
|
標準時数
|
180
|
90
|
150
|
95
|
50
|
50
|
60
|
90
|
35
|
35
|
110
|
週
時
数
|
15週
|
6
|
2
|
4
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
2
|
10週
|
5
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
3
|
1
|
1
|
4
|
10週
|
4
|
3
|
5
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
4
|
この方法だと、1年間に3種類の時間割を作成するだけで間に合うので、月ごとの細かい時間調整は不要になる。
ただ、上の表を見ても分かるように、教科によってはある時期にかたよって実施されることもあるので、教科書の学期別の単元配当数とのズレが生じる。季節に関係した内容の場合など、学習する時期と実際の季節が合わなくなることもある。
また、週の分け方が、従来の1・2・3学期とは合わないので、学期の途中で時間割が変わるということになる。
3つ目は総合的な学習を中心とした時間割編成の方法である。
「総合的な学習の時間」は、「学校が創意工夫を生かして」行う性質のもののため、他教科のように毎週きまった時間数で実施する形態にならないことも考えられる。(むしろそのような場合が多いだろう)
ある一定の期間、重点的に「総合的な学習の時間」を行うとすれば、授業時間の配当もそれに応じて変更しなければならない。その時期になって急に時間割変更を行ったのでは、年間の総時数を標準時数どおりに実施するのが難しいので、年度当初に年間を見通して、どの時期に「総合」をどのぐらい行うか、他の教科の時数はどうするかという計画を立てる。それがこの方法である。
文章で説明しても分かりにくいので、下の表をご覧いただきたい。
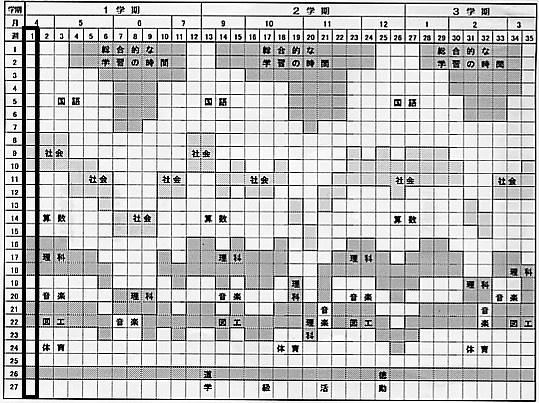
これは4年生の例である。例えば4月の第1週の時間配分は左端の列を縦に見ていけばわかることになる。(黒い太線で囲まれた部分)
この方法が、今回の教育課程改訂の本来の趣旨にふさわしいものかもしれないが、時間割は毎週のようにめまぐるしく変わるし、学年間の調整をとるのもきわめて難しいという問題点もある。
4つ目は45分という1単位時間にこだわらない方法である。
これまでの3つの方法では、授業の1単位時間を45分として扱っているが、4つ目の方法では、15分授業・30分授業・60分授業などという柔軟な時間設定で考える。
例えば、60分授業を3コマ実施すれば、60×3=180となり、45分の授業を4コマ行ったのと同じ結果になる。
具体例を図示したりするのは、かなり面倒になるが、要するに45分に1回チャイムが鳴るといった従来の学校の時間進行をやめ、教科によって15分単位のユニットをいくつか組み合わせた時間設定にするという方法である。
この方法だと、うまく組みさえすれば、1年間同じ時間割で進行することも可能である。
これが「35時間で割り切れない」教科時間数をうまく時間割に組む方法である。
これだけでも「わけが分からないほど難しい」と感じるかもしれないが、実は、これだけなら何も難しくはない。
小学生程度の頭脳でも、半日もあれば、どの方法でも時間割を組むことができるだろう。普通の大人なら1時間もかからないで時数上だけなら間違いのない時間割を組むことができるはずである。
ところが、現実の学校現場ではそんなに簡単な問題ではない。
例えば、4年生に3つの学級があり、それぞれの担任に時間割を組ませたとする。
単一の学級で見れば全く問題のない時間割が組めたとしても、その3つの学級担任が組んだ時間割が、全く同じものだったとしたらどうだろうか?
こうなると、実際の学校現場では、これは「全く使えない時間割」ということになるのである。
学校には、体育館・音楽室・理科室・図工室・家庭科室など、いわゆる特別教室と呼ばれるものがある。もし、3つの学級が同じ時間(例えば月曜日の1校時)に音楽をやるという時間割を組んだとすれば、その時間割は「ダメな時間割」なのである。
このように、それぞれの学級担任が好き勝手に時間割を組むと、特別教室の使用に衝突が起きる。
これを調整するために、最初に「特別教室使用割当」を組む担当の教師がいる。多くの学校では教務主任がそれを担当するだろうが、学校によっては研究主任が担当しているところもあるかもしれない。
私も、教務主任として4年、研究主任として2年、この仕事を担当した。
1学年に1学級しかないような小規模校では、それほど問題もないが、学年の学級数が3つ以上になるところでは、特別教室使用割当を組むのがかなり難しい。
例えば、現行の学習指導要領では、週当たりの体育の時間が3時間である。1週間の授業時間数が29単位時間だから、10学級ある学校だと体育館の使用割当がパンクする。新教育課程では1週の授業時間数が27単位時間だからさらに厳しくなる。
1学年の学級数が3であれば、学校全体では18学級になるから、単一学級で体育館を使用するのは無理ということになる。そこで、複数の学級で合同授業をやるような方法でなんとかクリアしているのである。
仮に体育館の使用割当が、そのような方法でうまくできたとしても、音楽室や理科室などの特別教室使用割当と照らし合わせた場合、同じ学級の同じ時間に2つ以上の特別教室が割り当たっていたとすれば、これもエラーである。
また、そういうエラーがなくても、1つの学級の時間割を見た場合、1日に体育が3時間もあったりしてもまずい。それほど極端なことはなくても、1日の時間割が「体育・音楽・図工・図工・家庭・家庭」などのように、いわゆる実技教科ばかりになるような時間割も好ましくない。
更に、多くの学校で行われている交換授業にも配慮しなければならない。交換授業というのは、担任どうしが教科を交換して授業を行うというもので、具体的には、1組の担任が2組に音楽を指導する時間に、2組の担任が1組に体育を指導するというような方法だ。
基本的に小学校の教師は全ての教科の指導ができることにはなっているが、個人的には教科の得手不得手というものもある。あまりよい例ではないかもしれないが、音楽の指導は得意だけれども身体を動かすのは辛くなってきたという高齢の女性教師と、スポーツは得意だがピアノは苦手という若い男性教師が同じ学年を担当したような場合、音楽と体育の授業の担任を交換するというのは、授業を受ける子供にとっても利点がある。
このような場合に、1組の体育館使用と2組の音楽室使用を同じ時間に位置づけなければ、交換授業はできないことになる。
以上のようなたくさんの要素を全て満たして、エラーのない時間割(特別教室使用割)を組むのは、とても難しいのだ。前にも書いたように、私も過去に6年間、この作業を体験したが、1学年の学級数が3以上の学校では、必死になって考えても、完璧なものを作るのに数日を費やした。
それでも、年に1回の作業であったから、他の仕事を放っておいて、この仕事にだけ集中し、2・3日で仕上げるということができたのだが、こんな難しい仕事を毎月、あるいは毎週やらなければならないということになると、教務主任(研究主任)は他の仕事ができないような状態になるだろう。
(実際には毎週やらなくても、10数パターンの組み合わせを作れば用が足りるかもしれないが、それにしても10数年分の仕事をやらなくてはいけない)
今回の新学習指導要領を作った方たちは、当然、現場のこのような状況も知っているとは思うのだが、これからは時間割編成を担当する教務主任(研究主任)に、かなり頭のよい人を置かないと大変なようだ(^^;)
また、時間割編成の実務作業は教務主任等が行うことになるが、これまでのように35で割り切れる比較的簡単な時間割編成であれば、教務主任が「例年通りの作業」ということで、自分だけの判断で作業を進められるのだが、今回のように「学校全体としての教育のあり方をどうするか」という大きなビジョンが時間割編成に影響するようになると、これまで以上に校長の企画力・指導力が必要になってくるだろう。
教職員全体で十分に話し合い、その総意に基づいて決めるというのもよいのだが、それではいつまでたってもまとまらないということもある。この教育課程編成については、「こういう方針でやっていきたい」という校長の考えが明確に出されなければ、学校が動いていかないということにもなりかねない。
いずれにせよ、今回の教育課程改訂によって、学校の方向を決める校長も、時間割編成等を進める教務主任も、大きな責任を負うことになり、その存在がいっそう重要となった。十分に勉強し必死に考えるという仕事を避けることができなくなったのである。そうしないと平成14年度からの学校が活動停止してしまう。学校現場に大きな刺激を与えたという意味では興味深い改訂であると思う。(大きな宿題も与えられたことになるが)
ただ、ここまで何度も書いたように、35で割り切れない授業時間数で時間割編成をするのは大変に難しく、時間割編成者が超人的な能力を発揮しなくては実現できないというのは事実である。
紙の上の数字だけではわりと簡単に帳尻を合わせることはできても、場所と時間、さらに子供の1日の学習進行過程といった、3次元・4次元・5次元の配慮までしないと時間割は作られないのだということを、今回の新教育課程を作成する際に、どの程度まで理解していたかということについては若干疑問も残る。
約10年たてば、次の学習指導要領が発表され教育課程が改訂される。
10年後、もっと時間割編成が複雑になるような教育課程になるのか、あるいはもとのようなすっきりした教育課程に戻るのか、現場の反応も含めて、注目したいと思っている。
やはり、超「長文」になってしまいました。スミマセン(^^;)
<00.04.29>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ