円周率3騒動
私のホームページの掲示板「千客万来ルーム」でも、以前に話題になったことなのだが、ここでもう一度まとめてみたい。
どうも某テレビ局の朝のニュースワイドショーが発端になったようなのだが、3月頃に「小学校の新しい教育課程では、円周率を『3』として教えるのだそうだ」という話が広まった。
私もちょうどその番組を見ていたので、「へえー!そうなんだ!!」と思ってしまった。職場に行ってみても「今度の新しい学習指導要領では円周率を『3』として扱うんですってね」というような話が出ていた。
私のところの掲示板に限らず、インターネット上でもそのことが話題になっているようで、掲示板で賛否両論が交わされたり、個人のホームページでそのことについて意見を述べているところも多いようだ。(検索エンジン等で「算数・円周率」をキーワードにして探してみれば、かなりの数のページが見つかる)
私も最初は、「これまで3.14として教えてきた円周率を、単純に3として教えてもいいのかな」などと思ったくちである。
ただ、生来の(^^;)疑い深さもあり、「それってホントかな?」と思って、いろいろ調べてみた。
その結果、わかったのは、その「円周率が3になる」という話は、全くのデマであるということだった(^^;)
私が、そのデマを信じてしまったのは、3つの不勉強が原因になっていた。以下、そのことについて述べてみたい。
1つ目の不勉強は、2002年(平成14年)から完全実施される「小学校学習指導要領」をきちんと読んでいなかったということであった。
新しい教育課程では、これまでなかった「総合的な学習の時間」などが新設されるなど、変更の主な部分については、いろいろと聞いたり読んだりはしていたが、その「おおもと」になる「小学校学習指導要領」の本文をきちんと読んでいなかったのである。
したがって、自分に自信がないものだから、マスコミの報道を鵜呑みにしてしまった。これが1番目の間違いである。
2つ目の不勉強は、その学習指導要領の「算数・第5学年」の本文中にある、円周率に関した部分の、「3を用いて処理」の部分(確かにそう書いてある)だけにしか着目しないニュースの報道を、「それが学習指導要領の主旨である」というように受け取ってしまったことである。
実は、小学校5年生の算数の学習指導要領の全文をきちんと読めば、文部省が言いたいのはそうではないということがすぐにわかるのであるが、本文全体を正確に把握していなかったので、一部の表現だけを見て、それが全てであるようなとらえ方をした報道を信じてしまったのだ。
まさに文字通り「木を見て、森を見ない」状態だったわけである。これが2番目の間違いであった。
なお、学習指導要領で「3を用いて処理」するという意味がどういうことであるかは、後述する。
3つ目の不勉強は、現行の学習指導要領(平成元年3月15日改訂、平成4年度より完全実施)にも、新学習指導要領(平成10年12月14日改訂、平成14年度より完全実施)にある「3を用いて処理」と全く同じ文章があることを確認しなかった点である。
例のニュース番組では、「今度から実施される新しい学習指導要領では、円周率を『3』として指導することになりました」というような扱い方をしていたようだが、なんのことはない、現在使っている学習指導要領にも「目的に応じて3を用いて処理」という同じ表現があるのである。けして、新しい学習指導要領になったから、そのように変わったということではない。
今、実際に使っている学習指導要領そのものをも、きちんと把握していなかったというのが、3番目の間違いであった。
では、どうして「今度から、円周率は『3』になる」というような勘違いが生まれたのだろうか。これには少々事情がある。
円周率が出てくるのは、小学校5年生の学習である。
この学年では、少数の乗除計算を指導することになっている。(少数自体および少数の加減計算は4年生で出てくる)
これまで(現行)の学習指導要領では、小数点以下の桁数が何桁にもなる計算を行わせていたのだが、これは小学校5年生にとっては難しいという実態もあり、新しい学習指導要領の改訂の方針が「難しすぎたものをなくす」ということもあって、新学習指導要領では「少数の乗除計算では、1/10の位までの計算を取り扱うものとする」というように改められたのだった。
このことは、小学校学習指導要領、第2章「各教科」、第3節「算数」の「第5学年」の中の「3.内容の取扱い」の(2)の部分に書かれてある。
これに沿えば、小数点以下第2位まである「3.14」という数字は、「1/10の位」を超えているため、もし原則に合わせるとしたら「3.1」という数値になってしまう。
しかし、「3.内容の取扱い」の(4)には、「(前略)円周率としては3.14を用いるが、目的に応じて3を用いて処理できるよう配慮するものとする」というように書かれている。
つまり、小学5年生では、小数の乗除計算では小数点以下1桁までの計算しか扱わないようになったが、円周率だけは例外的に小数点以下2桁まである「3.14」を用いるのだというのが、新学習指導要領の本来の意味である。
このあたりを短絡的にとらえて、「5年生では小数点以下1位までの計算しかしない」ということと、「(円周率は)『目的に応じて3を用いて処理』」ということだけに着目したために、「円周率を3として教えることになった」と勘違いしたのであろう。
現行の学習指導要領に沿った指導でも「目的に応じて3を用いて処理」ということは行っているのだから、このことについての変化は全くない。ただ、小数の乗除計算が「小数点以下1桁まで」と変わったということが、この勘違いの原因になっているのかもしれない(^^;)
問題になるのが「目的に応じて3を用いて処理できるよう」ということである。(くどいようだが、これは新学習指導要領にも、現行の学習指導要領にも書かれている)
この「目的に応じて」ということの具体例として、文部省発行の「指導書」(新要領では「解説」と呼ばれている)には、「円周の長さや円の面積の見積りをするなど」と書かれている。
例えば、運動場に直径10mの円をひき、その円周を走ったら何m走ることになるかといった問題。(実際に運動場にランニングコースなどを作るときには必要になる発想である)
この場合、最初から「3.14」という数値を使うと、小数の計算になってしまうので、小数点の位置をうまくつけることができなければ「3.14m」とか「314m」などという的はずれな答えになってしまう可能性もある。
その際に、「3.14」ではなく「約3」という数値を用いれば「約30m」という答がすぐに出てくる。こうやって見積りを立てておいてから、実際に細かい数の計算をしたほうが間違いは少ないし、素速く見積りを立てるという能力が身につくわけである。(この例では直径を10mとしたのでわかりやすいが、直径が55mなどの場合には、3.14をかけるよりも、3をかけるという計算のほうが見積りをする場合に合理的であることがわかるだろう)
円の面積の場合も同じである。円周率の3.14という数値は、実測した結果求められたもので(円に内接するn角形のnの数値を増やしていくことで計算上でも求められるが小学生には無理な計算である)小学生が自分の力で算出できるようなものではない。
あくまでも「円周率は3.14ですよ!」と言って覚えさせるしかない数値である。
しかし「約3」という数値ならば、小学生でも次のような方法で見つける(考え出す)ことができる。
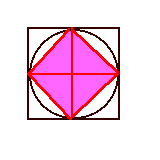
この図で、円に外接する大きな正方形の1辺の長さを「2」とする。
すると、この正方形の面積は「4」となる。
ここで、円に内接する小さな正方形の面積を考えると、上の図から見てもわかるとおり、大きな正方形の半分であるから、面積は「2」ということになる。
この円の面積は、図から判断すると、ほぼ「大きな正方形と小さな正方形の中間」ということになる。したがって「約3」という数値を導き出すことができる。
円周の長さも、この正方形をもっと辺の数の多い正多角形にしていくことで、その正多角形(正n角形)をn等分した二等辺三角形の集まりと考えることができる。その場合、円の面積は「底辺(円周)x高さ÷2」で求められることになる。正多角形の角数を増やすことで二等辺三角形の「高さ」は、限りなく円の半径に近づくことになるので、円の面積を「約3」とすれば、円周の長さも「直径の約3倍」ということになる。
ちょっとくどい説明になってしまったが、これが「目的に応じて」(見積りをする)という具体的な事例である。
こういう場合には、教師が「円周率は、3.14ですよ」と教え込むよりも、子供が「円の面積や円周を求める場合に必要な数は『約3』なんだな」と自分で見つけだすことのほうが大事なのだということがおわかりだろう。
そして、こういう学習活動を行うことで、素速く、しかも大きな間違いがなく、見積りをする能力も身につくのである。
ただ、「運動会などで正確に1周100mのコースを作るには」というような場面で、「約3」では不十分だという問題も出てくるので、そのときに「もっと詳しくいうと約3.14なのですよ」と指導するというかたちでよいと思う。
さて、小学生レベルの算数の話が長くなってしまったが(^^;) 私が今回気になったのは、実は円周率がどうのこうのということではない。
実は、「プロの教師うんぬん」などと言っている私自身が、マスコミの報道程度で簡単に影響されてしまうアマチュアレベルの知識しかなかったということである。
例のニュース番組(の誤報)によって、世間の人の多くは、「新しい小学校の算数の指導では、円周率が3になる」と思いこんでいるのではないかと思う。
私が今回、検索してみたら、ホームページや掲示板にそのようなことを書いている人が多くいた。中には「だから文部省の教育行政は‥‥」というようなことを書いている例もあったが、これは大きな勘違いで、書いた人も真実を知ったら赤面するだろう(^^;)
ただ、現場の教師の中にも、世間一般の人のレベルで新学習指導要領を認識している人も多いのではないだろうか。
もし、その程度の理解のまま、PTAの懇談会などに臨み、保護者から「今度は小学校で円周率を3として教えるんだそうですね」などと言われたときに、「ええ、そうなんですよ!」などと言ってしまったら、これは赤っ恥である(^^;)
そうではなくて、「いいえ、あれは『○ざましテレビ』でいいかげんなことを言っているだけで、実はこうなんですよ」と説明できるようでなくてはいけない。
そのためには、やはり文部省で発行した学習指導要領を、ちゃんと読んでおく必要があるだろう。まあ全文を読むのはかなり時間もかかるので(私も読んではいない)せめて手もとに置いて、必要な場合には見ることができるようにしておきたい。
この学習指導要領、おそらくは日本で一番安い本である。下の表をご覧いただきたい。
国語
|
110円
|
図工
|
70円
|
社会
|
100円
|
家庭
|
90円
|
算数
|
120円
|
体育
|
80円
|
理科
|
90円
|
道徳
|
260円
|
生活
|
50円
|
特活
|
80円
|
音楽
|
60円
|
総則
|
70円
|
|
|
合計
|
1,180円
|
ラーメン2杯分ぐらいの出費で買えるのだから、教師で生計を立てている人なら、必ず揃えておきたいものだ。
私も職場には全冊揃えて置いてあるのだが、今、この文章を書いている自分の部屋には置いていない。
しかし、世の中は便利になったもので(^^;) インターネットを活用すれば、書籍を持っていなくても、すぐに学習指導要領の本文を参照することができる。
文部省のサイトから入るのが普通の入り方だが、中に入っても必要とする資料を見つけにくいので、すぐに見たいという方は、下のリンクをご活用いただきたい。
○新小学校学習指導要領の内容
○旧(現行)小学校学習指導要領の内容
インターネットから情報を見つけたほうが、検索機能を使って、長い文章の中から必要とするキーワード(円周率等)を見つけたり、自分の文章の中に引用できたりするので、書籍を購入して手もとに置くよりも便利かもしれない。
<00.04.16>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ