野球用語だけ一般化
新首相が党総裁に指名される前、インタビューに答えて、「いいシュートをしても、オフサイドになることもあるから‥‥」と言っているのを聞いて、「おっ!」と思った。
早稲田大学ラグビー部の出身ということなので、なるほどとも思ったが、こういう場面でラグビーやサッカーなどの用語を使うのは珍しい。
一般的にはどうかというと、「○○知事、ついに降板」「○○党首、続投の意向」などのように、(野球の試合結果などではない普通のニュースに)野球の用語が使われていることが多いようだ。
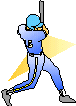
投手関係の言葉だと、登板・降板・続投・継投。打者関係では、トップバッター・代打・ヒット・クリーンヒット・凡退など、ちょっと考えただけでもかなりの数の例をあげることができる。攻守交替・外野・アウト・セーフなども、語本来の意味よりも野球の場面を連想して使われることが多い。
今では、野球以外にもサッカーとかバレーボールとか人気のあるスポーツが多いのだが、それらの用語が社会一般のことがらに転用される例はあまり見かけない。「連立政権で○○党がオフサイド」とか「予算委員会でサービスエース」などという表現を目にすることは少ない。
今回の新首相の発言は、その数少ない事例の1つということになる。
ちょっと視点を変えて、日本における野球の歴史を調べてみた。
野球(ベースボール)そのものは19世紀中頃に今のようなルールの原型ができたということで、これはサッカーやバレーボール、バスケットボールと大差はないのだが、日本に入ってきたのは他の競技よりかなり早い。
日本に野球が伝わったのが1871(明治4)年。東京の開成学校(現在の東京大学)のアメリカ人教師H.ウィルソンが伝えたといわれている。翌年には芝増上寺内の開拓使仮学校(のちの札幌農学校)でA.G.ベーツも試合のやり方を教えている。
これによって、学生を中心に広がりはじめ、1877(明治10)年、アメリカ留学から帰国した鉄道技師平岡煕(ひろし)が新橋鉄道局に「新橋倶楽部」(愛称アスレチックス)を創設してからますます盛んになったのだそうだ。
この平岡氏が、ルールブックや用具などをアメリカからとりよせ、本場じこみのベースボールを同僚たちに教えた。一高、慶応義塾、駒場農学校、明治学院などの学生の間で流行したが、彼らの中にはこのクラブで指導をうけたものが多かった。ベースボールを野球と訳したのは当時一高の野球部員だった中馬庚(かなえ)で、「テニスはコートでプレーするから庭球、ベースボールはフィールドでおこなう競技だから野球とした」といわれている。それまでは「玉遊び」だとか「打球おにごっこ」などと呼ばれていた。
正岡子規が「野球」という言葉をつくったという説もあるようだが、上記のように中馬庚がつくったというのが事実のようだ。
ちなみに、他の主な球技が日本に伝えられた時期は、下の表のようになっている。
1873(明治 6)年
|
サッカー
|
1878(明治11)年
|
テニス
|
1899(明治32)年
|
ラグビー
|
1901(明治34)年
|
ゴルフ
|
1902(明治35)年
|
卓球
|
1908(明治41)年
|
バレーボール
|
1908(明治41)年
|
バスケットボール
|
1921(大正10)年
|
ソフトボール
|
サッカー、テニスなどは、日本に伝わった時期は野球と近いのだが、詳しく調べてみると、その競技の協会やクラブなど、きちんとした組織ができたのが、サッカーの場合は1921(大正10)年、テニスの場合は1900(明治33)年という具合で、野球に比較するとかなり遅れている。
野球の場合、他の種目と比較して早い時期に伝わったことや、旧帝大や旧制高校等の先進的な学生の間に普及したことなどが理由となって、全国的に流行したようである。
さらに、明治時代後期から大正時代にかけては大学リーグが全盛となり、大正には現在の高校野球の前身である中学野球全国大会が始まり、昭和になると同時に、大学野球・高校野球のラジオ実況中継も始まった。
プロ野球も1935(昭和10)年にスタートし、各種野球の結果は、新聞・ラジオ等のマスコミでもにぎやかに報道されたので、野球は全国的な人気スポーツとなり、各種スポーツの中で独自の地位を築いたようである。
用語の面では、太平洋戦争中、敵国の言葉を使うのはけしからんということで、全ての英語表現が日本語化されたということもあるが、それ以前にも「一塁手」「捕手」というような表現がされていたようだから、野球は近代日本の文化の中にしっかり根付いていたのだろう。
近頃では、高校生のスポーツでも、サッカー・ラグビー・バレーボール等は全国大会のテレビ中継が行われて人気が高まってはいるが、やはり甲子園の全国高校野球大会の人気には及ばないようである。その他の種目の全国大会のテレビ中継は、たまにNHK総合テレビや同教育テレビで見かけることもあるが(それもほとんど決勝日だけである)、民放ではほとんどないようだ。
やはり、野球は日本人の国民的スポーツということができるだろう。
では、野球以外に、そのような(種目の用語が生活の中で一般的に使われるような)スポーツはないだろうかと考えてみたら、実はまだあった。
相撲がそうである。
「うっちゃり」「寄り切り」「仕切り直し」「水入り」「三役」「序の口」などの相撲用語は、相撲そのものの場面ではなく、社会一般のことがらを表現する場合にも多く使われている。
そういうことでは、さすがに「国技」と呼ばれるだけのことはあるが、相撲の場合にも野球の場合にも、その競技をやる人口が多いということよりも、新聞やラジオ・テレビ等のマスコミで扱われることが多いために、それらの用語を耳にする機会が多いので、社会一般の現象に転用されるようになったというのが、大きな理由なのかもしれない。
<00.04.08>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ