漢和辞典の謎
国語辞典、英和辞典などの辞書はできるだけ新しいものを使ったほうがよいのだが、使い慣れた辞書は手放せないもので、私なども中学・高校時代からの辞書をまだ使っている。
その中で漢和辞典を見ると、古い辞典(といっても昭和40年代のものだが)では「おやっ?」と思うようなことに出会うときがある。
特に面白いのが部首の分け方である。
例えば「体」という文字。見た目では「イ」があるので「にんべん」のように思える。ところが「にんべん」では出てこない。これは「ほね(骨)」を調べると出てくる。
なぜそうなるかというと、「体」の旧字が「體」であるからだ。
あるいは「和」。これは左側の部分が「禾」なので「のぎへん」と思われそうだが、実は「くち(口)」に属する。
 これも、古くは、「へん」と「つくり」が左右逆になった上の図のような形で、意味上は「口」に関係するものであり、「禾」は音を表すという理由からである。
これも、古くは、「へん」と「つくり」が左右逆になった上の図のような形で、意味上は「口」に関係するものであり、「禾」は音を表すという理由からである。
このような部首分けの基本になっているのが「康煕字典(こうきじてん)」である。
康煕字典は、中国の清代に編集された字書で、康熙帝の命令をうけて張玉書、陳廷敬らが監修し、5年をついやして、1716年に完成した。後に、道光帝の時代、1827年に王引之が引用上の間違い等を訂正して完成形となっている。
康煕字典では、明の「梅膺祚(ばいようそ)」の「字彙(じい)」の分類配列法を踏襲しており、字の構成部分のうち、意味に関する部分に分類の目印を求めているのだそうだ。
したがって見た目は「禾」の部分を持っていても、「移」「稲」「穏」「科」「穀」「秀」などは「のぎへん」または「のぎ」の部首に属するが、「利」は「?(りっとう・かたな)」の部に属するし、「季」は「子(こ)」、「委」は「女(おんな)」の部に属するという具合になるのだ。
このような例はたくさんあるので、以下、紹介する。
まず、最初の例の「体」のように旧字体が現在の文字の形と異なるために、見た目とは違った部首に属するという文字はかなり多い。全ては紹介しきれないが、次のようなものである。(フォントの関係で文字の表示が簡略化されることもあります)
|
現字
|
部首
|
旧字
|
|
現字
|
部首
|
旧字
|
|
現字
|
部首
|
旧字
|
|
当
|
田
|
當
|
|
営
|
火
|
營
|
|
単
|
口
|
單
|
|
厳
|
口
|
嚴
|
|
円
|
口
|
圓
|
|
与
|
臼
|
與
|
|
写
|
宀
|
寫
|
|
両
|
入
|
兩
|
|
予
|
豕
|
豫
|
|
県
|
糸
|
縣
|
|
余
|
食
|
餘
|
|
並
|
立
|
竝
|
|
冒
|
冂
|
冐
|
|
台
|
至
|
臺
|
|
寿
|
士
|
壽
|
|
声
|
耳
|
聲
|
|
医
|
酉
|
醫
|
|
処
|
虍
|
處
|
|
点
|
黑
|
點
|
|
変
|
言
|
變
|
|
欠
|
缶
|
缺
|
|
双
|
隹
|
雙
|
|
売
|
貝
|
賣
|
|
弐
|
貝
|
貳
|
次に、「和」のように、意味に関する部分が部首となるために、見た目の部首(通常は文字の左側とか上側とか)とは違う部分が部首になる文字は次のようなものがある。
漢字
|
部首
|
|
漢字
|
部首
|
利
|
刀
|
|
委
|
女
|
季
|
子
|
|
香
|
香
|
化
|
匕
|
|
行
|
行
|
術
|
行
|
|
衛
|
行
|
相
|
目
|
|
視
|
見
|
禁
|
示
|
|
則
|
刀
|
敗
|
攵
|
|
想
|
心
|
問
|
口
|
|
田
|
田
|
巡
|
巛
|
|
今
|
人
|
令
|
人
|
|
合
|
口
|
命
|
口
|
|
金
|
金
|
食
|
食
|
|
和
|
口
|
もう一つ面白いのが「王」と「玉」の関係である。
「王」に点「、」を一つ加えると「玉」という字になる。したがって、「玉」という字は「王」を構成要素として含んでいると考えるのが自然なのだが、実際は「王」は「玉」の部に属するということになっている。
つまり「王」は「玉」の部の「0画」ということになっているのだ。「玉」の部の「マイナス1画」とでもしたらいいようなのだが‥‥‥
さらに「珍・班・琴」など、文字の一部に「王」を持つ字も、「玉」の部に属するとされているのだ。これは不思議である。
これは「王」と「玉」の字源によるものだそうだ。
もともと「玉」は「王」の形であった。また「王」は別の字源によるもので、下の図のように上の横画と中の横画の間隔が狭い字形だった。
本来の「王」は斧をかたどった(人が手足を左右に大きく開いて天地の間に立っているという説もある)象形文字から発したものであり、「玉」(最初は王の形)は、「たま」をひもで三個連ねた形を表した象形文字から発したものなのだそうだ。
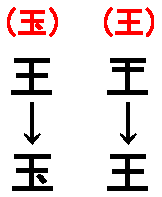
しかし、これでは紛らわしいので、後に「、」を加えて「玉」にしたというのである。
そこで「康煕字典」では「王・珍・班・琴」などを「玉」の部に位置づけているのだそうだ。
このような面白い(不思議な)部首の分け方も、最近の漢和辞典や児童生徒用の漢和辞典では、現在一般的な文字に合わせて見た目で理解しやすい部首に整理しているものがほとんどのようだ。具体的には、「体」は「イ(にんべん)」、「両」は「一(いち)」の部に属するという分け方になっている。
しかし、現在、市販されている漢和辞典の中には、やはり「康煕字典」の分け方を忠実に守っているものもある。また、一太郎等で使われる日本語FEPの「ATOK」に「漢字検索」という機能があるが、そこで「文字情報」を表示させると、やはり「体」は「ほねへん」、「両」は「入」というように康煕字典通りの部首になっている(最新版でもそうである)
反対に三省堂の漢和辞典などのように、昭和40年よりも前から、見た目通りの部首分けを行っていた辞書もあるようだ。
まあ、部首がどうであろうと日常生活に大きな影響はないのだが(^^;)、酒飲みの席でちょっとうんちくを垂れたいときなどには、面白いネタかもしれない(^^;)
なお、このページに使った資料の多くは、文化庁「言葉に関する問答集3」(昭和52年発行)による。
<00.01.31>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ