2000円ネットワークの構築
新しいパソコンを買ったので、嬉しくて調子に乗って書くコンテンツ。既に実行している方や、使用パソコンが1台の方には無関係な内容だが、今後の何かの参考になれば‥‥
また、以下の内容は、私が見よう見まねで試行錯誤してやってみたことなので、本職のシステムエンジニアの方が見たら「なんじゃこれは!間違いが多いぞ!」というものかもしれないが、その場合はご容赦を‥‥。ただ、素人レベルでも、このぐらいはやれそうだという内容である(^^;)
新しいパソコンを買う
パソコンを使い始めて1年ほどの方は、最新型高性能のマシンをお使いだろうが、2年以上になる方だと、そろそろ性能的に満足できなくなったということもあるかもしれない。
私はMacを使ったことがないので、Windowsマシンに限定して話を進めるが、2年以上前のマシンとなると、特別に改造や増設をしていない場合、CPUはペンティアムの200MHz以下、ハードディスク容量は2GB以下、メモリは多くても64MB、OSもWindows95といったところではないだろうか。
これまで使っていたアプリケーションを使うだけなら、これでも全く問題はないのだが、新しいソフトを入れようとしたりするとだいぶ苦しくなってきた。不要なソフトやファイルを削除したりして工夫をしても限界がある。
ここで、CPUを載せ替えたり、ハードディスクやメモリを増設するのも1つの手だが、この頃ではパソコン自体の価格が安くなってきて、デスクトップマシンの場合、20万円以下で高性能のものが手に入るようになった。廉価版だと10万円を切るものもある。それでも2・3年前のマシンと比較したら夢のような高性能を備えている。
古いマシンに手を加えて使い込むのもよいのだが、それよりは新マシンを購入したほうが合理的な状況になってきたので、私もついに新しいマシンを買うことにした。
古いパソコンをどうするか
さて、新しいパソコンを手に入れたら、問題になるのが古いパソコンをどうするかということである。
知人に譲ったり、子供に使わせたりという方法もあるが、誰かに売るにしても、せいぜい1万円程度でないと詐欺になってしまう(^^;)
長い間使い込んだパソコンほど、自分にあった環境設定になっている。使い勝手が良いように各種ビューワーなどの小物ソフトが組み込まれていることもあるだろうし、ファイルの種類(拡張子)とアプリケーションとの関連付けもうまくいっているはずだ。インターネットをやっている場合は、プロバイダへの接続設定や受信したメール・アドレス帳など貴重なデータも保存されている。
これを新しいパソコンに全て移しかえるとなると大作業である。
置くスペースがあるのなら、古いパソコンはそのまま残して、ネットワークを組んで使うのが、生かした活用のしかただと思う。
ただし、古いとはいっても許容されるのはWindows95マシンまでで、MS-DOSマシンはもちろんだがWindows3.1マシンでもちょっと無理があるようだ。これらのOSではネットワーク機能が弱いからである。(フォーマットしなおしてWindows95等をインストールすれば別だが、性能的にちょっときびしい)
カードとケーブルで2000円
そこで、2台のパソコンをネットワーク化するのに、どれだけのお金がかかるかということになるが、うまくやれば現在の価格で2千円でまにあう。
最小限必要となるのは、ネットワークのためのカード(ボード)とケーブルである。
カードはパソコンのスロットに差し込むもので、既に装着済みで発売されているパソコンもある。私の新パソコンは装着済みであったので、この場合、1台分は購入の必要がない。未装着の場合は購入して、パソコンのカバーを開けて装着しなければならない。
機種によって、ISAバス用とPCIバス用があるが、どちらも千円ちょっとで買える。PCIバスに空きがあるのならPCI用が望ましい。ノートパソコンの場合はPCカードスロット用になるが、これは少し価格が高くなる。通信速度によって「10BASE」のものと「100BASE」のものがあり100BASEが高性能だが、家庭内LANなら安価な10BASEで十分である。形式は現在一般的な「10BASE-T」にする。
あとはケーブルだが、2台のパソコンを直結するだけなら、「ツイストペア・クロスケーブル」を使う。これで2台のパソコンのネットワークカードを接続すればよい。このケーブルは数百円で買える。
私の場合は、将来の拡張性も考えて、間にハブを入れる形式にしたが、2台を直結するだけならハブは不要である。(実際にクロスケーブルでハブを使わずに接続してみたら、ちゃんと動作した)
ハブを使う場合には、クロスケーブルではなくストレートケーブルを使うので、電器店などにはクロスケーブルを置いていない場合もある。その場合はストレートケーブルに「クロス変換コネクタ」をつけるとよい。これは置いている店が多い。500円程度で買えるようだ。
ハブを使う場合は
将来的にもっと拡張したネットワークにしたい(パソコンを3台以上にするとか、プリントサーバやルータを入れるとか)という場合は、ハブを使う。これも3千円以下のもので十分である。
この場合は、前にも書いたように「ストレートケーブル」を使う。2台のパソコンの間をハブで接続するので、ケーブルは2本必要になる。
両方のパソコンにネットワークカードが付いていない場合、ネットワークカード2つで約3千円、ハブが3千円以下、ケーブル2本で千円ぐらいだから、7千円もあればお釣りがくる。
導入の実際
以下は、実際にどのような作業を行うかということだが、機種によって若干の違いがあるはずだし、細かい作業については記述することができないので、自分でやる場合にはカード等に添付の説明書や、市販のガイドブック等を参照してほしい。
ただ、やってみたけどうまくいかないというときには、以下の文章の中にヒントがあるかもしれないので、ご覧いただきたい。
カードの挿入とドライバの組み込み
まず(デスクトップ機の場合だが)、カードの説明書にしたがって、パソコン本体のカバーを外し、所定のスロットにカードを差し込む。
カードを取り付けた後、パソコンの電源を入れると、ほとんどの場合は「プラグアンドプレイ」によって「新しいハードウェアが検出されました」というメッセージが出て、デバイスドライバの組み込みを行う状態になる。
ここでネットワークカードに添付されたドライバを組み込むことが多いようなので、カード添付の説明書どおりにやれば問題はない。ただ、次の点には注意したほうがよい。
まず、添付のフロッピー(またはCD)には、ドライバそのものは入っていても、他に必要なWindowsファイルは入っていないことが多い。この場合、WindowsのCDからインストールするようになるが、パソコンに最初からWindowsが入っているマシン(プリインストール版と言う。市販のパソコンはほとんどそうである。そうでないのは自作のマシンとか後からWindowsを組み込んだもの)では、本体ハードディスク内に既に保存されているファイル(圧縮されている)を使うことになる。その場合、ファイルのコピー元の場所は「c:\windows\options\cabs」(NEC98シリーズの場合はCではなくA)を指定することになる。
また、この段階で「識別情報」(コンピュータ名とワークグループ名)を指定しなければいけないこともあるようだ。これについては後述するので、そちらを参照していただきたい。もしここで間違った名称を設定しても、あとで変更できる。
ドライバ組み込み成否の確認
ここまでがうまくいけば、パソコンを再起動すると次のようになっているはずである。
まず、いちばん見分けやすいのは、デスクトップに、これまでなかった「ネットワークコンピュータ」というアイコンが表示されることである。
あとは、「設定」→「コントロールパネル」→「システム」とクリックしていき(デスクトップのマイコンピュータを右クリックしてプロパティを選んでも同じ)「デバイスマネージャ」タブをクリックすると、たくさんのデバイスが表示されるので、その中の「ネットワークアダプタ」の「+」マークをクリックして内容を見てみる。ここにネットワークカードのアダプターが入っていればOKである。
ここからが難しいネットワークの設定
これで終わりならカンタンなのだが、ここから多くの設定を行わなければならない。手順が多いので要点だけ記述していく。
ネットワークの設定の確認
この後、様々な作業を進めていく上で、よく使うのが「ネットワーク」の画面なのだが、これは次の方法で表示する。
デスクトップの「ネットワークコンピュータ」アイコンを右クリックして「プロパティ」でOK。他に、「設定」→「コントロールパネル」→「ネットワーク」という方法もある。どちらでも同じ画面が出るので、状況に応じて楽な方を使うとよい。
下のような画面である。
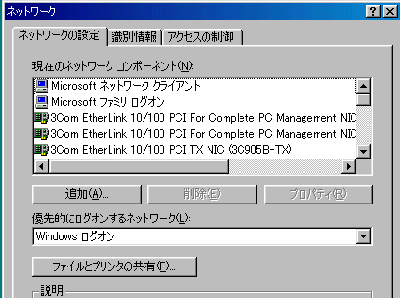
上の例は私のパソコンのものなので、家庭内ネットワークをするためには必要でないものも入っているのだが、次の4つは必ず入っている必要がある。
○ Microsoft ネットワーククライアント
○ ネットワークカード(前の作業で導入済み、メーカー名が表示される)
○ TCP/IP(上の行のネットワークカードに対応したもの)
○ Microsoft ネットワーク共有サービス
この他に、インターネットを(ダイヤルアップ接続で)行っている方の場合は、「ダイヤルアップアダプタ」と「TCP/IP」(ダイヤルアップアダプタ対応のもの)が入っているはずである。
足りない場合の追加のしかた
おそらく上記の必要な4つのうち、いくつかは足りないものがあるはずである。
その場合は、上の画面の「追加(A)」のボタンをクリックする。すると下のような画面が開くはずである。
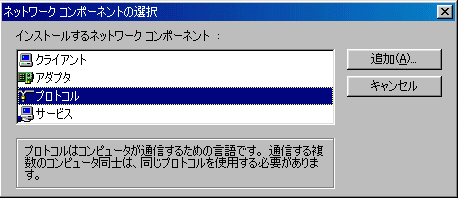
もし「Microsoft ネットワーククライアント」がなかったならば(たいていは初期状態で導入済みのはずだが)、上の画面の「クライアント」を選択して「追加(A)」ボタンをクリックすると「ネットワーククライアントの選択」という画面が開くので「製造元」でMicrosoftを指定し、いくつか表示される候補の中からMicrosoft ネットワーククライアントを選択すればOKである。
他の「アダプタ」「プロトコル」「サービス」も、不足なものがあれば、同様の手順で追加する。(追加するごとに再起動が必要なので少々面倒だが‥‥)
TCP/IPの設定
次に「ネットワークの設定」画面に戻って、ネットワーク用の「TCP/IP」(ネットワークカードの名前がついたもの)を選択して(色が反転)、「プロパティ(R)」ボタンをクリックする。
「バインド」とか「詳細設定」とか、いろいろなタブのついた画面が出てくるので、ここで一番右端の「IPアドレス」をクリックすると、数値を入力するような画面になる。
自動的に取得の方にチェックがついているかもしれないが、自宅でネットワークする場合には特にサーバーがあるわけではないので、自分が手動で設定しないといけない。
ここでは、ある程度のお約束があるので、その通りにやる。
まず、IPアドレスのところは次のようにする。
192.168.1.○
この「○」の部分は自分で好きな数字を入れればよい。ただし、2台のパソコンの数値は異なるようにする。「1」と「2」でもよいのだが、私の場合は、もし今後、台数が増えた場合のことを考えて「10」と「11」にしてみた。具体的には「192.168.1.10」と「192.168.1.11」にしたわけである。
それから「サブネットマスク」のところは、無条件に次のようにする。
255.255.255.0
識別情報の入力
これまで「ネットワーク」の画面の「ネットワークの設定」タブの画面で作業を進めてきたが、次に、そのわきの「識別情報」のタブをクリックする。Windows98では「識別情報」となっているが、Windows95では「ユーザー情報」となっている。
すると「コンピュータ名」と「ワークグループ名」を入力する画面になる。
「コンピュータ名」には、それぞれ好きな名前をつけてよい。たとえば1台には「akira」、もう1台には「sasaki」などのようにする。(2台に同じ名前をつけてはいけない!)
「ワークグループ名」は全て同じ名前にしないといけない。例えば「MY-ROOM」などでよいわけである。
その下にある「コンピュータの説明」のところには記入する必要がない。記入してもかまわないが、エクスプローラ等で見たときにその説明が表示されるだけで、動作上は何の影響もない。
アクセスの制御の設定
右端に「アクセスの制御」タブがある。(Windows95の場合は「アクセス権の管理」になっている)
この画面では「共有レベルのアクセス管理」を選ぶ。
「ユーザーレベルのアクセス管理」はNTサーバーを使っているときに可能になるもので、Windows95や98では使えない。
共有の設定
共有の設定は2段階で行う。
まず、「ネットワークの設定」の画面に戻り、「ファイルとプリンタの共有」ボタンをクリックする。自分で使うのだから、ファイルもプリンタも「共有できるようにする」にチェックをつける。
これで「ネットワーク」の画面での作業を終わり、マイコンピュータかエクスプローラの画面を開く。これまでの作業がうまくいっていれば、例えば「Cドライブ」を右クリックすると開くいくつかのコマンドの中に「共有」というのが表示されるようになっているはずである。
ここで「共有」を選択し、フルアクセスを可能にしておく。他人に使わせる場合は勝手にアクセスされないようにすることも必要だが、自分で使うのだから全てのドライブをフルアクセスにしておいたほうが便利である。ただ、CD−ROMのような読みとりしかできない媒体は「読みとり専用」でよい。
他人も使うネットワークで、ドライブ全体を共有するのでは具合が悪いという場合は、フォルダ単位で共有の可否の設定もできる。
また、プリンタもここで共有の設定をしておくとよい。
もしだめだったら
これで、2台のパソコンは互いを認識して、相互にファイルを読み書きできるようになるはずだが、だめな場合もあるようだ。(私の場合がそうだった)
そのときには「プロトコルの追加」で「NetBEUI」(Microsoftのもの)を追加すると解決するようだ。(私の場合は様々な設定を行ってもうまくいかず、最後にこれを導入して、やっと動作するようになったのだが、知人には何も面倒なことをしなくてもNetBEUIを入れるだけで大丈夫という話をする人もいるが真偽のほどはわからない。NetBEUIを入れると動作が遅くなるという人もいるし‥‥)
優先的にログオンするのは
ここまでやれば、おそらくネットワーク化は完成のはずである。ただ、場合によっては、パソコンを起動した段階でユーザー名などを入力する画面が出て、「Enter」キーを押さないと次の画面に進まない場合もあるかもしれない。(「スタートアップ」に自動実行ファイルなどを登録している場合、これはかなり不便である)
これは「ネットワーク」の画面(最初の図参照)で「優先的にログオンするネットワーク」を「Microsoft ネットワーククライアント」にしているためである。
そこで「優先的にログオンするネットワーク」を「Windows ログオン」に変更すれば、特別にパスワードを設定しておかない限り、問題なく動作するはずである。
ネットワークが完成したら
この手順で進めて、うまく2台のパソコンがネットワークで結ばれたら、あとはなんでも好き放題である(^^;)
まず、片方のパソコンから、相手のパソコンの中を自由に見たり操作したりすることができる。
エクスプローラやマイコンピュータで見てみると、こちら側のコンピュータの中身が表示された下に「ネットワークコンピュータ」というのが表示されて、それを開いてみると相手側のコンピュータの中身が表示される(ただし共有化しているドライブやフォルダの中だけである)
例えば、ワープロソフトを使う場合、自分のコンピュータの中にあるファイルだけでなく、ネットワークで結ばれたコンピュータの中のファイルも自由に編集ができるのだ。
あるいは、2台のコンピュータのハードディスク(あるいはフロッピーやCD)の中のファイルを、自由にコピー・移動・削除ができる。しかもフロッピーにコピーして2台のパソコン間でやりとりするのとは比較にならない(何百倍もの)速さで転送されるのである。もちろんフロッピーには入らないような大きなサイズのファイルも自由自在に扱える。
私の場合、新パソコンがDOS/V機なので、従来のNEC98シリーズで使われていた1.2MBフォーマットのフロッピーディスクは読めないのだが、これもネットワークを介することで旧パソコン(NEC-9821)のドライブで読み書きできるようになった。旧パソコンを廃棄してしまえば読み書き不能になるフロッピーのデータも活用できるので、これは便利である。
旧パソコンのCD−ROMドライブにCD百科事典を入れて、これを新パソコンから使うようにしてみたが、これも大丈夫であった。新パソコンではDVD兼用のドライブも含めて2つのCDドライブがあるので、旧パソコンと合わせると3つのCDドライブが使用可能になった。
環境コピーに最適
古いパソコンを使っていて、新しいパソコンを買った場合、一番の悩みが、いかに元の操作環境を移植するかである。
特にインターネットで使っていたアクセスポイントへの接続の設定やFTPの設定などは再度設定するのも大変である。またアドレス帳のデータや、これまでの送受信メールのデータも移植できたほうが具合がよい。これらも関係のファイルをコピーすることで解決する。
また、コピーしなくても、データの置き場所をネットワーク先のパソコン・ハードディスク上にしておいてもよいのだから、実質使用できるハードディスク環境が増えるということにもなる。
インターネットは切り替え器で
インターネットへの接続は、ダイヤルアップルーターを導入すれば、どのパソコンからもスムーズにできるようになるし、ルーターがあればハブも不要なのだが、ルーターの価格が4万円程度なので、これはあきらめた。
本格的なネットワークで複数の人間が同時にインターネットに接続するのならば、ルーターが必要になるが、私のように自分一人が使う場合には、両方のパソコンで同時にインターネット接続するということはありえないので、シリアルポート(RS323C)の切り替え器を使うことにした。これは3千円程度で入手できる。これまでつかっていたTAに接続するだけでよい。
旧パソコンはフルカラー表示にした場合、800x600ドットが限界のマシンだったので、インターネットをブラウズする場合、その設定にしていた。そこで自分のホームページも、その表示を前提としている。新パソコンでは1024×768ドット表示にしているので、だいぶ見え方が違う。両方のパソコンを使って2通りの見え方をチェックするのも、ネットワーク化した環境だと簡単である(この場合はインターネットに接続しないで、自分のパソコン内にあるデータをブラウズするのだが)
片方のパソコンにプロキシの設定をして、他方のパソコンで使用することもできるようだが、これはまだ試していない。
プリンタ切り替え器はいらない
プリンタも両方のパソコンから使いたいと考えた。
使っているプリンタが高性能のものなら、プリントサーバーを導入することもできるが、安価なプリンタだとネットワーク対応していないのもある(私が自宅で使っているものはそうである)
しかし、プリンタ共有の設定をすれば、特別な装置を使わなくても両方のプリンタから印刷が可能であった。(ただしプリンタを直接接続しているパソコンの電源は入れておかなければならない)
面白いもので、新旧両方のパソコンからプリンタのテスト印字の指定をして印刷したら、旧パソコン側からやった場合は「Windows95」というロゴが入った印刷になり、新パソコンからやったら「Windows98」になった。フォントも若干違ったような結果になった。
特別なものは何もいらない
この作業をやるまで、正直なところ、ネットワークを構築するのは大変なものだと思っていた。
学校などで使っているネットワークには、WindowsNTだのLinuxだのといった特別なOSのサーバーマシンが使われている。もしかしたら自分でやる場合もそういうものが必要なのかとか、ネットワークのための特別なソフトが必要なのかとも思っていたが、これもいらなかった。Windows95やWindows98には、十分にそのような機能が備わっているのである。
また、片方のマシンがWindows98で、他方がWindows95の場合、うまくつながらないのではとも心配したが、これも全く問題がない。
最初は旧パソコンにハードディスクの空きができたら(データ等を新パソコンに移動するので)Windows98をインストールしてみようかとも考えていたのだが、これも不要なようだ。むしろWindows95がプリインストールされていたマシンならば、そのまま使ったほうが様々な設定をする場合に都合がいいようである。(Windows98にアップグレードしたりすると、設定作業のたびにCDを挿入しなければならないこともあるようだ)
こんな感じ
ということで、まずは無事にネットワーク化された私の部屋のコンピュータ、下の写真のような感じである。

私の場合は、今後の拡張も考えて、ハブや切り替え器類も購入したのだが、それでもかかった経費は1万円程度。前述のようにクロスケーブルによる直接接続であれば2000円ほどで大丈夫である・
何かのはずみで(^^;)パソコンが2台以上になった場合は、こんなネットワーク化も試してみたら面白いだろう。その場合には、このページを印刷して参照していただけば、少しは役に立つかもしれない。
<00.01.10>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ