ナマケモノと休符
音楽に日頃から親しんでいる人だと、楽譜を見るのは慣れているはずだが、いざ自分で楽譜を書いてみるということになると、意外に記号の書き方などに自信がないということもあるのではないだろうか。
この頃では、コンピュータで作曲する人も多くなり、音楽ソフトも充実してきている。これを使えば、ソフトが自動的にきちんとした楽譜を書いてくれるので便利なのだが、これに頼ってばかりいると、かえって正確な記号が書けないということもあるかもしれない。
実際、私の場合などは、ギターやピアノを使いながら音を探して、五線譜に鉛筆で記録するということのほうが多い。
これをあとでコンピュータやシーケンサーで整理していくので、手書きの楽譜は自分だけ読めればよいのだが、それでも、ちょっとした記号などを書くときには、「これでいいんだっけ?」と不安になることもある。
ドレミなどの音符は、音階と音長だけがわかればよいのだから、特別に気をつけることもないが、よく使う割には不安になるのが「ト音記号」や「ヘ音記号」。
形はだいたいわかるのだが、どの場所に書くのか自信がないという方もいるのではないだろうか。
まあ、これは、その記号本来の意味を考えれば難しいことではない。
「ト音記号」とは「ト」の音を示す役割をしているのだから、下の図のように、音名(階名ではない)の「ト」の音となる第2線をぐるぐると囲んで「ここがトの音ですよ」ということがわかるようにすればよいのである。
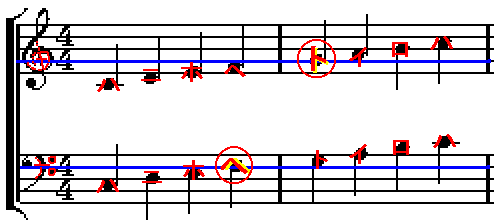
低音部の楽譜に使われる「ヘ音記号」も同様で、音名「ヘ」の音となる第4線を、2つの点ではさみ、さらに丸く囲んで示している。
したがって、これらの記号は、少しでも位置がずれてしまえば、意味をなさないわけだが、逆に考えれば、どの位置に書けばよいかということも理解しやすい。
余談であるが、ト音記号・へ音記号のことを英語では「G clef」「F clef」という。クラシックの曲を現代風に演奏する「Gクレフ」というグループがあったが、その名前はこれに由来しているようだ。
音楽にかなり詳しい人でも、意外にわからないのが、二分休符と全休符。
どちらも黒い四角であることはご存知だろうが、どちらが上向きで、どちらが下向きか、それに五線譜上のどこに書けばよいのかとなると、「???」という方も多いのではないだろうか。
まあ、正解は下の図のとおりなのだが、もしかしたら、これを逆に覚えていたとか、どちらも五線の真ん中の第3線に接していると思っていたとかいう方もいるのではと思う。(実は私がそうであった‥‥‥)
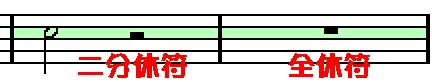
ご覧のように、二分休符は第3線に乗っかるようなかたち、全休符は第4線にぶら下がるようなかたちである。
これを正確に覚えるのは、けっこう難しい。
こうやって見たときは、わかったようなつもりになるが、しばらくたつと忘れてしまう(中年の私だけかもしれないが‥‥)
そこで、絶対に忘れないように、何かにこじつけて、強いインパクトを与えるような覚え方がないか考えてみた。
私が「これは、いいんじゃないかな」と思ったのが「ナマケモノ」に例える方法である。これは今までに何度か試してみたが、この方法で説明した子供たちは、わりによく覚えてくれたようだ。
ナマケモノとは、ご存知のとおり、木の枝にぶら下がって生活する例の動物である。(下の写真)

参考までに事典にあった説明を引用する。(主な内容のみ)
- ナマケモノ Sloth
- 樹上生活をおくる動きのにぶい数種の哺乳類の総称。南アメリカおよび中央アメリカの熱帯林に生息する。ナマケモノは2科に分類される。ミユビナマケモノ科とフタユビナマケモノ科である。いずれも体長は、約41〜74cm。小さな頭部はひらたく、大きな目としし鼻が特徴。耳は外からはみえない痕跡器官となっている。体は灰色がかった茶色の短い毛でおおわれ、ミユビナマケモノには小さな尾があるが、フタユビナマケモノの場合は尾がまったくないか痕跡器官となっている。1万年以上前に西半球にいた巨大なナマケモノは、ゾウに匹敵する大きさで、地上でくらしていた。
- 寿命は比較的長く、10年以上生きる場合もある。生涯の大半を太い枝にぶらさがって、食べる、ねむるはもちろん、交尾、出産までそのままですごす。四肢でぶらさがるため、顔は上向き、背中が下向きになる。四肢は長く、よく発達しており、長い湾曲したかぎ爪をひっかけるようにして枝をつかむ。前肢は後肢より長く発達していて、よくうごく。移動するときは、肢(あし)を1本ずつゆっくり慎重にうごかしてすすむ。木から地上におりるのは、週に約1回の割合で排便および排尿するときだけである。歩けないため、地上では仰向けになるか、腹ばいで移動する。
- 日中は、前肢の間に頭をいれ、四肢をよせあって枝につかまり、まるくなってねむっている。この姿勢は遠目には大枝の切り株のようにみえるため、ジャガーなどの天敵から身をまもる擬態になる。また、体毛に藻類が付着し、体全体が緑色でおおわれているため、周囲の葉や苔(こけ)と見分けがつかなくなる種もいる。ふだんはほとんど声をださないが、ときどき低いかなしげな声を発する。食べるのは主として葉と新芽で、口のとどく範囲に独特なゆっくりした動作で葉をひっぱってきて食べる。メスは毎年、1頭の子をうむ。子は単独で行動できるようになるまで母親にしがみついてすごす。
事典の説明によると、本当は背中を上にして歩くということはできないようなのだが、説明の都合上、木の上を腹這いになって移動できるのだと仮定する(^^;)
そうすると、「完全に休んでいる状態」は「木にぶら下がっているかたち」、「少し休んでいるけど、すぐに動き出せるような状態」は「木の上に腹這いになっているかたち」という図式が成り立つ。
これと、二分休符・全休符のかたちとを結びつけて連想させるのである。
あとは、「どの位置に書くのか」という問題になるのだが、本当は熱帯林(ジャングル)ということだが、これを「山間部」にこじつける(少々苦しいこじつけだが‥‥)そこで「さんかんぶ」から、「第3間(第3線と第4線の間)に書くのだ」と覚えさせる。
ちょっと、本物のナマケモノの実態と違うところもあるので、あまり「ナマケモノ」を力説すると、子供たちに間違ったナマケモノのイメージをうえつけることになり、教育上よろしくないかもしれないし、ナマケモノに怒られるかもしれないが、少なくても自分でしっかり覚えておこうというときには、この「ナマケモノこじつけ記憶法」(^^;)が効果的なのはたしかである。
<99.12.29>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ