超簡単ジャズピアノまがい
西田敏行の「もしもピアノが弾けたなら」という歌を聴くと、私はしみじみと共感してしまう。
ピアノはおろかオルガンさえも持っている家庭が少なかった時代に育った私。今のように鍵盤ハーモニカを学校で使用することもなかった。音楽の授業で鍵盤の練習をするときには、音楽の教科書の真ん中の見開き2ページの紙鍵盤であった(^^;)
これだと運指がでたらめだろうが、間違った鍵盤を叩こうが、他の人には迷惑がかからない。なにしろ音が出ないのだから‥‥(^^;)
そんな具合で、ピアノが弾けるのは学年でも1人か2人ぐらい。ピアノ教室に通っているお金持ちのお嬢様くらいだった。
その後、趣味でロックバンドをやったり、教師という商売柄、どうしても授業で使わなければいけなかったりということで、鍵盤楽器に触ることになり、とりあえずは伴奏らしきものを弾いてはいるが、私の奏法は全くの我流で、左手でベース音、右手でコード(和音)を弾くという「ズンチャッチャ」ピアノである。

したがって、右手でメロディ・ラインを弾くようなピアノ独奏型の演奏は全くの苦手である。正直にいうとほとんどできない。私の場合、メロディ・ラインはピアノで弾くものではなく、声に出して歌うものである(^^;)
そんな私だから、左右の手の指を自由に操って弾きまくる独奏型のピアノ演奏には大いにあこがれる。
ショパンやリストなどの難曲を1曲でもいいから弾きこなすことができたら‥‥と思うのだが、ぎこちなく動く指ではしょせん無理である。
ましてや、学校では習わないような難しいコードをつけながら、リズムもハーモニーも複雑なソロを弾きまくるジャズピアノなどは、自分には無縁のものだと思っていた。
ところが、先日、テレビを見ていたら、ジャズっぽいピアノソロを簡単に弾ける方法を知った。
実際には、そういう意図の番組ではなく、ジャズのモード奏法について解説した番組だったが、私は勝手に「これなら私でもジャズのピアノソロを弾ける」と思いこんでしまったのである。
クラシックでもジャズでも、ピアノソロが難しい理由の1つが、「白い鍵盤だけでなく黒い鍵盤も弾かなくてはいけない」ということである。
小さい頃から段階的に練習した人には苦でもないかもしれないが、私には黒い鍵盤はつらい(^^;)。大学のピアノの授業でバイエルを弾いたときも、黒い鍵盤を使う曲になったとたんに挫折してしまった。
もう1つは弾いてよい音と弾いてはいけない音があることだ。
クラシックの曲はメロディラインが厳密に決められているから外れた音を弾かれないのは当然だが、ジャズの場合でもコードに合った音でないと外れた感じになってしまう。13thだのオギュメントだのディミニッシュだのという難しいコードになると、その構成音をきちんと覚えていないとイモっぽいアドリブになってしまうし、そういうことを考えているうちに指はぴたっと止まってしまう。
要するに、勝手気ままに弾きまくりたいと思っても、でたらめに弾いてはだめだということになる。これも私にはかなりつらい。
ところが、モード奏法(正式には私の認識とは違うものなのだが)では、白い鍵盤しか使わないし、しかもどの鍵盤を押しても、その音が間違いということはないのだそうだ。
これなら白い鍵盤を気分にまかせて文字通り手当たり次第に弾けばよいのだから、私にもピアノソロができるということになる。
ここからの解説は素人の私が聞きかじりで書くので、かなりいいかげんである。インターネット上で検索したら、モード手法について詳しく書かれている安増高志さんのこのページ(Takashiの簡単作曲講座No.21)を見つけたので(リンク申請済み)、きちんと知りたい方は参照していただきたい。
モード奏法は、モダンジャズで、マイルス・デイビスや、ジョン・コルトレーンが使って注目された。
もともとは教会旋法から発生したものということだが、そこらへんは私はよくわからない。
現在、一般的に使われている音階は、「ハ長調」「ニ短調」などという調性を持つものである。
例えば長調(メジャースケール)の場合は、主音(トニック)から1オクターブ上の主音までの、それぞれの音の間隔が「全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音」という具合になる。
「C」(ハ)を主音とした場合、五線譜上に1つもシャープ(♯)やフラット(♭)をつけなくても(つまり白い鍵盤だけを使えば)長調の音階になる(Cメジャースケール・ハ長調)
「F」(ヘ)を主音にする場合は、「B」の音を半音下げる(B♭にする)と、「F」から始まる長調の音階(Fメジャースケール・ヘ長調)になるわけである。
これが一般的な調性を持つ音階なのだが、モードというのは、この「全・全・半・全・全・全・半」という間隔にこだわらずに、例えば「D」から始まったら黒い鍵盤を使わずに「D・E・F・G・A・B・C・D」と弾き切ってしまうのである。(この場合、音の間隔は、全・半・全・全・全・半・全となる)
この例に出した「D」から始まるモード(ドリアモード)だけではなく、「E」から始まる「フリギアモード」など、全ての音から始まるモードが存在するのだそうだが、そのことについての詳細は前述のページでご覧いただきたい。
それらのモードの中でも、「D」から始まる「D-ドリアンモード」がジャズでは多く使われるのだそうだが、私もそれに挑戦してみた。
まずは「D」を意識させるために、ピアノの低めの鍵盤で「D」の音を長く鳴らす。サスティンペダルを踏んでおくと効果的である。
「D」の音だけでもよいのだが、雰囲気を出すためには、特性音の「B」や、チャーチモードでよく使用された「A」の音を絡ませるとよいのだそうだが、私の感じでは「A」のほうが雰囲気に合っているようだ。
したがって左手で「D」「A」さらにオクターブ上の「D」の音を「タララーン」という感じで鳴らす。あとは右手で好き勝手に鍵盤を叩けばアドリブ演奏の出来上がりということになる。このときは白い鍵盤だけを叩けばよい。
これだけでも、そこそこの雰囲気が出るのだが、ちょっとワンパターンで飽きてしまう。
そこで、数小節過ぎたら、全体を半音だけ上げると、よりジャズらしくなる。
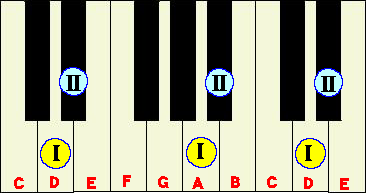
具体的には、最初の数小節を、左手で上の図の「Ⅰ」の鍵盤を押し、次に「Ⅱ」の鍵盤を押すようにする。
「Ⅱ」のパターンを数小節演奏したら、また「Ⅰ」に戻すということを繰り返す。
「Ⅰ」のときに、右手は白い鍵盤をどれでも叩きまくり、「Ⅱ」のときには全体が半音上がるわけだから黒い鍵盤だけを叩きまくればよい。
細かいことをいえば、全体が半音上がることによって「E」が「F」に、「B」が「C」にということが起こるので、黒い鍵盤全部の他に「F」と「C」の音も使えることになるが、それがめんどうな場合は黒い鍵盤だけでアドリブを行っても問題はない。
このやり方で、ピアノのサスティンペダルを思いっきり使って、ゆっくりめに自由気ままに弾いていると、自分がモダンジャズピアノの巨匠になったような気になる(^^;)
もちろん、本格的にジャズピアノをやられている方から見たらお笑いのプレイだろうが(理論的にも勘違いかもしれないし)、自分でピアノを楽しむという点では、それなりに面白いアプローチのしかたではないだろうか。少なくてもバイエルなどで味わったことのないハーモニー(?)の響きが楽しめる。
文字だけではわかりにくいので、最後に私の模範演奏のMIDIデータを(^^;)
(下のプレーヤーのプレイボタンをクリック)
おもちゃっぽいキーボードで一発録りしたものなので、「この音はもうちょっとどうにかしたら」という部分も多いのだが、そういう細かいことにこだわっていると、立派な大人、もとい立派なジャズピアニストにはなれない(^^;)
「超簡単ジャズピアノまがい」の雰囲気だけでも味わっていただけると幸いである。
<99.11.13>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る  うんちく目次へ
うんちく目次へ