デジカメで簡易プレゼンテーション
文化祭・講演会・学習発表会など、体育館・講堂のような広い場所で発表を行うときに、液晶プロジェクター等を使って、スクリーンに画像を表示すると効果が大きい。
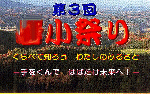
上の画像は、私の勤務校のイベントで使用した画像である。体育館のステージに設けられた大きなスクリーンに、このような画像が次々と表示され、その前で発表する児童たちの背景となって、会の雰囲気は大いに盛り上がった。
昨年までは、この表示をコンピュータで行っていた。
ノートパソコンを会場に持ち込み、コンピュータのRGBディスプレイ端子に液晶プロジェクターをつないで表示していたわけである。
設備が整ってさえいれば、それでよいのだが、手頃なノートパソコンがなかったりすると(昨年までは職員の私物を借用していた)大げさにデスクトップパソコンを持ち込んだりしなければならず、かなりめんどうである。
個人のノートパソコンを借用する場合も、画像を表示するためのソフトをインストールしなければならなかったりして、事前の準備に時間がかかった。
マイクロソフト社のパワーポイントのような、プレゼンテーション専用ソフトを使えば、画像や文字が、回転したり、上下左右から滑り出してきたりと、多様な表現効果を活用できる。
どうしてもそのような効果が必要な場合はコンピュータを使うしかないが、これまで私がやってきたのは、上の例のような静止画像を次々と表示させるという、いわゆる「スライドショー」的な使い方だった。
ふと考えついたのが、デジカメ(デジタル・カメラ)を使えないかということだった。
現在、出回っているデジカメの多くには、カメラ内に保存している画像をビデオ出力としてテレビなどに映すことできるものが多い。画像を順番に表示するだけなら、デジカメでもできそうである。
その機能をうまく使えば、わざわざめんどうな思いをしてコンピュータの設定や接続をする必要もなくなる。
今回、試してみたのは、ソニーのデジタル・マビカという機種であった。
3.5インチのフロッピーディスクを記録媒体としているという特徴もあって、学校で使うデジカメとしては定番となりつつある機種である。(マビカの公式サイトはこちら)

上の写真(ちょっとわかりにくいが)の右下の部分が外部に映像を出すジャックで、テレビ等のビデオ入力端子に接続すれば、フロッピーディスクに保存された画像を表示することができる。
もちろん液晶プロジェクターのビデオ入力端子にも接続可能である。コンピュータの場合、RGB端子がなければ接続できないのと比較すると、とても手軽である。コンピュータ専用の機器でなくても一般的なビデオ端子につなげるというのは、使用の可能性が大きく広がる。
ここで、本題に入る前に、少し、マビカの優れている点について触れたい。
一般のデジカメは、コンピュータと画像データのやりとりをする際に、RS−232C等のシリアルポートを使うのが一般的である。
それはそれで、双方向のデータ交信が可能であるなどのメリットもあるのだが、使用する場合には、それ専用のソフトを立ち上げなければならないとか、データのやりとりに時間がかなるとかいう問題もあって、あまり使い勝手はよくないようだ。
最近では、スマートメディアという記録媒体を使い、コンピュータ側にスマートメディア用のスロットがあれば直接データを読み込めるというものも増えてきたが、全てのコンピュータにスマートメディア専用スロットがついているわけでもない。多くの場合はシリアルポートを介してコードを接続し、データをやりとりすることになる。
その点、どんな安価なコンピュータにも標準で装備されているフロッピーディスクドライブを活用できるマビカは画期的である。
撮影したフロッピーディスクをカメラから引き抜いて、コンピュータのドライブに挿入するだけで、簡単に読み込みや編集が可能である。
フロッピーディスクは記憶できる容量が少ないので、保存できるいちばん小さなサイズ(640×480)の画像にしても、1枚のディスクに20数枚の画像しか保存できないが、ディスクがいっぱいになったら、すぐに別のディスクに差し替えればよいわけだから、バッテリーが続く限り撮影し続けることができる。
充電式バッテリーを使用できるのも魅力的だ。このバッテリー、撮影だけなら1時間半程度の連続撮影が可能である。しかも同社のビデオカメラ「ハンディカム」とバッテリーを共用できるのも嬉しい。
場合によっては、児童ごとにフロッピーディスクを準備し、撮影したらすぐにディスクを差し替えてコンピュータで読み込ませるということを次々とできるから、授業で活用するには、非常に使い勝手がよい。
静止画として保存できるファイル形式が「JPG」形式というのも、コンピュータで扱うには具合がよい。
付属の機能として、動画をMPG形式で保存できるというのもすごい。マビカを使わないで動画ファイルを作ろうとすると、コンピュータ側でビデオキャプチャーボードなど、まだあまり一般的でない機能を追加しなければいけないのだが、マビカだとそれがカメラ本体だけで簡単にできてしまう。
ただ、フロッピーディスクで使うことを前提としているために、カメラ本体にはコンピュータと接続するための端子がない。
ディスクに保存された画像をコンピュータに取り込むだけならそれでよいのだが、コンピュータ側からカメラにデータを送ろうとすると、ディスクそのものをコンピュータで編集しなければならない。
これは少々コツがいるようだ。
今回、このマビカで簡単なプレゼンテーションをするために、ソニーのサポートセンターに電話で確かめたり、自分で実験したりして、わかったノウハウがいくつかあるので、ここで紹介したい。
まず、普通にマビカで撮影した場合、次の3種類のファイルが作られる。
1.Mavica.htm
2.Mvc-001s.jpg
3.Mvc-001s.411
1枚の画像を撮影した場合は上のようになるのだが、2枚目を撮影すると、1番目のMavica.htmはそのままで(内容は書き換えられるが)、2番目のJPGファイルと、3番目の拡張子が「411」のファイルだけが、ファイル名「Mvc-002s」のように番号が1つずつ大きくなって増えていく。
ちなみに、「s」というのは、静止画の「スチル」の意味らしい。動画の場合は「ビデオ」の略のようで「Mvc-003v.mpg」・「Mvc-003v.411」のようになる。
静止画でも動画でも、撮影モードの設定により、画質や画像の大きさを変えることができるのだが、その差はファイル名には関係ないようで、どんなモードで撮影しても、静止画には「s」、動画には「v」がつく。
このファイル名の付け方をわかってしまえば、コンピュータで作ったり編集したりした画像を、ディスクに書き込めばよいということになる。
まず、前述の3種類のデータであるが、これが全て必要なわけではないということがわかった。
「Mavica.htm」というファイルは、撮影したフロッピーディスクをコンピュータ側のブラウザで見るときに使用するファイルなので、カメラ側でプレゼンテーションする場合には全く必要がなかった。
また「Mvc-00*s.411」というファイルは、カメラ側で「インデックス表示」(一覧形式で表示する)を行うときに使用するファイルで、これもプレゼンテーションには必要がない。
したがって、コンピュータで「Mvc-***s.jpg」(***は3桁の数字)というJPGデータを作り、これをマビカのプレゼンテーションに使うフロッピーにコピーするだけで大丈夫である。
411ファイルやhtmファイルはあまりサイズが大きくはないのだが、それでもこれらのファイルを扱わなくてもよいだけで、1枚のフロッピーディスクに保存できる画像データの数は少し増える。
そこで、コンピュータの画像処理ソフトなどを使って、プレゼンテーション用の画像データを作成する。
画像サイズは、「640x480」、「1024x768」、「1280x960」というのがマビカの標準画像サイズである(いずれも縦横の比率が4x3)
このサイズにフィットさせた画像データを作るのがコツなのだが、特に細緻な画像を表示したいという場合でなければ、640x480のサイズに仕上げるのがよいだろう。
そのほうがデータサイズも小さくなるので、1枚のフロッピーディスクに保存できる画像数が多くなる。
マビカの標準画像サイズに合わない画像データならどうなるのかという実験もしてみたが、サイズが合わないことが理由で表示できなくなるということはなかった。
基本的には、画像データのサイズに合わせて、マビカのほうで調節してくれる。
640x400のようなサイズだと、横は画面いっぱいになり、縦のほうは上下に少し空白(黒)をとったかたちで表示される。
400x200のような小さな画像は、640x480の画面の真ん中に小さめに表示される。
1024x768の画像は、標準画像サイズなので画面いっぱいの表示となるが、900x700のような画像は1024x768の設定の画面に小さめに表示されるようだ。
要は画像データが必要とする最大の表示サイズに合わせて、カメラ側で調節を行うということだ。
ただし、私の実験では、マビカの標準画像サイズではない「800x600」のサイズでも、それが最大表示されることや、縦が標準より若干長いデータ(640x485など)の場合、上下が少しカットされて表示される現象も見られた。(横が641のように少し長い場合は容認されず、小さめの画像表示となる)
もう一つ、興味深い現象は、JPGファイルでも、アドビのフォトショップで作って保存した画像データは「ファイルエラー」の表示が出て、画像が表示されなかったことだ。
アドビは自社独自の画像データ形式に力を入れている傾向があるので、JPGファイルでも標準形式と少し違う仕様になっているのかもしれない。
この場合は、コンピュータ側で、アドビの作ったJPGファイルを、別のフォトレタッチソフトで読み込み、上書き保存すれば大丈夫であった。
こうやって作ったファイルを、エクスプローラ等のファイル管理ソフトで、マビカの標準ファイル名である「Mvc-001s.jpg」等という名称に変更し、フロッピーディスクに保存すれば、マビカによる簡易プレゼンテーションができるというわけである。(001のような番号は、表示したい順番につける。同じ画像を最初・中間というように数回使いたい場合は、内容は同じでもファイル名を別にした複数のファイルとして保存する必要がある。またマビカの場合、mvc・Mvc・MVCといった大文字小文字の区別は無視されるようである)
これで、マビカを使った簡易プレゼンテーションはOKである。
ただ、電源を入れたばかりの状態だと、メニューバーや電池の残り時間・ファイル名・日付・現在時刻なども表示されてしまう。
メニューバーを表示しなくするには「メニューボタンを下側に押す」ということが画面にも表示されるので、すぐにわかるが、ファイル名等の余計な文字表示を消すには、下の写真の「ディスプレイボタン」を押せばよい。

また、途中でフロッピーディスクを差し替える場合、普通に接続したままで行うと、画面に「ディスクがありません」という文字表示が出てしまい格好が悪い。
この場合は、使用説明書では勧めていない方法だが、外部出力端子に差し込まれているプラグを抜いてしまうのがよいようだ。
プラグを抜いているうちにディスクを交換してしまうと、会場に余計な文字表示をしないで済む。実際に試してみたがトラブルはなかった。
さらに面白い使い方もある。
デジカメを液晶プロジェクター(または大型テレビ)につないだ状態で、画像再生モードではなく撮影モードにしてしまうのだ。
こうするとデジカメがビデオカメラになってしまう。
この状態でレンズを会場内に向けると、スクリーンに会場内の様子が映し出される。ディズニーランドのショーベース2000などで開演前に使われる手法であるが、これも学校で使ってみるとかなり楽しい。
今年のイベントでうまくいったので、ついつい長談義になってしまったが、デジカメを使った、このプレゼンテーションの方法、手軽なだけでなく、コンピュータではできないことも可能になるので、お勧めである。
ここでは、マビカを使った例をあげたが、他のデジカメでも不可能ではないと思う。マニュアルを精読してお試ししてみられたらいかがだろうか。
<99.10.24>
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ