車を運転していたときの話。
お盆の頃だったので、帰省客の車も多く、道路には他県ナンバーの車がかなり走っていた。
すれ違う車のナンバープレートをなんとなく見ていたのだが、ふとつまらないことが気になった。
普通、車のナンバープレートは、下の図のようになっている。
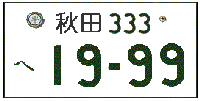
「秋田○○○」の部分が3桁になったのは、全国的には平成11(1999)年5月14日から。(一部の地区では平成10年5月19日)同時に希望番号制が導入された。それ以前に発行されたナンバープレートでは「秋田○○」のように2桁にである。
ここで、いちばん大きな文字で書かれている番号の部分は、4桁の数字なのだが、これが「314」のように3桁の場合、どんなふうに表記されるだろうかということが、ふと気になったのである。
コンピュータなどで数字を扱う場合、4桁で表示する場合は、「314」であっても、「0314」のように頭に「0」をつけて、見た目の桁数を揃えることがある。
私の誕生日「11月14日」のように、全ての桁が数字でうめられる場合はよいのだが、七夕の日などは「07月07日」と表記することがあるのだ。
そう考えるとナンバープレートは下のようになりそうだ。
ここで、「03」と「14」の間に短い横棒(ハイフン)を入れたのは、4桁の番号表示の場合、そうなっているので、同じ形式にしたのである。
あるいは単純に、頭に「0」をつけないとすれば、下のようになるかもしれない。
車は次々とやってくるので、ちょっとしたら運良く3桁ナンバーの車がやってきた。
やってきた車のナンバープレートは?‥‥と、よく見ると、なんと私の予想を見事に裏切って、次のようになっていた。
最初の部分(千の位)は、「0」でも空白でもなく、「・」という黒い点になっていたのである。
さらに意外なことには、4桁数字の場合、2桁と2桁の真ん中にあった「-」(ハイフン)がなくなり、半角程度の空白になっていたのである。
そうなると「26」のような2桁だけの数の場合、どうなるだろう?
「これまで気づいた規則性から想像すると、こんなふうになるのでは‥‥」と考えながら走っていたら、間もなくそういう車が走ってきた。
その車のナンバープレートは、私の予想どおり、次のようになっていた(^^;)
この日は、さすがに1桁だけの数字の車には会わなかったが、発見した規則性にしたがうとすれば、次のようになるだろう。
この結論にいたるまで、時間にして10数分のできごとであったが、私は大いに満足した。
たしかに「つまらない」ことではある。
しかし、自分なりに観察を行い、データを集めて(ただ車のナンバープレートを見るだけなのだが)、それを分析し、ひとつの規則性を見いだしたということに、私は興奮した。
この規則性は、私が作ったものではないし、なんらかのきまりで決められていることであり、既に知っている人にとっては別になんでもないことなのだが、そのきまりを知らない私が、規則性を発見したということは、ニュートンが万有引力の法則を発見したことにも匹敵する「偉大な発見」なのである(^^;)
子供の学習にも、こういうことは大事なのではないかと思う。
極言すれば、学習とは、これまで人類が発見してきた規則性を学ぶことであると言えよう。
これまで人類の誰もが気づかなかったことを、子供が最初に発見するということはほとんどないだろう。もしそういうことがあったとすれば、その子は「学習者」ではなく「偉大なる発見者」ということになってしまう。
学習の多くは、過去の人が発見した規則性を追体験しながら、自分のものとして理解し身につけていくというかたちをとる。
ただ多くの場合は、子供自身が本当に発見するというのではなく、他の人から説明してもらって理解したり、書籍に書かれたものを読んで理解するということになる。
そうではなくて、子供が自分の力で、何かの規則性を見つけたとしたら、それが既に誰でも知っているような簡単な規則性であっても、その子にとっては、過去の大発見と同じ価値を持つのである。
私のドライブ中の10数分の「研究」(^^;)と、それによる「大発見」は、まさにそのようなものであった。
私の場合は、「そういう大発見ができた自分」を、「自分でほめてあげたい」という気持ちになっただけであったが、子供がこのような発見をした場合には、大いに認めてあげたい。
また、そういう発見ができるような場や活動を、できるだけたくさん工夫していきたい。
例えば、遠足のバスの中でも、ただ歌を歌ったり、クイズを出していくだけでなく、「10分間、外を見て、何かを発見しよう」などという時間を設けるのも面白いかもしれない。
その結果、子供が発見したことが、本当につまらないものだったとしても、独力で見つけたものならば、どれも「素晴らしい発見」である。
以下は余談である。
この大発見をしたあと、私は家に帰って、自分の発見を裏付けることをインターネットで調べた。(子供の発見の場合も、発見だけで終わらせずに、インターネットや書籍でさらに調べるということが大切だと思う)
それによると、車のナンバープレートについては、私が発見したとおりの規則性が決められており、他にも次のようなことがわかった。
昭和26(1951)年6月1日から、「道路運送車両法」により自動車登録が始まる。これによってナンバープレートの形式が決められた。当時は3桁〜5桁の一連指定番号が使われた。「001」〜「99999」のようになる。頭のほうには「0」がつき、間にハイフンはない。(それ以前にも5桁までの番号が使われており「12.345」のように千の位の区切りの部分にピリオドが打たれる形式であった)
昭和30(1955)年3月28日に、4桁の一連指定番号が導入される。現在とほぼ似た形式にはなったが、「0001」のように頭に「0」がつき、間にハイフンはない。
昭和37(1962)年8月に、現在の形式が導入される。頭の「0」のかわりに「・」が使われ、1000以上の数になった場合は、2桁と2桁の間にハイフンが入る形式になる。変更の理由は、交通事故が急増したので、警察が見やすく、取り締まりがしやすいようにとのこと。
これらのことだけでなく、ナンバープレートについては、このサイトが詳しいので、興味のある方は参照のこと。
<99.08.28>