運勢の相対評価
朝のニュース番組には「今日の運勢」のようなコーナーを持つものが多い。
私が見ている番組では、星座別に順番をつける形式でやっている。
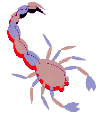
私は「蠍座」なのだが、どういうわけか12星座のうちの下位にランクされることが多いようだ(私が見るときに限って、そうなのかもしれないが)
「今日、一番悪い運勢の人は『蠍座』の人でーす!」などということもよくある。そういうときは他局の番組に切り替えてみる(同様の占いをやっているので)
それで全く別な結果が出ていれば、「ほーら、だから占いなんて信用しないほうがいいんだよ」ということで一件落着するのだが、切り替えた先の番組でも「最下位は『蠍座』です!」などということになると、「ガーン!」と暗い気持ちになる(^^;)
もちろん私は、それを頭から信じて、出勤を見合わせるほど占い等を信じているわけではない。あくまでも遊びのノリであるのだが‥‥
しかし、落ち着いて考えてみると、「なんかおかしいぞ‥‥」という気持ちになる。
「今日、一番良い運勢」とか「一番悪い」とかいっても、結局は相対評価でしかない。場合によっては今日の最下位だといっても昨日の第1位よりも運勢が良いということもあり得るわけだ。
また、12の星座にきちんと順番がつくのも、考えてみると不自然だ。プロ野球の順位争いではないが、同率首位で3つの星座がならぶということだってあっても不思議ではない。
私が購読しているスポーツ新聞にも占いの欄があるが、こちらはちょっと違った形式になっている。
星座ごとに、「金運・健康運・仕事運」などのチェック欄に「◎・○・△・×」の記号がついている。これだと他の星座の人の運勢の良し悪しに関係なく、今日の自分の運勢を知ることができる。
繰り返しになってくどいのだが、私は、そんなに運勢とか占いを信じているわけではない。あくまでも遊び心である(しつこいなぁ‥‥)
この違いは、放送であるテレビ番組と、印刷物である新聞という媒体の違いに起因するものなのだろう。
時間とともに流れ去っていく放送という媒体を使って、人の注意をひきつけるには、ランキングという相対評価形式が有効である。「1番良いのは○○、ビリは○○」という発表の仕方は印象が強烈だし、細かいデータうんぬんを紹介しなくても、なんとなく一発でわかったような気持ちにさせる。
これに対して、じっくりと時間をかけて読むことができる印刷物という媒体では、目先だけの派手さでは通用しない。(また運勢のハナシになってしまうが)どこがどのように良くて、何をどのようにしたらよいのかという正確で細かなデータを知らせることができるかどうかが勝負である。
「これって何かに似ている」と思われる教育関係者の方もいるかもしれない。
実は「通信簿」の評価がそうなのだ。
10数年前までの通信簿は、相対評価の評定を行っていた。いわゆる「5段階評価」である。
どんな教科でも優秀な成績を収める子を「オール5」などというのは、その頃のなごりである。(今の子供たちに「オール5」と言っても意味がわからないだろう)
私が教師になった頃は、このやり方で評定をしていた。これには分配率があり、次の表のようになっている。
評定の段階
|
割合(%)
|
5
|
7%
|
4
|
24%
|
3
|
38%
|
2
|
24%
|
1
|
7%
|
30人の学級だと、5と1は各2人程度、4と2が各7人、3が12人ということになる。
もちろん、当時も機械的に人数を割り振るということではなく、学習成果の実態に応じて、若干の人数修正は行っていたが、だいたいはこれが基準になっていた。
これだと、学級の中でどの程度の位置にいるのかということが把握しやすい。
しかし、この評定は、あくまでも学級という集団における成績順をもとにしたものであって、学級全体のレベルによって、個人に対する評定は変化する。
具体的にいうと、ほとんどの子が、テストの平均点が90点以上であるという学級ならば、75点をとった子は「2」という評定になることもある。その子が平均点が60点の学級に移ったならば、「5」や「4」という評定に変わることもありうる。(実際にはテストの成績だけで評価するのではないのだが、ここでは説明を簡単にするために、テストという例を使っている)
つまり、この5段階評定は、その子の絶対的な成績をあらわすのではなく、学級集団の中で上位なのか下位なのかということをあらわしていうのである。
これでは、前述のような問題があるため、最近では通信簿に相対的な評定を書くことをやめている学校がほとんどである。
では、どんな通信簿に変わったのかというと、スポーツ新聞の占い欄のように、細かい観点でその子の学習の達成度を絶対的なかたちで評価するようになったのである。
5段階評価型の通信簿の頃も、「観点別評価」と称して、「知識・理解」「表現力」「関心・意欲」などを「A・B・C」評価していたのだが、「知識・理解」というような総括的な観点では、子供の学習活動の具体的な姿が見えにくい。
そこで、最近では、「繰り上がりのある2桁の足し算ができる」というように、その時期の具体的な学習内容を明示した細かい観点をたくさん準備して、一つ一つについて「A・B・C」等の評価をするようになってきている。
私はこれまで、3つの学校で新形式の通信簿に切り替える場面に立ち会った。
通信簿を見る側の保護者からは、最初は「自分の子供の成績がわかりにくくなった」という声も聞かれた。しかし、次第に「うちの子供が、学習したことの何が身についていて、何がわかっていないかということが、きちんとわかるようになった」という好評の感想が増えてきた。
5段階での相対評価は、テレビの「今日の運勢ランキング」に似ている。
ぱっと見ただけで、「うちの子は、よその子よりも頭がいいようだ」とか、「どうも学級のどんじりの方にいるらしい」とかいうことはわかるのだが、そればかりに目を奪われて、「知識・理解の力は『A』だが、表現力は『B』だ」などというところを詳しく見ないでしまうということになりがちだ。
それに対して、今の通信簿の形式は、順位ランキング的な相対評価の評定をやめたために、かえって学級内の順位などにとらわれないで、子供の具体的な学習の状況をきちんと見ることができるようになったのではないか。
「割り算の筆算はちゃんとできるようだが、重さの単位についてはよくわかっていないようだ」というようなことを、保護者が把握できるようになったのだ。
そういう意味では、印刷物としての情報提供としては正しい方向に改善されてきたことになる。
ただ、もっと欲を言えば、それぞれの観点についての評価がもっと細分化されてもいいように思う。「A・B・C」程度の評価では具体的な姿が見えにくい。
◎:完全に身についている
○:ほぼ身についているが、間違うこともある
△:ある程度はわかっているが、まだ理解が不十分である
×:ほとんど身についていない
この程度の評価は必要であろう。
最近は「よさを認める通信簿」ということで、あまり子供を傷つけないようにし、積極的にほめることを主にした通信簿が主流になっている。
その考え方自体は、よいことであるが、「通信簿」というからには(今はそういう名称を使っている学校も少なくなったが)、教師が保護者に対して提供する資料という性格を持っている。やはり子供の実態を正確に伝えるということが必要であろう。
本来は「×」がつくような状態のまま、子供に対する学習指導を終えるということは許されないことである。したがって、十分な補充指導を行い、「×」ではない状態にしなければならないということで、意識的に「×」はつけないと教師もいるようだが、通信簿をつける時点でその子がまだ「×」の状態であるならば、事実は正確に伝えなければならないだろう。
「申し訳ございませんが、お宅の○○さんに、私は○○○のことをきちんと指導することができませんでした。そのために○○さんは○○○がほとんどできない状態です。今後、いろいろな方法で指導を続けていくつもりですが、今のところでは『X』をつけなければならない状態です。私も頑張って指導を続けますが、ご家庭でもこの実態をご理解いただいて、家庭学習などで力を伸ばしていくことができましたら、ご協力をよろしくお願いします」というような気持ちで、「×」をつけるということも必要であろう。
タイトルの「運勢の相対評価」からは、少し話がそれたかもしれないが、実は通信簿のことを言いたかったというわけである(^^;)
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ