エレベーターでリズム指導
耳から聞いて曲を歌えるようになるだけでなく、楽譜を見て歌えるようにさせたい。
音楽の授業をするときに、私はそう考えている。ところが、これがなかなか難しい。
ドレミ‥などの音階は鍵盤楽器等に頼れば絶対音感のない人でも(もちろん私もそうである。譜面を見ただけでちゃんとした音程を発声するというのは至難のワザである)なんとかできるはずである。ところがネックになるのがリズムのとり方である。譜面を見て、きちんとした音の長さをつかめる人は意外に少ない。
そこで、私が長年の経験(^^;)から編み出したのが、次の指導法である。実際にやってみるとかなり効果があるので、私は自分で音楽の授業を担任する場合、最初の授業で必ずこれを行っている。
まず、話のマクラとして、エレベーターのネタを持ってくる。
「病院のエレベーターは、亡くなった人を運ぶことも多いので、夜中に1人でそれに乗ってしまうと、背中に霊気を感じる」などという「怖いハナシ」あたりから入って、「都会では土地の値段が高いので、狭い土地しか買えない人は、1部屋が縦に何階も重なったような家しか造れない。その場合、4階あたりに老人が暮らすことになると階段の上り下りだけで疲労困憊してしまうし、階段のスペースで家の中がいっぱいになってしまうので、それを避けるために家庭用のエレベーターを設置する」などといういい加減なハナシをしながら、最大積載量が400kgという小さなエレベーターを無理矢理想像させる。(実際にこういう家庭用のエレベーターが製造されている)
これが、実は4分の4拍子の場合の、1小節の長さになるわけである。しかし、この時点では、まだそのハナシは出さないでおく。
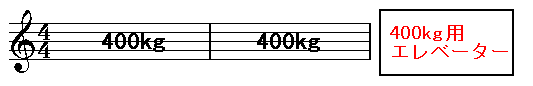
ここで、「こんなエレベーターがあったら、それにどのくらいの人が乗ることができるだろう?」と話をもっていくわけである。
そのときに、例として出すのが下の表である。
まず、基本形として、「かなりガッチリした体型のお父さん」を出す。この人の体重がちょうど100kgだとする。すると、子供たちは「4人乗れる!」という。
「じゃあ、相撲の曙とか武蔵丸あたりは、体重が200kgぐらいなんだけど、これだと何人乗れる?」と聞くのである。すぐに「2人!」という答が返ってくる。

|
世界最大のデブ
|
全音符
|
ターアーアーアー
|

|
お相撲さん
|
2分音符
|
ターアー
|

|
体格のいいお父さん
|
4分音符
|
タン
|
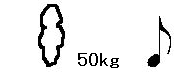
|
スマートなお母さん
|
8分音符
|
タ
|
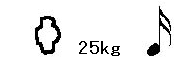
|
小さい子供
|
16分音符
|
ッ
|
さらに、「あまり太っていないお母さん」は体重が50kg、「小学校1年生ぐらいの小さな子供」は体重が25kg、「ギネスブックに載るような世界最高の体重の人」は400kgということで、このエレベーターに乗れる人数を確認する。(「世界最大のデブ」というのは、あまり教育的な言葉ではないが、語呂がいいのとインパクトがあるのとで、私はこう言っている)
これを一通りやったところで、「今までムダ話をしたと思っているかもしれないけど、実は音楽で大事なことを話していたんだよ」と言って、上の表のように、それぞれの音符と結びつけて、1小節にどれだけ入るかということや、音符の名称、音の長さについて整理するわけである。(^^;)
また、8分音符や16分音符には、「しっぽ」(正式には『旗』というらしい)がついているが、これを「手」に見立てて、「女の人や子供は、手をつなぎたがるので、隣に仲間がいると手を結び合っちゃうんだよ」と説明する。
さらに「このエレベーターは、ときどき真ん中のところでギロチンが落ちてくるので、真ん中にまたがるような音符の置き方(4分の4拍子の場合、4分音符・2分音符・4分音符のような並べ方)はしないほうがいいんだよ」ということまで説明すれば万全である。(そういう場合は、4分音符をタイでつないで2分音符の表現をするのが正しい記譜法)
そうして、エレベーターの最大積載量が400kgになるのは「4分の4拍子」の場合で、「4分の3拍子」では300kgだし、「4分の2拍子」だと200kgになるということも説明する。
ここで、リズム譜を見て、「タンタタ タタタン ターアーアー(ウン)」などと読めるようになれば、あとはそれに楽器で音程をつけるだけで、譜面を見て曲がわかるようになるという次第である。
あまり説明する知識の量が多くなりすぎるとわからなくなってしまうこともあるので、学年の実態に応じて話す内容を調整するのだが、こういった知識の指導も、ときには必要なように思う。
音楽の授業というと、小学校では、「あまり知識にこだわらず、とにかく楽しく歌わせたり演奏させたりして、音楽の喜びやよさを感じさせる」ということに力点が置かれていたと思う。小さい頃からピアノなどに慣れ親しんできた子供はそれでいいかもしれないが、あまりそういう環境で育たなかった(私のような)子供は、楽譜というものがいつまでたっても謎の世界で、音楽の授業が楽しくなくなるということもあるようだ。
ピアノ教室などに通っていた子供が、楽譜を見ただけで簡単に演奏ができるのに、自分は楽譜にカタカナで「ドレミ」を書かないと演奏できないなどということになると、疎外感を持ってしまう。
もともと音楽の構成というのは、かなり数学の世界に近いと思う。長調の音階の構成が「全・全・半・全・全・全・半」であることとか、和音の構成が根音に半音を4個・3個重ねるとよいとか、短調の和音は3度の音を半音下げればよいとかいうことも、数的に説明すれば、わりと簡単なことである。
小学校高学年くらいになれば、こういう説明を理解できる子供もかなり増えてくる(全員ではないが)。「算数は得意だけど、歌ったり楽器を演奏したりするのは苦手」という子供(男子に多いようだ)に、このような説明をしただけで、とたんに作曲などに開眼する子もいる(特にパソコンで音楽ソフトを使わせるとその傾向が強い)
小学校高学年や中学校で音楽の授業をやる方で、自分自身にもある程度、楽典の知識のある方は、こういった指導を試みても面白いのではないだろうか。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ