子供はあきない
この文章を書いている99年3月末時点で「だんご3兄弟」シングルCDの売り上げが300万枚を軽く突破とか‥‥。史上最高売り上げの「およげたいやき君」に迫る勢いである。
「だんご3兄弟」「およげたいやき君」の他にも、子供の歌には「黒ネコのタンゴ」などのヒットもあり、一度火がつくと大ブレークということがよくあるようだ。
レコード(CD)を欲しがるのが小学校入学前後の幼児なので、親が無理をしても入手しようとすることもあって大ヒットになるということもあるのだろうが、売り上げ枚数がとても大きな数になるのは、瞬間的なヒットではなく、かなり長い期間にわたって売れ続けるというのが大きな理由ではないかと思う。
成人(あるいは青少年)向けのヒット曲が、発売直後は突風のように売れ、数週間たつとピタリと売り上げが止まるのに対して、子供用の曲は数週間どころか数ヶ月、場合によっては数年間も売れ続ける。
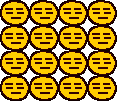
これは、子供が、なかなか飽きないということも関係しているようだ。
よく子供は飽きやすいなどと言うが、そんなことはない。たしかに1つのことを長く続けるという集中力はないのだが、1つのものをいつまでも好み続けるという点では、大人よりもずっと「飽きない」といえるだろう。
お気に入りのぬいぐるみを何年間も大事にしたり、大好きな絵本を何百回となく見るなどというのは、子供にはよくあることだ。
ずっと前に聞いた話だが、知的障害の子たちの特殊学級の担任が、出張の時に、補充してくれる先生に「○時間目はビデオを見せておいてください」と頼んだのだそうだ。
そこで、頼まれた先生は教室に出かけて行き、ビデオを見せようとして、「このビデオ、見たことある?」と聞いた。子供たちが「見たことあるよ」と言うので、「それじゃあ、別のを見せてあげよう」と、自分が持っていた別なアニメのビデオを見せたのだそうだ。
ところが子供たちはちっとも面白そうな顔をしない。しかたなく担任から預けられたビデオを見せてみると、今度は楽しい場面になる前から期待に顔を輝かせ、その場面になると手をたたいて喜んで見たということである。
これは特殊学級に限ったことではなく、小さな子供にはよく見られることだ。
私の家でも、小さい娘のリクエストで、何十回となくディズニーのビデオを見せられている(^^;)
子供が同じものを何度も見たりするといっても、それが何でもよいということはないようだ。気に入らないものは数分もしないうちに見ることをやめてしまう。何度も繰り返し見ることができるのは、本当に気に入った限られたものだけである。
結局、それが「好きだ」ということなのかもしれない。
それを見ることで「快い感覚」を得ることができるので、その感覚を求めて何度でも見ようとする。これは、大人が刺激や新しい情報を求めて次々と別なものに触れようとするのとは、だいぶ違った態度である。
考えてみれば、大人にもこれと似たことがある。
音楽などは、そうかもしれない。
若い頃、よくロックやポップスのレコードを買ったが、買ったばかりのうちは「これはすごい!」などと思っても、すぐに飽きてしまうものもあったし、反対に最初はそれほど良いとも思わないのに、聴き込むうちに次第に良さがわかってくるものもあった。
聴くレコードだけでなく、何度歌っても気持ちの良い曲もあるし、ストーリーはわかっていても何度も読み味わいたい小説もある。
何度繰り返しても飽きることがなく、その度に気持ちがよいものこそが、本当に良いものなのだろう。
大人も本当に良いものを見つけることはできるのだが、流行や、マスコミの情報、目が眩むような刺激などに影響される機会が多いことと、1つのものをじっくり味わう時間的な余裕がないこともあって、本物を見失いがちになっているのかもしれない。
その点では、新聞も読めないような小さな子供たちの間から人気が出てくるような「子供の歌」というのは、本物が多いように思う。
どんなに長い時間いっしょにいても飽きないし、いっしょにいると快い、もっともっと長い時間いっしょにいたいと思うという、人間どうしの感情、これも「好き」ということなのだろう。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る うんちく目次へ
うんちく目次へ