大学ノートと近視
小学生は、マス目や形式が工夫された「教科別ノート」を使うことが多いが、中学生ぐらいになると、いわゆる「大学ノート」と呼ばれる横罫のノートを使うことが多い。
中学生や高校生が使っても「大学ノート」とは、おかしな感じがしないでもないが(^^;)その歴史について書いている本を見つけた。(佐藤秀夫著「学校ことはじめ事典」小学館発行)
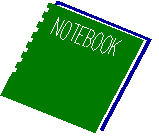
この「大学」とは、東京大学のことらしい。
それについて書く前に、前述の本から、筆記用紙の歴史を簡単にまとめてみよう。
書きつけることを目的として、白紙をあらかじめ綴じ合わせておくというのは、紙が大量に生産されるようになってからののことで、それ以前は、書きつけた紙を保存するために、あとで綴じ合わせるのが一般的だった。現存する日本最古の大福帳は17世紀初頭のものだが、それは自家製で、商品として大福帳が販売されるようになったのは18世紀中頃からだという。和紙を用いた日本特有のノートである。
紙の歴史が浅く、しかも油性インクを使っての印刷用紙としてもっぱら作られたヨーロッパの場合、紙の表面に鉱物質の粉末をこすりつけて(サイジングという)、水性インクによる筆記を可能にした紙が出まわるのは19世紀になってからのことである。フランス革命期においても、メモには鑞版(ろうばん)が用いられていたという。
19世紀前半にイギリスを中心に、サイジングされた良質の筆記用紙が大量に工場生産されるようになり、海外にも輸出されるようになった。それが、留学した日本の学者や学生によって、1880年代の日本にもらたされるようになる。
大学ノートが誕生したのは、この頃のことである。
1885(明治18)年、本郷赤門前の洋書屋が留学帰りの教授にすすめられて、輸入筆記用紙を綴じ合わせたノートを、東京大学の学生用に売り出したのが最初と言われているのだそうだ。
神田の丸善がその評判を聞きつけて、イギリス製筆記用紙を特別注文で大量に輸入してノートを生産し、「大学ノート」の名で売り出したのが、その名称のきっかけになったとされている。
これが「大学ノート」の名称の由来なのだが、ここで注目しなければならないのが、日本で生産・印刷した紙を使ったのではなく、輸入筆記用紙をそのまま使ったという点だ。
大学ノートの紙に印刷されている横罫線は、もともと欧文のアルファベット文字を記入するために引かれたものだったのである。
ご存じの通り、アルファベットは単純なかたちをしている。「うんちく講座」のNo.176「横10本・縦10本」にも書いたように、パソコンの画面に表示するとき縦横それぞれ8ドットもあれば表現できるような簡単なかたちである。
それに対して日本語の文字、特に漢字は、横の線や縦の線が10本もある漢字があるように、とても複雑なかたちをしている。
これをきちんとしたかたちで書こうとするならば、かなり大きく書かなければならないのだ。それをアルファベットを書くための用紙に書こうとするのだから、本来は無理があるのだが、勤勉実直な日本人は頑張って小さな文字を書く努力を始めた。
古くからの筆記具である毛筆では無理なのだが、ペンや鉛筆を使えば、小さな文字も書けないことはない。ちょうどそれらの筆記具も普及し始めた頃だったので、アルファベットなみの大きさで漢字を書くということもできるようになっていたのである。
大学ノートが使われるようになったのと時を同じくして、日本では「小さな文字を書く」ということが始まったのである。
日本人のイメージとして「眼鏡」があげられるが、日本人に近視が多いのは、このことも影響しているのではないかと、私は考える。
時代劇などによく出てくるシーンに、手紙や和歌等を書くときに、巻紙や短冊を左手に持ち、筆を軽く持って、さらさらと書くのがある。
これが、もともとの日本人の筆記スタイルだったのではないだろうか。
これだと近視にはならないだろう。また、江戸時代までに書かれたものを見ると、どれも大きな文字で書かれている。
まるで紙に文字を刻み込むように、かりかりと小さな文字を書くようになったのは、大学ノートが普及してからのことなのだろう。
これによって、書く姿勢が悪くなった。
毛筆で大きな文字を書く場合には、背筋を伸ばし、書いている文字に対して顔を正対させるのが基本なのだが、小さい文字を書く場合には、これだと書いている文字が見えにくいのである。
そこで、(右利きの場合)、体を左に傾け、右手で握ったペンの先を下からのぞき込むような姿勢をとらざるを得なくなった。自然、紙に目を近づけることになるし、左右の目からの距離も同じではないので、こういう作業を長時間続けた場合、目に悪影響を与えることになる。
欧文を書く場合も同じではないかと思われるかもしれないが、こちらは手が横に動いていくスピードが速いし、漢字を小さい字で書くときのような細かい動きが必要でないため、あまり顔を近づける必要がないようだ。
下の図は、鉛筆の正しい持ち方である。ある資料によると、日本人の中で、きちんとこの持ち方ができる人は10%に満たないのだそうだが、このような正しい持ち方をしたとしても、やはり手元の文字は見にくい。
このように手を机面にのせて書く方法を「堤腕法(ていわんほう)」という。欧文や小さい文字を書くときに使う方法なのだが、日本の文字は、本来は手やひじを机にのせないで、机面と平行になるように持ち上げて書く「懸腕法(けんわんほう)」で書くのが向いている文字なのだ。
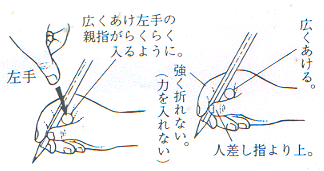
まあ、それでも、このような正しい鉛筆の持ち方をすれば、背筋を伸ばした姿勢であっても、ある程度は鉛筆の先(文字を書いている部分)が見えるのだが、最近はシャープペンシルやボールペンなどの筆記具を使うことが多いため、上の図よりも人差し指からペン先までの長さを短くして持つ傾向がある。
上のような持ち方だと、シャープペンシルの場合は芯が折れやすいし、ボールペンの場合は直立気味に持たないとボールがうまく転がらないのだ。
したがって、、書く姿勢はいっそう悪くなり、視力低下の原因にもなっている。
ちなみに、下の図が、毛筆を使って懸腕法で大きな文字を書くときの持ち方である。これだと指先から筆先までの距離がかなりあるし、書く文字自体が大きいので、書いている文字が手のかげになって見えないということはない。
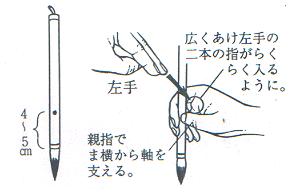
ついでに、おまけの知識だが、懸腕法で筆を持つときに、人差し指だけを前に出す「単鉤法(たんこうほう)」と、人差し指と中指の2本を前に出す「双鉤法(そうこうほう)」がある。(下図参照)
小学校の書写の時間では、「双鉤法」を基本のかたちとして指導している。
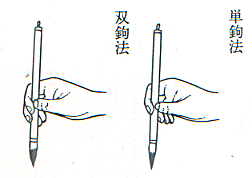
話を大学ノートに戻そう。
罫線の幅によって3つの規格があり、一般的なサイズ(B5判)では、罫線の幅と行数は次の表のようになっている。
A罫
|
7mm幅、31行
|
B罫
|
6mm幅、35行
|
U罫
|
9mm幅、30行
|
1ページにたくさんの内容を書き込むために、B罫を使っている生徒・学生も多いが、6mm幅では漢字を書くにはいかにも苦しい。できれば1cm程度は欲しいところだが、まあ9mm幅のU罫あたりなら許容範囲だろう。どうしてもB罫を使いたい場合は、1行あけで書くのが良いように思える。
日本語の文字を正しく無理なく書くには、本当は原稿用紙のマス目程度の大きさがちょうどよいのだ。これは小学校中学年用の「国語」のノートの規格である。
1枚のページにたくさんの情報量を詰め込もうとする場合は大学ノートが向いているかも知れないが、今ならワープロで印字したほうが、より見やすく、多くの情報を扱える。
自分の考えを書きながらまとめるなどという場合には、気持ちよくすらすらと書けることが大事になる。そんなときには、「大学ノート」ではなく、「小学ノート」を使ってみるのもよいかもしれない。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ