正しいマイクの握り方
講堂や体育館などでマイクを使って音声を拡大するときに、ハウリングという現象が起きることがある。
「howling」と書き、「howl」(犬や狼などが吠える)が語源なのだが、スピーカーから出た音がマイクでひろわれ、これが繰り返されて、特定の周波数で共振が起き、「ウォーン」とか「キーン」という音が発生する現象のことをいう。
スピーカーの出力を上げ過ぎたり、マイクの入力を上げ過ぎたりすると起き、かなり耳障りなので嫌がられる。
コンサート会場や講演会などでは、こういった現象が起きないように、使用するマイクは「単一指向性」マイクという種類のものを使うことが多い。
下の図が、「単一指向性マイク」と「無指向性マイク」の構造図である。
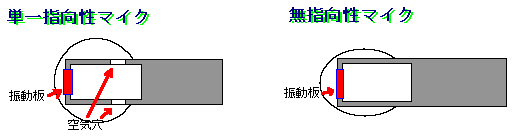
無指向性マイクは、拡声装置としてではなく、録音装置に使われることが多い。
この場合は、マイクからひろった音をスピーカーを使って外部に出すことがないので、周囲の音を全てひろうことができるような構造になっている。どんな方向からのどんな小さな音もひろうことができる方が録音にも向いているのである。
これに対して「単一指向性マイク」は、正面から入る大きな音だけをひろうような構造になっている。
上の図をご覧いただけばわかるが、このマイクには後側面に空気穴が開いている。これによって、会場全体に響いているような音は、正面からと空気穴からと同時に入るので、音を拾う部分である「振動板」をプラスの方向とマイナスの方向に同じ大きさで振動させようとするため、結果的には振動板を動かさないということになるのである。
振動板に対して正面から強く吹き込まれた音(歌声や話し声など)は、空気穴側から入る音量と正面からの音量の差が大きいので、その音だけが振動板を動かすことになり、結果的には正面からの強い音だけをひろうマイクになるというわけである。
したがって、単一指向性マイクを効果的に使うためには、空気穴をふさがないことが大切である。

上の図が、「単一指向性マイク」の正しい持ち方と悪い持ち方の例である。
ハウリングを起こさないようにするためには、空気穴をふさがないように、左のような持ち方をしなくてはならない。
よく、ハウリングが起きると、「周囲からの音を拾いすぎたせいだ」と思って(それ自体は正しい考え方なのだが)、「なるべく音をひろわないように」と考えるのか、手のひらでマイクを包み込むような(右のような)持ち方をする人を見かけるが、結果的には空気穴をふさぐことになってしまい、無指向性のマイクと同じようになるので逆効果である。
ハウリングが起きてしまった場合、拡声装置のミキサーを操作してくれる人が、音量を下げてくれればそれでよいのだが、あいにく誰もミキサーを操作してくれていない場合などは、マイクの持ち方を正しくして、スピーカーの方向にマイクを向けないようにし、なるべくスピーカーから離れるのが正しい対応である。マイクに「ON−OFF」スイッチがついているのなら(高級マイクにはついていないことが多いが)、一度、スイッチを「OFF」にするのがよい。(コンサートで歌っている場合などはそれもできないが‥‥)
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ