生は生でも
中学校や高校の先生は、学校の子供たちのことを「生徒」と呼ぶ。小学校では「生徒」ではなく「児童」と呼ぶ。
だから、小学校に来て「この学校の生徒たちは‥‥」などと言う人がいると、「おっ、この人は中・高の先生だな」とか、「ははあ、この人は学校教育のことをよく知らないな」などと感じてしまう。
これが大学になると「生徒」とは言わずに「学生」になる。学校で学ぶという立場は同じなのにこのように使い分けなければならないというのは、ちょいと難しい。(漢字文化圏の国で使い分けているのは日本だけなのだそうだが)
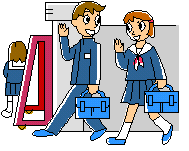
ところで、「生徒」でも「学生」でも、同じ「生」という漢字が使われているのだが、見た目は同じようであっても、全く別の意味で使われているのだそうだ。
「生徒」の場合は、あまり良い意味で「生」という字が使われていない。
「生徒」は後漢の時代から「教えをうけるもの」という意味で使われているのだそうだが、元来は「生」と「徒」の複合語だという。
「徒」は弟子をさし、その上につく「生」には「未熟」という意味があるのだそうだ。「生徒」となると「未熟な弟子」ということになる。
これに対し、「学生」の下につく「生」は、「書生」などのように、読書人の謙称だということである。山田さんが自分のことを「山田生」などというのと同じ使い方だ。
したがって、「学生」の方が「生徒」よりかなり高級な意味を持つ言葉ということになる。
韓国や朝鮮では、学校で学ぶ人を全て「学生」と呼び、中国では「学員」または「学生」と呼ぶそうだ。
日本でも、明治初期には全て「生徒」と呼んでいたのだそうだが、1880年代になって、東京大学で「本科生徒」に限って「学生」と呼ぶようになり、以降は大学生を「学生」と総称するようになったという。
ついで、1890年代後半に、小学校について法制上の表現として「児童」が登場するようになり、1900年の第3次「小学校令」によって定着したのだという。
こうして、「生徒」の中から上と下が分離し、正規の「学生」資格を持たないもの(中等学校・師範学校・旧制高校・旧制専門学校・大学の別科生や研究生・聴講生など)で、「児童」よりも年長のもの全てが「生徒」と呼ばれるようになった。
1920年代に入って幼稚園が普及すると、そこで学ぶ子供は「幼児」と称されるようになった。
学生と生徒を合わせたかたちで「学徒」という呼び方をしたり、学校で学ぶ児童と児童一般とを区別する意味で「学童」という言葉が使われることもある。
また、最近では大学院の学生を特別に「院生」と呼ぶこともあるようだ。
まあ、言葉の本来の意味はどうであっても、それはそれでひとつの記号のようなものだから、あまり細かいことを気にすることはないのだが、「生徒」という言葉が、もともとはあまり子供の人権を尊重した言い方ではないということは、覚えておいてもよいかもしれない。
えっ? 「生母」はどうなるのかって?
うーん、「未熟な母」というわけではないと思うけど‥‥(^^;)
参考文献:「学校ことはじめ事典」(佐藤秀夫著・小学館発行)
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ