教え子
年賀状を整理するときにデータベースソフトを使っている。そのときに「友人」とか「親類」・「同僚」などという分類のしかたをしているのだが、前に担任として受け持っていた子供たちについては「教え子」として分類している。
この「教え子」という言葉、使っていてちょっと抵抗がある。
前に、「教師は自分の受け持った子供たちを『教え子』などと呼ぶべきではない」という文章を読んだこともあるし、インターネット上の文章の中にも「教え子(この言葉にはちょっと抵抗があるのですが)から年賀状をもらいました」というような表現を見かけることも多い。
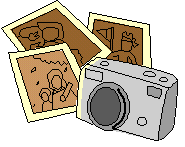
たしかに「あの子は私の教え子でね」などと言うのは、ちょっと尊大な感じもする。教師が自分でそう言うのはあまり良い言い方とは言えないだろう。
私の場合、自分が教えていただいた先生方をは「恩師」と読んでいる。前述のデータベースでもそのように分類している。だから私自身のことを表現する場合は、「私は○○先生の教え子です」と言っている。このことについては、全く抵抗がない。
しかし、自分のことを「私は○○君の恩師です」と言うことはありえない。
「教え子」も「恩師」も、言う人・言われる人の立場によって、適切な表現であったり、そうでなかっったりするのだろう。ここでちょっと整理してみたのが下の表である。
教え子と呼んでいいか?
|
教師が子供を
|
第三者が子供を
|
子供が自分を
|
?
|
教え子
|
教え子
|
恩師と呼んでいいか?
|
教師が自分を
|
第三者が教師を
|
子供が教師を
|
×
|
恩師
|
恩師
|
これでおわかりのように、「教え子」とか「恩師」というのは、本来は教えられる子供(あるいは子供だった人)が、自分を一段下げていうときの言葉である。師弟の関係に直接関係のない第三者がそういうことも許容範囲であろう。
ただ、教師本人がいうべき言葉ではないようだ。
「教え子」という言葉は、かなり古くから使われているようである。あまり詳しく調べたわけではないが、小学館「日本国語大辞典」によると、その用例として、江戸時代中期、本居宣長の随筆集「玉勝間」の中の「わがをしえ子にいましめおくやう」という文があげられている。
ただ、この本居宣長の一文からは、「教え子」という言葉に対しての彼の意識が感じられる。
この場合、「教え子」というのは、自分の「子」と同じなのである。「教える」ということによって親子のように身内の関係になっているのだ。自分の子供を「愚息」などと表現することがあるが、それに近い感じもする。だとすれば、あえて尊称を用いる必要はないのだから「教え子」でもおかしくはない。
ある意味では、こういう意識は必要なのかもしれない。
最近では、「教師が一方的に上から指示したり教えたりするという『指導』ではなく、子供と同じ高さに立って学習を助けてやるという『支援』という発想が大切である」という考え方が普及してきている。
これも大切なことではある。しかし、それはあくまでも「指導法」に関してであって、教師と子供の意識までが同等のレベルに立つべきだというものではないと思う。
教師がヒゲをはやして壇上に立ち、子供はかしこまって教師の言葉を聞くという上下関係ではなく、学級の子供を自分の子と同じように大事に思い、ときには子供のそばで肩を抱いて(あくまでも例えだが)親身に教えるという意識をなくしてはいけないと思う。
言いかえると、子供の立場を教師と同じレベルまで上げる発想の「支援」と、教師の立場を子供と同じレベルまで下げる「教え子」という2つの発想を持ってこそ成立するのが「指導」ではないかと思うのだ。
そう考えると「教え子」という言葉は、けっこう味わい深いものに思えてくる。
「指導」「教授」「授業」など、教育関係の用語は、「上から与える・授ける・教えてやる」といったニュアンスが強いものが多い。
そのため、「支援」の例のように、「今の考え方に合わない」ということで言いかえられる言葉も出てきた。しかし、古い言葉にも味わうべき意味を持っているものが多い。単に言葉の上での言いかえですませるのではなく、本質を考えた上で、きちんと使い分けていくことが大切だと思う。「指導」と言っただけで、「それは古い!」などと批判する傾向こそ警戒しなければならない。
最後に本題に戻ってしまうのだが、「教え子」にかわるべき言葉がないので困っている。「いわゆる『教え子』」では具合が悪い。「受け持った子供たち」でもすっきりしない。
私もいろいろ考えてみようとは思うのだが、どなたか、「こんな言葉がいいですよ」というものがあったら、教えていただきたい。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ