地層的名前・地理的名前
ずっと前に担任した学級で、名前に「博」という文字がつく子が多かったことがある。「博孝」とか「一博」とか「国博」とかいう具合である。
調べてみたら、その学年は昭和45年生まれの子たちの学年であった。
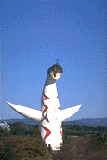
昭和45(1970)年といえば、3月〜9月に、大阪で万国博覧会が開かれた年。
それを記念して、我が子の名前に「博」という文字を入れた人が多かったのだろう。「国博」という名前だと、見事に2文字も入っている。
これに似たような例はたくさんあるようだ。
ちょっとローカルな話題になるが、私の住んでいる「由利町」は、昭和30年3月に、「東滝沢村」「西滝沢村」「鮎川村」が合併して「由利村」になった。私は昭和29年生まれなのだが、私と同じ学年と1つ下の学年には「由利子」さんがたくさんいる。
「今年多かった名前」というのが毎年発表される。平成10年のトップは、男の子が「大輝」クン、女の子が「萌」ちゃんということだ。
上位になる名前は例年似たような傾向があるそうだが、ふだんあまり上位にならないような名前が突然上位になるような場合もある。それらの場合、ほとんどはその年に起きた社会現象がもとになっていることが多いようだ。
前述した2つの例は、それにあたる。ちょうど地層が、火山の噴火や土地の隆起・陥没などで、層の境目がつくられるのに似ていると思う。そこで、私は、こういう名前を「地層的名前」と(勝手に)命名した(^^;)
突然の出来事などがもとになっている場合は1年限りの現象として残る場合もあるし、前述の町村合併の例のように、あらかじめそれがあるのが分かっている場合は、出来事の前後数年にわたる場合もあるようだ。
私の同級生にも数人いるのだが「秀樹」という名前は、昭和24(1949)年にノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士に由来しているようだ。このように立派な人の名前にあやかるという場合には、1年限りの現象でなく、その出来事(この場合は博士のノーベル賞受賞)の数年後まで影響する場合も多い。
「亜希子」さんという名前の子が3人もいる学級を受け持ったこともある。これはどうも、長嶋茂雄氏(現巨人軍監督)の奥さんの名前が関係しているようだ。長嶋氏の結婚が昭和40年1月で、この子たちの生まれが昭和48年なので、直接的な関係はないのだが、この子たちの父親が3人とも熱烈な巨人ファンというのが関係しているらしい。これも広い意味では「地層的名前」かもしれない(^^;)
個人の名前だと姓まで変えることはできないので、氏名全体で何かを表現するというのは難しいが、本名に関係なく氏名を考えることができる芸名だと、かなり大胆な名前にすることもできる。
この場合は「地層的」というのではなく、もろに「地理的名前」というのがある。具体的には、その人の出身地の地名などに因んだ名前にするというやりかただ。
西城秀樹・郷ひろみとともに「新御三家」と呼ばれた「野口五郎」(「青いリンゴ」「私鉄沿線」などのヒット曲があった)は代表的だ。
北アルプスの長野・富山県境に、「野口五郎岳」という高峰がある。彼の場合は、それをそのまま芸名にしたわけだ。
これもローカル(マイナー?)な話になるのだが、私の住む「由利町」から女性演歌歌手がデビューしたことがあった。あまり売れなかったようで、全国的には全く知られていないと思うが、彼女の芸名が「本荘由利」!!
私の住む地域をまとめて「本荘市由利郡」と呼び、通称「本荘由利」地域と呼んでいるのだが、彼女の芸名は、そのものズバリであった(^^;)
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ