研究紀要を私的に使う
研究機関などもそうだろうが、学校でも年に一度は「研究紀要」というものを出しているところが多いと思う。
学校の研究テーマに基づいて、1年間に行った研究実践を論文にまとめて冊子にして発行するというものである。
○○大学教育学部附属○○学校などという、研究の先進校の研究紀要などは、研究テーマも先進的だし、授業実践も充実しているので、お金を出して買っても価値があるような研究紀要(実際に販売していることが多い)を出しているが、そんなに大げさなものでなくても、どんな小さな学校でも、年間の研究のまとめとして「研究紀要」を作成している(はずである)
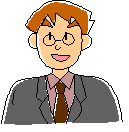
これを作るのは学校の先生たちである。校内の教科部(国語部とか社会科部など)で1つの論文をまとめる場合もあるだろうが、多くは個人ごとに自分の研究をまとめた論文を書くことが多いのではないだろうか。
論文をまとめるのは、冬休みから3学期のはじめにかけてである。
まあ、学校の教師にとっては、冬休みの宿題のようなものである。宿題というと気が重くなるものだが、私も研究紀要の原稿をまとめるのが、かなり苦痛に思えたときもあった。「研究紀要を書かなくてもよければ、もっとゆっくり正月気分にひたれるのに‥‥」という気持ちになったこともある。
ところが、ちょっと考え方を変えてから、積極的に研究紀要の原稿をまとめようとする気になったのである。
「こんなやり方をしたら、子供の力が伸びるのではないか」と、様々な工夫をし、資料や教具なども十分に準備して、自分が考えた方法で学習指導に取り組むことが、年に何回かある。学校全体の研究計画のもとに行う研究授業というかたちで行うこともあるし、全く自主的に取り組んでみることもある。
そのときの授業の指導案や学習資料、子供の学習成果、参観してくれた先生たちの話し合いの記録など、保存しておけば、その後の学習指導の際に、とても参考になる。
ところが、そういった資料や記録は、授業直後には大量にあるのだが、年がたつと次第に散逸してしまい、いざ必要となったときには、どこにしまっておいたかわからなくなってしまうということも多い。(余談になるかもしれないが、そういう資料は市販のファイルボックスに全て放り込んで、棚に並べて置くのが最良の整理法なようだ)
自分で資料を整理して保存するのが苦手な私は、研究紀要を資料散逸防止のために使ってしまおうと考えた。ちゃんと製本されたものならば、整理と保管がとても楽になるのである。
印刷屋さんに頼んでタイプ打ちをしてもらうやり方の研究紀要だと、教師1人あたりに与えられるページ数は2ページとか4ページとかで少なくなってしまうが、この頃はワープロ等も普及し、校内印刷の技術も進んだので、自分でワープロ打ちした印刷原版を作れば、何ページの原稿にしてもよいという学校も増えてきたように思う。(製本の関係で偶数ページになるようにという指示がある場合もあるが)
そこで、できるだけたくさんの資料を、研究紀要の原稿としてぶち込んで(おっと、品のない言葉で失礼)しまうのである。指導案はもちろん、子供の書いたものなども縮小コピーして原稿に入れる。授業後の研究会の話し合いの記録なども、自分で「これは残しておいたほうがよい」と思うものは全部書いてしまう。写真なども良い資料になる。
1人で数十ページになってしまうと、さすがに「おいおい」と言われるが、苦情が出ない程度に、研究紀要のページを独占してしまう。
もちろん、ただ指導案や学習資料のコピーを集めただけでは、見てくれる人にとっても迷惑だし、あとで自分が見なおしたときにもわからないので、「何をめざして、何をやろうとして、どんな手だてをとって、結果はどうだったのか」ということを筋道立てて論文にする。コピーした資料は、それを具体的に示すためのものとして扱う。
こういうつもりで取り組むと、研究紀要の原稿をまとめることは、ちっとも苦にならない。研究主任の先生から「少なくても4ページ以上でまとめてください」と言われて、そのページ数を満たす文章が書けずにため息をつくこともなくなる。かえって「何ページまでなら使っていいですか?」と聞くような態度になってくる。
こうやって出来上がった研究紀要は、年度順に並べておけば、必要になったときに書架から取り出して見るだけで、すぐに使える資料になる。もっと完璧をめざしたい人は、自分の書いたページだけをコピーしてファイルに綴じておけば、自分の教師としての歩みを振り返ることのできる記録になる。
せっかくお金をかけて作ってくれる研究紀要である。また、自分の時間をたくさん費やして作る研究紀要でもある。他人に見せるためではなく、自分に役立つものとして使わないという手はない。自分にとっては「自分ひとりのためだけの研究紀要」という意識で書くのもよいことではないかと思う。そしてそういう論文が集まった研究紀要こそ、学校全体の研究テーマをより深めるものになるはずだし、面白くてパワーのある研究紀要になると思う。
これもまた余談だが、せっかく書いた原稿なのだから、それをHTML文書化して、ホームページで公開するなどという方法も、これからは面白いかもしれない。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ