ABたてよこ
「ガマの油売り」の口上に次のような一節がある。
さて、お立ち会い。ここに取り出したるは、天下の名刀。抜けば玉散る氷の刃。
これにて1枚の紙を切ってご覧にいれまする。
ハイッ! 1枚が2枚、2枚が4枚、4枚が8枚、8枚が16枚‥‥‥
という具合に細かく切っていき、最後は紙吹雪‥‥となるのだが、この紙、どんどん半分にしていっても、大きさは変わるが、形そのものは変わらない。
西洋紙や画用紙などの紙を扱ったことのある人はわかると思うが、これらの紙は、ちょうど半分の大きさに折ると、大きさは半分になるが、縦横の比率は下の図のように変わらない。
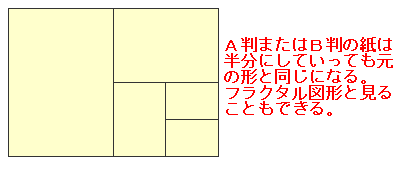
当たり前のことのようにも思えるが、よくよく考えてみると、これは不思議なことである。
もし、縦が10cm、横が20cmであったら、横半分に折ると1辺が10cmの正方形になってしまい、形が変わるということになる。
どんなに半分に切っていっても縦横比が変わらない形となると、ある微妙な比率をもった「ただ1つの形」ということになる。
それは、どんな比率なのだろうか?
これは、そんなに難しい問題ではない。中学生程度の数学の力があれば簡単に解くことができる。
その回答例(^^;)は下の通りである。
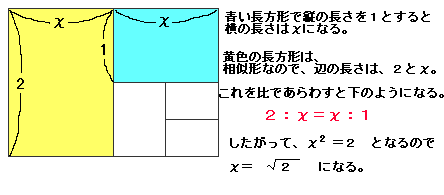
つまり、縦横比は「 1 : 1.41421356‥‥(2の平方根)」となる。
平方根などというと、あまり生活には関係のない数のようにも思えるが、こんな目に見えるところに登場していたわけである。
日常、よく使われている紙のサイズには、A判とB判がある。「A4サイズ」とか「B4の画用紙」などというあれである。
AとかBとかいう呼び方は違っていても、どちらも縦横比は同じである。つまり相似形であるということだ。
どちらも大きさによって「0判」から「12判」までの規格が決まっている。それを一覧表にしてみた。
A判
|
大きさ(mm)
|
|
B判
|
大きさ(mm)
|
0
|
841×1189
|
|
0
|
1030×1456
|
1
|
594× 841
|
|
1
|
728×1030
|
2
|
420× 594
|
|
2
|
515× 728
|
3
|
297× 420
|
|
3
|
364× 515
|
4
|
210× 297
|
|
4
|
257× 364
|
5
|
148× 210
|
|
5
|
182× 257
|
6
|
105× 148
|
|
6
|
128× 182
|
7
|
74× 105
|
|
7
|
91× 128
|
8
|
52× 74
|
|
8
|
64× 91
|
9
|
37× 52
|
|
9
|
45× 64
|
10
|
26× 37
|
|
10
|
32× 45
|
11
|
18× 26
|
|
11
|
22× 32
|
12
|
13× 18
|
|
12
|
16× 22
|
この表を注意深く見ていただければ、左上の数値(縦)が、1つ下のサイズの右の数値(横)になっているし、右上の数値(横)が、ちょうど半分になって下の左の数値(縦)になっていることがわかるだろう。
まあ、実際には半分折りにしたのだから、当然なのであるが‥‥
では、A判・B判のそれぞれの基準となる「0(ゼロ)判」の縦横サイズは、どうやって決められたのであろうか?
試しに、縦横のサイズをかけ算していただきたい。
A判の場合は「841×1189」となり「999949」となる。B判では「1030×1456」で「1499680」である。
実は、それぞれ「0(ゼロ)判」のサイズ(面積)が、A判の場合は「1㎡」、B判の場合は「1.5㎡」になるように設定されていたのである。これも初歩の数学で求められる数値ではあるが、数的には実に美しい数値になっている。
これは洋紙の規格なのだが、日本で従来から普及していた和紙の「菊判・四六判」もこれとほぼ同じ比率、同じサイズであることを見ると、人間の規格感というのは、洋の東西を問わないものらしい。
学校現場では長い間「B判」が基本的な紙のサイズであった。ちょっと大きなサイズを必要とする場合はB4判を使用し、小さな印刷物ではB5判を使うことが多かった。
学習ノートや教科書などのサイズも、ほとんどこれが基本になっていたし、教師用の棚のサイズや、児童生徒用の教室の机のサイズもこれに合ったものになっていた。
ところが、一般官庁に合わせるためか、ここ数年は、A判を使うことが多くなってきた。
文書等を綴じておくファイルも、これまではB5(182×257)判用を使っていたのだが、これに1枚でもA4(210×297)判が入ると、うまく整理できなくなる。しかたないのでA4判用のファイルにかえることになる。
すると、それらのファイルを入れる棚の大きさも変えなければならなくなる。棚だけでなく、バインダや封筒の大きさなど、いろいろなものに影響が出てきた。校内で印刷する文書類は、まだB判が多いのだが、児童生徒用の冊子(教科書や学習ノート類)がA判に変わってきているので、教室の学習机の机面の広さも現在のままでは狭い状態になってきた(教科書とノートを広げておくだけの広さがない)
仮に机のサイズを大きくしたとすれば、今度は教室の大きさが足りなくなってくる。これに対応するには、教室を作りなおすか、学級の定員を減らすしかない。(子供の体も大きくなってきているので、それもよいかもしれない)
たかが紙の大きさというかもしれないが、このように周りの環境全てを変えていかないといけないような影響力を持っている。文具メーカーや事務用品メーカーにとっては、新規格の商品が売れることになって好都合なのだろうが、棚やファイルの大きさを変えなければならない現場にとっては、大変な出費になる。
私個人の感覚としては、無理してA判に切り替えなくても、これまで使ってきたB判で十分だと思うのだが‥‥
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ