さしぼ

秋田県(の中でも私の住む本荘由利地域に限られているというハナシもあるが)の春の食卓を飾る野草に「さしぼ」がある。
秋田県では名詞の最後に「こ」をつける習慣もあり、私の地域では、「さしぼこ」と呼んでいる。
右がその写真である。
これをゆでて、おひたしにし、醤油やマヨネーズをかけて食べる。
味噌汁の実にすることもある。
独特の酸味、苦味、ぬめりなどがあり、慣れない人には気持ちが悪いかもしれないが、食べ慣れた人に言わせると、これを食べないと春が来た気がしないともいう。私も大好きである。

正式には、この「さしぼ」は、タデ科の大形多年草「イタドリ」の幼茎であるという。
右の2枚目の写真が、その生えている様子である。
これは近くの川原の堤防で撮ったものだが、日当たりのよい南側の場所に生えていることが多いようだ。
 成長すると左の写真のようになる。
成長すると左の写真のようになる。
こうなると高さは1mにもなり、茎も固くなって、とても食べられるものではない。
「さしぼ」として食用になるのは、地面から芽が出てからの、ほんのわずかな期間である。
「イタドリ」そのものは、漢方として使われ、その根茎は「虎杖根」と呼ばれているそうで、痛みを取り去ることから「イタドリ」と呼ばれるようになったという説もある。
事典等をみると、「その幼茎は食用となる」とあるので、これを食べているのは、私たちの地域だけではないようだが、秋田県でも全く食べない地域もあるようだし、全国的にはどんな分布になっているものだろうか?
また、これをなんと呼んで食べているのだろうか?
心当たりの方がおられたら、情報を寄せていただきたい。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ
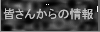 寄せられた情報へ
寄せられた情報へ
 この話題に関するメールはこちらに(assoonas@chokai.ne.jp)
この話題に関するメールはこちらに(assoonas@chokai.ne.jp)