夕顔を食べる
夕顔(ユウガオ)をご存じだろうか。
源氏物語にも夕顔という女性が出てくるが、ここで話題にするのはそれではなく、植物のユウガオのことである。
夏の夕方に白い花が咲き、翌朝しぼむことからこの名がついたが、ヒルガオ科に属するアサガオ・ヒルガオ・ヨルガオと同じ仲間ではない。まれにヨルガオをユウガオと呼ぶこともあるが、ここで扱うのはウリ科で大きな果実ができるユウガオである。
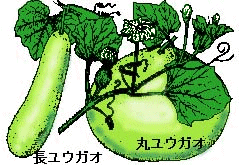
左がその図である。ウリ科に属する1年生のつる性草本で、長ユウガオと丸ユウガオがある。
丸ユウガオは主として「かんぴょう(干瓢)」の原料になる。(下の写真)
完熟した丸ユウガオの果実は外皮を乾燥して、火ばち、炭取りなどとしても使う。
(平凡社「世界大百科事典より)
 いっぽう長ユウガオのほうは、事典によると「若い果実を食用にする」とある。
いっぽう長ユウガオのほうは、事典によると「若い果実を食用にする」とある。
私の育った地域(秋田県の本荘由利地方)では、ユウガオといえば長ユウガオのことであり、小さい頃からずっと食べてきたので、「食用にする」という記述を読んでも違和感を持たなかったのだが、ある会合に出たとき、「全国的には長ユウガオをほとんど食べないらしい」という話が出た。
その会合に参加していた他県出身の人も「そういえば、こちらに来てから初めて食べましたね」と言う。
職場で話題にしたら、やはり同じような反応だった。
長ユウガオも丸ユウガオのようにカンピョウとして加工するか、スイカを栽培するときの接ぎ木の台木として栽培されていることが多いのだという。
私の地域では長ユウガオの若い果実(果肉の部分)をみそ汁の具にして食べることが多い。ユウガオだけのみそ汁もあっさりした味で美味しいが、その他に「けんちん汁」や「クジラ汁」に使うこともある。
あるいは醤油に砂糖を加えて甘く煮つけたり、だし汁で煮て食べることもある。あんかけにしても美味しい。ちょっと変わった食べ方としては、ゆでただけのものをさしみのように切ってわさび醤油で食べるというのもある。
クセのない淡泊な味で、私は大好きなのだが、これを食べている人が全国的にはほとんどいないとなると、本当に「オラホだけかな」ということになってしまう。
これまでメールや掲示板等でいろいろ聞いてみたのだが、お隣の青森県でもあまり食べないようだし(食べたことがあるという人もいるが)、関西方面では食べないという情報が多かった。
引き続き情報を集めて、このページに載せていきたいと思う。全国各地からの情報をお願いします。
このコンテンツをアップしたあとに、地域のJAの情報誌を見たら、興味深いことが書かれてあった。
私の町の近くの金浦町に住む男性からの投書である。「野菜農家であっても先祖代々からの伝えで『夕顔』を栽培してはならない家があることは、私の地域ではよく知られていることなのですが、理由を知りません。だれか分かる方は教えてください。ちなみに、そういう家であっても食べることはさしつかえないそうです」
ふーむ、これもなかなか面白い話である。こちらについてもお知りの方は教えていただきたい。
 ホームページに戻る
ホームページに戻る 前のページへ
前のページへ
 この話題に関するメールはこちらに(assoonas@chokai.ne.jp)
この話題に関するメールはこちらに(assoonas@chokai.ne.jp)
いっぽう長ユウガオのほうは、事典によると「若い果実を食用にする」とある。